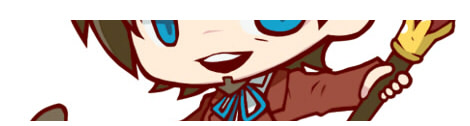
!!! R-18 !!!
裏/ゴリバレ後/付き合っている二人
「におうだち〜」の続きの付き合い始めた二人の話
WEB再録の短編2本を含みます
裏/ゴリバレ後/付き合っている二人
「におうだち〜」の続きの付き合い始めた二人の話
WEB再録の短編2本を含みます
続・におうだちする英雄の大剣を旅芸人がかばうする話
魔物の最後の一匹が黒い煙になって消えるのを、イレブンは見届ける。
改めて周りを見渡しても、もう魔物の影は残っていないようだ。イレブンは詰めていた息を吐き出して剣を鞘にしまう。周りの仲間達も次々に警戒を解いて、武器をしまったり下ろしたりするのが見えた。と、その中の一人と不意に目が合った。
「シルビ――」
戦闘終了にほっとしたように穏やかな笑顔を浮かべる彼へ呼びかけようとした、その瞬間。
「ゴリアテ」
「きゃっ」
イレブンが近付こうとするより早く、彼の腕を横から掴む影がある。その影はシルビアが何か反応するのも待たず、ぐいとその腕を引いた。道を外れ、木の生い茂った茂みの方へと彼を連れ去ろうとする。
「ちょっ……グレイグ!」
シルビアをそんな名で呼ぶのは、当然グレイグだ。慌てたシルビアがその腕をほどこうとするが、がっちりと掴んだ指はそう簡単に剥がれない。既に歩き出し始めているグレイグにぐいぐいと引かれるまま、つんのめるようにして着いていくしかない。
「ごめんなさいイレブンちゃん、先に行ってて! ――んもうグレイグ、ちょっと待ってったら……!」
「あ、うん……、わかった。気をつけて、ね……?」
慌ただしく茂みの向こうに姿を消す二人を、イレブンは小さく手を振って見送った。がさがさという音やシルビアの文句が段々と遠くなる。
その場に残された六人の仲間たちは、何ともなしに視線を交わしあった。
「……シルビアもああ言ってたことだし」
様々な意味を込めた沈黙を破ったのは、結局イレブンだった。
「僕たちは先に行こうか、しょうがないから」
仲間たちは苦笑いしたり肩をすくめたりして頷く。誰も何もツッコミを入れないのは、この展開が慣れたものだったからだ。この展開――つまり、戦闘の後にグレイグが強引にシルビアを連れてどこかに消え、イレブンたちが先行するという展開に。
少し前、戦闘の後にグレイグが目眩を起こすということが頻繁にあった。あまりにそれが繰り返されるのでイレブンたちは彼の体調を心配したのだが、問い詰められたグレイグが吐いたのだ。それは本当は目眩ではなく――実は、尿意を催していたのだと。若い女性陣、特に彼の仕えるべきあるじたるマルティナもいる場所で、便所に行きたいとは何となく言いづらくてごまかしていたのだと彼は語った。
ちなみに、毎回その目眩――というのは詭弁で用を足していたらしいわけだが、それにシルビアを付き添わせていたのは、用を足している間の見張りを頼むためだそうである。
そんなわけで、戦闘後にグレイグがシルビアを連れてどこかに消えるのは、みな慣れたものだったのだ。
――最も、そんな言い訳を信じているのは純粋なセーニャくらいのものだったが。
「グレイグ、――グレイグ!」
小さく呼ぶ声を無視し、グレイグはぐいぐいとその腕を引いて茂みをかき分ける。もうずいぶん離れたからイレブンたちの目から自分たちの姿は見えないだろうが、念のためもう少し離れておきたい。
見渡せば、右の方に少し開けた場所がある。そこを目的地と定め、グレイグはシルビアの腕を強引に引いた。
「きゃっ」
足をもつれさせながらついてくるシルビアを、その場所にあった太い木の方へと乱暴に押しやる。両手をその幹に付き顔を打つことだけは避けたシルビアだったが、文句を言おうと振り返る前にグレイグがその背から抱きついてきて、動きは封じられてしまった。その上、不埒な手は臀部を這い回り鷲掴むように揉んでくる。
「ま、待ってってば! ちょっと急ぎ過ぎじゃない!?」
ウエストまで辿り着いた手が衣服にかかり、下着ごと衣服をずり下げようとしてくる。半分ほど下げられてしまったところで、シルビアはやっとその手を掴んだ。
振り返って睨みつけるが、グレイグと視線は合わなかった。彼の瞳は、はみ出したシルビアの尻へと向けられていたからだ。シルビアの言葉に目もくれず、更に服をずり下げようとしてくるグレイグの手。シルビアはその腕を掴む指に力を加える。骨が軋みそうなほど掴まれてやっと、グレイグは顔をあげた。
――ぎらぎらと燃える瞳。自身を阻むものを射殺すような鋭さの。視線の強さにぎくりと怯みながらも、シルビアはその瞳を見返して睨んだ。
「ねえ、聞いてる? グレイ――、んむ」
しかしシルビアの問いへの答えは返ってこなかった。無言のまま顎が掴まれ、唇が塞がれる。抗議のために開けかけていた唇の間から急くように舌が入り込んできた。上顎の裏を舐められては弱い。ぞくぞくと登ってくる感覚に、思わずシルビアが指から力を抜けば、その隙に服はずるりと引き下げられてしまった。太ももと尻に冷たい外気が触れて背筋がぞわりとした。
用済みとばかりに唇が解放される。突き放されるようにして、シルビアはまた木に凭れる体勢になった。腰を強く掴まれる。振り返る視線はやはり合わない。――彼は、このまま進めるつもりなのか。気をそらすためのキス一つしかくれず、言葉もなく一方的に、まるでただの性欲処理のように。
「――ねえ、グレイグ」
「……」
「グレイグ!」
ひときわ強く怒りを込めて呼べば、ようやくグレイグは動きを止めた。はっとしたようにやっと合った視線は、しかし二度ほどのまばたきの後にふいと逸らされる。だが今度の視線は別に尻を見ているわけではなく、どこか斜め下の地面に向けられていた。その視線に先程までの射殺しそうな鋭さはなく、どうやらやっと正気に戻った彼は、バツの悪さを感じているらしかった。もごもごと口を動かし、ぼそりと呟く。
「……すまん」
「んもう、怒ってるわけじゃないのよ。何か言ってくれないと怖いじゃない」
「怖がらせるつもりはないんだ、悪かった」
「わかってるってば。アタシは言葉がほしいだけなの」
――だってアタシたちは、恋人同士なんでしょ?
シルビアはそう言って微笑む。少し恥ずかしくて、ぼっと頬が熱くなる気がした。グレイグの顔も見る間に赤くなる。落ち着かなげにうろうろと視線をさまよわせ、そして最後に小さく頷いた。
「……すまん、ゴリアテ。したい。駄目か」
今頷いたのは一体何だったのか。恋人らしさのまるでない直球すぎる言葉に、シルビアは思わず苦笑してしまった。甘い言葉を期待していたわけではないけれど、余りに彼らしすぎる。
「ダーメ、……とは言えないわね。この子がこんなになっちゃってるのを見ちゃったら」
シルビアは背後に手を伸ばし、指先でちょんとつつく。グレイグのサーコートの、まるでテントのようになった部分を。触れた瞬間、服の上からでもわかるほどびくんとそこは跳ねた。
「さ、触るな。我慢しているんだ」
少し震えたグレイグの声に、シルビアは思わず息を吐き出した。自分で想像したよりもそれは熱く喘ぎに似ていて、そんな自分の反応にまで煽られるように更に体の熱が上がるのがわかる。
「――わかってるわよ。アタシがどれだけ、こういう状態のあなたを見てきたと思ってるの?」
「ゴリアテ」
「それにアタシだって、――ガマン、してるんだから」
先程からずっとむき出しにされたままの尻を突き出す。片手を伸ばして尻たぶを広げ、その中央が見えるように開いた。グレイグの目にはきっと、期待にひくつく熟れた孔が見て取れることだろう。
「でも一回だけだからね。みんなのとこに、早く戻らなきゃ」
「……ゴリアテ」
大きな深呼吸の音。少し時間をおいてから、何かが孔の縁に触れた。だがその太さも熱さも、シルビアの知っている一番大きなものとは違う。しかし、シルビアは触れたそれが何かに気付いて微笑んだ。
「うふふ、優しくしてくれるのね」
「当たり前だろう」
それはグレイグの指だ。あんなにぎちぎちに反応しながらも、ちゃんとシルビアの体を慣らしてくれようというのだ。
とろとろとローションも垂らされる。こんな森の中に不釣り合いな、人工的な花の香りが広がった。ぬちゃぬちゃと音を立てながら、触れた指が孔を中心にそれを塗り込めていく。
「でも慣れてきたし、ローションもあるならいきなりでも大丈夫よ、多分――あっ」
言葉の途中でつぷりと突き入れられ、シルビアは小さく声を上げた。
「多分では駄目だ。貴様を傷つける可能性は、できる限り排除したい」
――俺たちは恋人同士なのだから。
耳のそばで囁けば、返ってきたのはきゅんと甘く指先を締め付ける反応。余りの可愛らしさに思わず笑めば、シルビアが勢い良く振り返る。薄く涙を浮かべた睨みには凄みなどなく、尖らせた唇がまた愛らしいと思ってしまうグレイグだったが、言わんとすることはわかる。
「ん、すまん。貴様の反応が愛らしくてな」
「もう……。焦らされる方の気持ちも考えてよね」
それはお互い様だ。そう答えたグレイグは、腰を突き出すシルビアの背に沿うように自身も身を倒した。
「愛している、ゴリアテ」
「うん、アタシもグレイグが……、すき」
触れ合う唇。先程の油断を誘うようなものではなく、もっと暖かさのあるキスだった。口を開き舌を絡め、暖かく柔らかい感触に溺れる。
やがてグレイグが挿れたままだった指をゆっくりと動かし始めれば、シルビアからは甘い声が上がった。その音も恋人の唇に吸い込まれてしまう。上からも下からも労るような優しい愛情を感じて、シルビアはうっとりと目を閉じた。
:
: