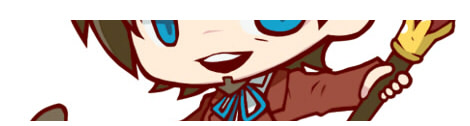
フユキ地方のトーサカシティでジムリーダーをしているトキオミさんと
その弟子キレイ、謎の居候ギルガメッシュ というポケモンパロ。
ほんのりと言→時、ギル→時を含みます。
ポケモンの世界観、設定などは、ゲームよりアニメに近いかも。
イワークをスプリンクラーで倒してもいいような自由な感じ。
なので、各ポケモンのスペックや技の性能などもかなり適当です。
その弟子キレイ、謎の居候ギルガメッシュ というポケモンパロ。
ほんのりと言→時、ギル→時を含みます。
ポケモンの世界観、設定などは、ゲームよりアニメに近いかも。
イワークをスプリンクラーで倒してもいいような自由な感じ。
なので、各ポケモンのスペックや技の性能などもかなり適当です。
トーサカジムのまるで優雅じゃない一日
「あの、すみません!」かけられた声に綺礼は振り向く。立っていたのは、横にミミロップを従えた少年だった。どこかで見たことがある、と綺礼は気付かれない程度に首を傾げた。
「今日は、ジムはお休みなんですか?」
その言葉は、綺礼の手にある看板を見たから発せられたものだろう。『本日はお休みさせて頂きます』と書かれたそれは、彼の手によって今にもジムの入り口にかけられようとしているところなのだ。
「ああ。師の家族…ジムのトレーナーたちが出かけていてね。トレーナーの数が足りないから、今日は休業とすることにしたのだよ」
「そうですか…。作戦を練りなおしてきたので、また挑みたかったんですけど」
トレーナーは傍らのミミロップにちらりと視線をやる。その言葉を聞いて綺礼は、彼が先日このジムに挑んでジムリーダーに敗北したトレーナーだということに気がついた。
「何、明後日には休業も開けるだろう。その時にまた来るといい」
「はい、わかりました!」
物分かりよく少年は頷いて、行こうミミロップ、と踵を返した。走っていく後ろ姿に、若いなと、恐らく十くらいしか変わらないはずの綺礼は思ってしまう。
ポケモントレーナーとして成功すること、に、綺礼は何の意義を見出すことも出来ない。ジムリーダーとして若い世代の夢を応援したいという父、伝説のポケモンたちと相対したいと野望を抱く師。綺礼の周りには何人ものトレーナーたちがいるが、その誰の意思も、綺礼の心を動かすことはなかった。
───とはいえ。
「綺礼、何かあったのかい?」
「時臣師」
今看板をかけたばかりの扉が開いて、現れたのは綺礼の師である時臣であった。柔らかな茶色の髪と宝石のような蒼い瞳が、明るい朝の日差しにきらきらと光って眩しく、綺礼は目を細めた。
次いで、その足元からひょこりと大きな紫の耳も覗く。こちらは、時臣のパートナーの一匹であるエネコロロだ。柔らかな笑みを浮かべる時臣とは対照的に、エネコロロは不機嫌な顔をしていた。
「…いえ、何もありませんが。いかがしましたか」
「看板をかけるだけだと言っていたのに随分と遅いから。何かあったのかと思ってね」
何もなかったならばよかった、と時臣は微笑む。
「終わったならば中に入ろう。一緒にお茶でもどうだい」
「ありがたく頂戴致します」
「ふふ、そんなにかしこまらないでおくれ。今日は葵もリンもいないから。…寂しいんだ、綺礼」
などと。少し背の高い綺礼を上目遣いで見ながら、照れたように頬を赤くして。はにかむような笑顔で。
「……………………………………ッ!?」
あざとすぎる師の無防備な笑顔に、綺礼が思わず一歩踏み出しかけた瞬間。脛に鈍い痛みが走った。
「あ、こら、エネコロロ!」
エネコロロが鋭いネコパンチを仕掛けてきたのだ───そんな技など無いくせに。慌てたように時臣が二人の間に割り入ってくるが、エネコロロは綺礼を睨みつけて視線を離さない。気紛れなはずのこのポケモンは、どうやらこの個体に限っては随分トレーナーに忠実らしい。自分のあるじに向けられた不埒な視線が許せなかったのだろう。
「す、すまないね綺礼。この子は余り他人が得意じゃないらしくって」
しかしそんな思惑など知らず、困ったように眉を下げ、エネコロロの頭を撫でながら時臣は綺礼を見上げる。
「………いえ、大丈夫です」
「そうかい?ならばいいのだが…」
いきなり攻撃をしては駄目だよ、と今度はエネコロロに向けて時臣は言う。ニャオンと彼は甘えた声をあげ、自分の頭に触れるあるじの手に耳を擦りつけた。まったく、「猫をかぶったような」とはよく言ったものだ。
「さてと。で、綺礼、看板はかけられたのかい?」
「はい、そちらは問題なく」
「ありがとう。これで、今日はもう訪ねてくる者はいないだろうな」
話を元に戻した時臣は綺礼の指さした先を見、満足そうに頷いた。
「まずは、お茶にしようか。そうそう、この間買った茶葉がとても良い香りでね…」
機嫌よく話をしながら、トーサカシティのジムリーダーは、彼の弟子と彼のパートナーを伴ってそのジムの中に消えた。
二人と一匹を抱く建物の扉には、休業の看板が揺れている。
話は戻るが、誰の強い意志も動かすことのなかった綺礼の心を動かしたのは、他でもないこの時臣という男だ。綺礼は、にこにこと紅茶について語っている傍らの師の横顔を盗み見た。この男に綺礼は、この世の愉悦を見出している。
何故ならば。
「それでね、その時葵が………ぅあ!?」
「師よ!」
合わせていた視線ががくりと下がる。話に夢中だった時臣が、なにもない所でつまずいたのだ。しかし間一髪、綺礼の出した腕がその体を支えた。彼の腕によって胸のあたりを抱きかかえられ時臣は、顔面を床に打ち付けるとなどという無様な展開からは逃れられた。ほっと息をつく。
「あ、ありがとう、綺礼」
「これしきのこと」
バツの悪そうな苦笑に、綺礼も薄い笑みで返す。時臣はもう一度ありがとうと言った。
………これである。
時臣という男は、その優雅な外見からは想像もつかないほど、途方も無いうっかりさんなのだ。何もないところで転ぶなど日常茶飯事だし、難しい言葉を言おうとすれば舌を噛む。昨晩散々戦術を考えていたのにいざバトルとなれば先頭のポケモンを間違えていたり、道具を持たせるのを忘れていたり。本棚から本を取り出そうとして足の上に落としたり、料理をしようとすれば調味料を間違えた上に焦がしたり。何というあざとさか!
彼の弟子として過ごしている内に、綺礼はそんな彼の姿を何度も見た。ふいにうっかりを繰り広げ、なのに彼は家訓を守るべく優雅な姿を保つ努力を忘れないのだ。そんな二つの姿を見せる師に、いつしか綺礼は愛しいと思う心を抱いていたのである。
彼を支えたり甘やかしたり、時には手酷く裏切ってみたりしたい。
それが、トレーナーとしての修行に意義を見出せない綺礼がここにいる理由だった。
「…時臣師」
「な、何だい、綺礼」
「今日は、二人でゆっくり過ごしましょうね」
「そうだね、久しぶりの休日だ。ゆっくり過ごそう」
転ぶのは阻止できているというのにいつまで経っても時臣を抱きかかえる腕を離さない綺礼に、とうとうエネコロロのみだれひっかきが炸裂した。
:
:
: