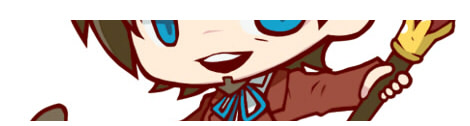
弟子が師匠にお触りする短編三本+α
触るだけでそれ以上の手は出さない、大変健全なお話
娘の指を父親がぺろぺろするシーンが一瞬だけ含まれます
触るだけでそれ以上の手は出さない、大変健全なお話
娘の指を父親がぺろぺろするシーンが一瞬だけ含まれます
ただのスキンシップですので。
【case1:】朝の支度の場合「う…ん………」
瞼を閉じていても遮断しきれない明るさと揺さぶられる感覚、そして何度も自分の名を呼ぶ声に、とうとう時臣は負けた。
ゆるゆると目を開けば最初に真っ白なシーツが目に入り、そこから視点を上げていくと、ベッドの傍に跪いた人影が見える。爽やかな朝にそこだけ影が佇んでいるような黒い姿。綺礼だ。
「おはようございます、時臣師」
「………、おはよぅ、きれぃ」
噛み殺しきれなかったあくびの余韻でふわふわとした声になってしまったが、何事もなかったかのように取り繕う。弟子の方も何も気づかなかったように無表情を貫いてくれたので、時臣はほっとした。
「ん〜……っ」
背を支えようとしてくれる手を断って、自力で上半身を起こす。下半身を毛布の中に残したまま大きく伸びをすると、眠っている間に固まっていた筋肉や骨が気持ちよく軋んだ。ふぅ、と満足気な吐息を漏らしてやっと、時臣は傍らに佇む綺礼にまっすぐな視線を向けた。
「ありがとう。起こしに来てくれたのだね」
「はい。そろそろ朝食とのことですので」
そんな綺礼の台詞に時臣は枕元の時計に目をやり、眉をひそめた。
「ああ…、もうこんな時間だったのか」
昨夜は、新しく手に入れた魔術書に夢中になりすぎてしまい夜更かしをしてしまったのだ。そのせいで、いつもならばとっくに起きているこんな時間まで寝てしまっていた。早く身支度をしてリビングに行かなくては。優雅を重んじる遠坂家の家長として、妻や娘に失態を見せる訳にはいかない。
「ありがとう綺礼。すぐに身支度をして行こう」
「それならば私も手伝いましょう」
「うん?結構だ、君の手をわずらわせるなど…」
「いえ、手伝ったほうが効率がいいはずです。お手伝いします」
私の弟子はこんなに頑なな人間だっただろうか…と時臣が考えている間に、綺礼は素早くクローゼットの前に移動していた。凝った装飾の扉を引き開けて、中を物色している。
「師よ、本日はどれをお召しになりますか」
「あ、ああ…いや、特に決めてはいなかったが」
「それならば私が適当に選びますが、構いませんか」
「ああ、頼むよ」
クローゼットに上半身を突っ込んだ綺礼は、てきぱきとシャツやスラックスを取り出して自身の腕にかけてゆく。靴下やタイまで取り出していくのを見てやっと、彼が本気で自分の身支度を整えるのを手伝おうとしているのだ、と時臣は認識したのであった。
そうとなれば、当人である自分が座ったままぼんやりしているわけにも行かない。時臣はベッドから出て、とりあえずは寝巻き代わりのバスローブを脱ごうとした。
「いえ、師はそのままで」
「うわ」
いつの間に移動してきていたのだろう、耳のすぐ後ろで綺礼の声がした。慌てて振り返ればすぐそこに無表情の弟子が立っていたものだから、時臣は驚いてベッドに尻もちをついてしまった。優雅ではない、と動いてくれるのは思考だけで、実際の動作にはつながらなかった。時臣がベッドに座り込んだのを、ちょうどいいと捉えたのだろう。綺礼は先程までと同じようにベッドの脇に膝をつき、身を乗り出した。
「師よ、シャツはこちらでよろしかったですか」
「あ、ああ」
時臣の座っているすぐ横に、持っていた衣装一式を置く。師の顔を見上げて確認を取った後、綺礼は一つ頷くと、
「では、失礼して」
バスローブの腰紐に手をかけ、一気に解いた。
動かない―――いや、動けない時臣をいいことに、前を開いたバスローブを肩から落とし、袖から腕を抜く。その間数秒。たった一枚で時臣の体を守っていた厚ぼったく柔らかい生地は、簡単にただの布切れになってしまった。あとには下着一枚て思考停止した時臣だけが残される。
「腕をこちらへ」
「……………………………えっ、あ、」
綺礼は、クローゼットから自身の持ってきたシャツを取り上げると、完全に固まってしまっている時臣の腕に触れた。思考が全く追い付いていないのだろう、時臣の腕は油をさしていないブリキ人形のようにぎこちなく上がる。
その指先を揃えるように押さえられ、シルクのシャツの袖が慎重に通されていく。肌触りのいい布地が肌を擦る感覚に、自分で着るときには感じないくすぐったさを覚え、時臣は小さく身震いした。
片方の腕が通ると、逆の腕も。両腕が通ってしまうと、手首のボタンがとめられた。綺礼の腕が前に回り、そのまま前のボタンもとめるのかと思ったが、
「っふ、何を………」
その手は布地を素通りし、その中の時臣の素肌に触れたのだ。胸から腹までを、両手で掴むように撫でる。乾いた温かい指先の皮膚はかさかさと硬く、それでいつも服で隠される敏感な肌をなぞられるのは、ぞわぞわと妙な感覚を生んだ。落ち着こうと大きく息を吐くが、どうにも熱と湿気を含んだ吐息になってしまい、気恥ずかしさを覚える。
「すみません。随分と触り心地がよさそうだったので」
「───っ!」
しかし綺礼は無表情のままそんなことを言い、時臣の体に触れたままの手をもう一度上下に動かした。思わずその腕を押さえるが、綺礼はしかし、同じ顔でちらりと時臣を見上げただけだった。
「…離していただけますか。ボタンがとめられませんので」
「あ…、ああ」
そしてまた、何事もなかったかのように時臣の着替えを再開させた。彼の真意がつかめないまま、時臣はシャツの前が上から閉じられていくのを見ていた。優雅たれ、優雅たれ、と自分に言い聞かせながら。
真意はつかめずとも、身繕いを手伝ってくれるというその行為が、善意以外から発生するとも思えない。それはらば、師として甘んじて受けるべきだろう。不器用な弟子の、彼なりの優しさなのだろうとは思うものの、妙な感覚は消せやしない。
「足に触れてもよろしいですか」
今度は靴下を取り上げて、綺礼が時臣を見上げる。時臣が頷くと、綺礼は時臣のふくらはぎを支えて自身の立てた膝の上に載せた。スリッパを脱がせてその膝の裏側まで指先を滑らせたあと、丸めた靴下をつま先にかぶせてくるくると一気に履かせる。最後に足首の後ろとふくらはぎの部分を足に沿うように伸ばせば、紺色の靴下はぴったりとその左足を覆った。仕上げにとソックスガーターを膝の下に回してベルトを嵌め、ぱちりと靴下をとめる。完璧な出来に満足して、綺礼はその足を床におろした。
続いて、右足にも同じ作業を行う。こちらは足首の部分がだぶついてしまって一気にとは行かなかったが、なんとか同じようにソックスガーターまでを完璧に施した。
ガーターなど、普段であれば衣服に隠されて見えない部分である。それを今、妻でもない他人が見ているのだと思うと、時臣は複雑な気分になった。いや、その前に足や腹や胸や、ほとんど全ての素肌も見られてしまっているのだが。
妙な顔をしている時臣に気づかないのか、自らが身につけさせた靴下と足を満足気に眺め、綺礼は次の指示を出した。
「次は、下を。立っていただけますか」
「わかっ、た」
一度意識してしまうと、急に恥ずかしくなる。綺礼の言に従って立ち上がったところで時臣は酷く後悔した。なぜならば寝巻き代わりのローブは脱がされ、下は靴下と下着しかまとっていないのだ。心もとない状態の下半身を綺礼の前に晒すことになってしまったわけである。ちなみに下着は体にフィットしたグレーのボクサーパンツである。
もじ、とさり気なくシャツの裾を伸ばして少しでも足を隠そうとするが、綺礼の選んできたそのシャツは伸びる素材ではなく丈もぴったりだったので、無駄な努力となってしまった。
「……………」
これはまずいな、と思ったのは、だが自分だけであったらしい。足元に跪いた綺礼は、目の前の師の足が丸出しであることなど何も気にならない様子で、ベッドの上から取り上げた赤いスラックスの折り目を伸ばしている。
:
:
:
■他2本+α
・【case2:】電車で移動する場合
・【case3:】座学での修行の場合
・【rare case:】師匠が反撃する場合