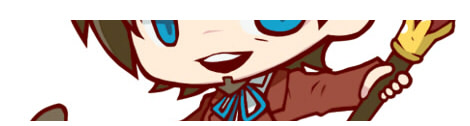
!!! R-18 !!!
転生記憶なし師弟が出会いお付き合いをする話。
現代パラレルです
ちょっとだけ年齢操作有り。甘め。
また、局地的にギルガメッシュの出番がありますが、
恋愛展開には絡みませんのでご注意ください。
転生記憶なし師弟が出会いお付き合いをする話。
現代パラレルです
ちょっとだけ年齢操作有り。甘め。
また、局地的にギルガメッシュの出番がありますが、
恋愛展開には絡みませんのでご注意ください。
貴方のいる世界に、私がいるということ
「夢、だと?」床に寝転がり菓子を貪っていたギルガメッシュは、言峰綺礼の持つクロッキー帳から視線を上げ、彼の横顔を見ながら聞き返した。
「その男が夢に出てくるというのか」
「……ああ」
「ほう」
「……もう、何度も出てくる。昨夜は特に鮮明に見えた」
「ほー」
ギルガメッシュは、自分が質問したことを忘れたような気のない返事を返して仰向けにバタリと倒れた。手を伸ばして、近くに置いてあった菓子の箱からプレッツェルを取り出す。前歯で折り取れば、ポキリと小気味いい音がした。
夕方の屋上。中学生や高校生ならまだしも、大学生にもなって、生徒が入るのを禁止されている屋上にこっそり登りたがるような者はほぼいない。だからこの場所はギルガメッシュだけの特等席だったはずなのに、何故か今日は綺礼もいる。さらに珍しいことに、その手にクロッキー帳と鉛筆など持って。
そもそも綺礼とギルガメッシュは別段仲がいいというわけではない。綺礼は一年生、ギルガメッシュは三年で一度留年した四年生。ちょうど一単位だけ同じ授業が重なっているというだけの関係だ。授業中はギルガメッシュが好んで綺礼の近くの席に座るせいでそれなりに会話はあるが、それ以外ではほとんど関わりはない。
だから、綺礼は別にギルガメッシュに会いに来たわけではないのだろう。たまたま、人のいなそうな場所を選んだらギルガメッシュがいたというだけで。
「そのクロッキー帳はどうしたのだ」
関わる必要はないとわかっていても、好奇心は勝つものである。ギルガメッシュは菓子をもぐもぐと咀嚼しながら、寝転んだせいでその裏側しか見えなくなったクロッキー帳を指さした。
「購買に売っていた」
「うちの学校の何の授業でそんなものを使うというのだ……。店頭に置いておくだけ場所の無駄だなあ」
「だが私にとっては今必要な物だった。無駄ということもないだろう」
「ふむ、屁理屈だな。しかし、貴様に絵心があったなど初めて知ったぞ」
「皮肉か?」
ギルガメッシュと会話している間も、綺礼の手は休まず紙のキャンバスの上に鉛筆を走らせ続けている。
ギルガメッシュの揶揄う口調の通り、その線はガタガタだし筆圧もまちまちだ。絵など描き慣れていないのだろう。だがそんな荒い絵ではあるが、それは一人の男の頭部を描いているのだということはわかった。
緩やかにうねる髪、太い眉、シャープな輪郭と顎鬚。そういう特徴を強調された絵柄で描かれているのは、遠くに視線をやった男の横顔。彼よりも少し背の高い人物が隣から見下ろしているような斜め上からの構図は、確かに綺礼が見た通りの光景なのだろう。綺礼は、背が高いので。
この場所には今ギルガメッシュと綺礼しかいない。だから、この男はこの場所にはいない。それなのに、まるで目の前にいるかのように綺礼はその姿をクロッキー帳のキャンバスの上に写しとっていく。それが不思議だと思ったギルガメッシュの問いへの返答が、冒頭のそれだった。夢で見たのだ、と。
次に綺礼はその男の瞳の位置に線を引き、少し悩んだあとにその線を消した。再度黒鉛がキャンバスに触れた後は手を休めず、紙の上にはまつげの長い伏し目がちな瞳が描かれていく。
「……」
しかし、その手は不意に止まる。
「どうした、続きを描かんのか」
「……この人の、目の」
綺礼の言葉は、ギルガメッシュに返したと言うよりはこぼれ出たと言った方が正しいような音をしていた。
「色を、私は知っているのに、わからないのだ」
「知っているのに、わからない?」
「知っている……と、思う。私の見た夢に色はない。夢の中で彼の瞳は灰色だが、本来は灰色ではないと私は知っている」
まるでなぞなぞのような言葉だ。綺礼の言葉はぽつりぽつりと途切れて、彼自身でもよくわからないままに発しているようだった。
鉛筆で描かれたモノクロの男。それと同じ色彩で、綺礼はその男を夢の中に見ているのだろう。
「お前は、それが誰なのか知らんのか」
「ああ、知らない。夢には出てくるが……声も、名もわからない」
「ほう」
キャンバスに目を落としたままの綺礼を、仰向けに寝転んだまま斜め下からギルガメッシュは眺める。
「そんな相手を、何故絵に描く?」
「何故、だと?」
ギルガメッシュの目を見つめ返し、綺礼がぱちぱちとまばたきをした。
「……何故、なのだろう」
そして、またキャンバスに目を戻す。しかしその黒い瞳に先程までの霧の中を彷徨っているかのような困惑は無く、代わりに浮かんでいるのは疑問のようだった。
何故、夢に出てきただけの見知らぬ男を、こうして目に見える形で描こうと、残そうとしているのか――。
「その男に会いたいのか?」
『会いたいのか?』。
ギルガメッシュにかけられたその問いに、綺礼は迷いながらも頷く。ノーかイエスかなら、イエスに近い。会えば、何かしらはわかるだろうから。
それになるほどと答えながら起き上がるギルガメッシュの次の声はとても普通だった。
「実はな、綺礼。我は、その男に心あたりがある」
その意味を、一瞬聞き逃してしまいそうになるほどに。
「な、んだと……!?」
がばっ、と勢い良く顔を上げる綺礼に、赤い目をきゅうと細ませたギルガメッシュは焦るな焦るなと笑いかけた。
「そんな髪型で生意気にも顎鬚なんぞ生やしている雑種など、あいつ以外に我は知らん」
指先でつんつんと、キャンバス上の男の顎鬚をつつく。綺礼は誘われるように自分の描いた絵に目を落とし、またギルガメッシュに目を戻した。
「……その人は、確かに私が夢に見たこの人なのか?」
「それは知らん。お前の個性的な絵から思いつく人間が一人いるというだけだ。お前が会いたいというのなら、我が取り次いでやろう」
今度の綺礼の逡巡は一瞬だった。
「……頼む」
「ああ、了解した」
そう言ってギルガメッシュはズボンのポケットからスマートフォンを取り出した。シンプルな形状の機種のはずだが、どぎつい金色のフレームが取り付けられており、金色の剣と赤い石をあしらったストラップが揺れていた。その赤い石は彼の瞳に似て見えた。
取り出したスマートフォンを、ギルガメッシュは何やら操作する。するすると画面の上を滑る指は、どうやらキーパッドを操作しているらしい。つまり、メールでも作成しているのだろう。
「……よし、これでいい」
暫く後、彼はスマートフォンの上部にあるボタンを押して綺礼をにやりと見上げた。
「明日の昼。駅前のカフェに来いとあいつに伝えておいた。うまくやれよ」
「……彼からの返答があったのか?」
見ていた限り、ギルガメッシュが一方的にメールを送っていただけの様子だった。だから伝えたのは確かだろうが、相手の方がその呼び出しに応じたのかどうかはわからないはずである。
「何、あいつは我からの呼び出しなら応じないはずがないさ。それに奴は壊滅的な機械音痴でな。メールを見ることはできるが、返信はできんのだ。期待するだけ無駄だぞ」
「そうなのか……」
夢の中のあの男は随分理知的な顔をしていると思ったが、と、少しだけ綺礼は落胆する。しかしそんな綺礼の感情の変化など気にもとめず、ギルガメッシュは機嫌がいいらしかった。
「ククッ、明日が楽しみだなァ。我は『お前に会いたいという奴がいる』とだけしか奴に伝えておらん。明日お前らが会って、何故自分に会いたかったのかと奴がお前に聞いた時、夢に貴方が出てきましたとでも答えてみろ。奴に不審な目を向けられた瞬間のお前の顔は見ものだろうなあ!」
「……」
随分と勝手なことを言う。そもそもその『あいつ』とやらが綺礼の夢に出てきたあの男と同一人物であるという保証はないのだ。違った場合、その昼食の席はひどく居心地の悪いものになるだろう。そうしたらギルガメッシュのせいだと愚痴って良いものだろうか。『あいつ』とやらとギルガメッシュの関係は知らないが。
「……そういえば、その人の名は何というのだ?」
「名か?出会ってから本人に問え」
少々カチンとはきたものの、引き下がる。確かに、本人に聞いたって問題はないはずだ。夢に出てきたという理由で、会いたいのだから。
「その人とお前はどんな関係なのだ?」
「ああ、近所に住んでいた、いわゆる幼なじみというやつだな。奴の方が一つ上だ。……なんだ、急に質問攻めか?あとひとつなら答えてやろう」
「……彼の、瞳の色は?」
「自分で確かめるがいい!」
そういって、ギルガメッシュはケラケラと笑う。
綺礼は。
沈みゆく夕日に燃えるような色へ染められたキャンバスの中の男に、なぜだか既視感を覚えていた。
*
気楽に鳴り響く着信音。ベッドに寝転んで雑誌をめくっていた彼は億劫そうに携帯に手を伸ばす。しかし受信したメールの送信者欄の名前を見ると、一気にその表情は笑みに変わった。足を振り上げて反動で起き上がると、メーラーを操作して受信メールを開く。
『全く、お前はいつも余計なことばかりする』
本文は、非常に短く。それだけだった。だが、彼はその短い文章に込められた感情を読み取っていた。思わず上がる口角。 『だが、貴様にとっても喜ばしい出来事だろう?』
そう打って、彼は返信ボタンを押した。無事に送信が完了したところまでを見届けると、音を消して机の上へ放る。どうせ返信などこないだろうし、来たとしても恐らくは想像の範囲内の内容だろうから。
彼は仰向けに寝転がり直し、目を閉じる。近い将来に訪れるであろう愉悦の気配に、口元を歪ませた。
*
綺礼はいつになくそわそわしていた。
人と待ち合わせをすることも、カフェという場所に来ることにも、そう慣れていない。だが一番の原因はそれではない。もちろん、待ち合わせの相手のせいである。
名も立場もわからぬ相手。わかっているのは顔の造形と、ギルガメッシュの知り合いだということだけ。その顔の造形にしたって脳内にあるのはモノクロの映像だから、役に立つかはわからない。
ギルガメッシュに伝えられたのは、昼、という漠然とした時間指定だったから、大体十二時くらいだろうと見当をつけ、大事を取って十一時からここに待機している。
昨晩はうまく寝付けなかったようで、寝不足のように頭ががんがんとしていた。
「……」
昼時だというのに、カフェ内に人は少ない。恐らく、近くにファーストフードの店がたくさんあるかだろう。学校にだって学食があるから、わざわざコーヒー一杯四百八十円というこんなオシャレなカフェに来るものは少ないのだ。綺礼だって、こんなことでもなければ入ることのない場所だっただろう。
綺礼が座っている席の場所は、一応ギルガメッシュにメールで伝えた。ギルガメッシュの方から『彼』へ伝えてくれるらしい。まったく、面倒なことだ。『彼』の名や顔を教えてもらえれば、こちらからコンタクトを取れるというのに。
だがギルガメシュはこの状況を面白がっているらしく、『彼』についての情報を漏らす気はさらさらないようだった。
「……」
プラスチックのコップに結露した水滴が流れ落ちる。
腕時計に目を落とせば、十二時まではあと十分ほど。もうここに五十分も座っていたのかと改めて思う。道理で、先程からウェイトレスが何度も追加の注文を取りに来るわけだ。
彼女にとっては申し訳ないと思いつつ、量が減るどころか、むしろ解けた氷で嵩が増しているコーヒーを口に運ぶ。もともと薄くて美味しいとは言い難かったそれが、まずいと形容するべきレベルになっていた。
その時、背後から人の気配が近づいてきたことに気付く。またウェイトレスか、と彼女に申し訳なく思いながら振り返ろうとした綺礼の耳に、
「――ギルガメッシュに呼ばれて来たのだけれど。
待ち合わせの相手は、君で良いのかな?」
低く、深い声。
振り向いた綺礼の目が見開かれる。
「――――あなた、は……」
緩やかにうねる髪、太い眉、シャープな輪郭と顎鬚。
夢で見た通りの男がそこに、いた。
しかし全てに鮮やかな色がついている。
髪は鳶色で、髭も眉も同じ色。白いシャツに臙脂のベスト、焦げ茶のスラックス。首もとを飾る黒のリボンタイ。
そして、髪と同じ色の濃いまつげの下に。
その色は、あった。
「――ぁ……!!」
その色を見た瞬間、綺礼は動けなくなっていた。呻くように漏れ出る声、早くなる呼吸。息がうまく出来なくて、肺は無意味に空気を孕んで吐き出すだけのモノと化す。わけもわからないままに、目からははらはらと涙がこぼれ出していた。何もかもぐちゃぐちゃでわからない。
だがなぜだか胸がぎゅうぎゅうと締め付けられ、悲しみなのか喜びなのか判断のつかない強い感情が全身を支配していた。 ああ、ああ、助けてほしい。自分の中にある何かに気付いてほしいと、誰かの悲鳴。酷く苦しく、綺礼は心臓を胸の上から押さえつける。
「き、君?どうしたんだい!?」
突然涙をこぼし始めた綺礼の顔を、『彼』が慌てたように覗きこむ。
綺礼の漆黒を映すその一対の宝石の色は、まるで湖面のような――深い碧だった。
*
「申し訳ありませんでした……」
「いや、こちらこそ。何だか驚かせてしまったみたいで、すまないね」
数分後、衝動の収まった綺礼は、深々と『彼』へ頭を下げていた。
目元と鼻の下がヒリヒリと痛むのは、彼に差し出されたハンカチを固辞してテーブルに備え付けられていた紙ナプキンで思い切りこすってしまったせいだろう。もしかしたら赤くすらなっているかもしれなかった。
全く、なんという醜態だ。泣くという行為自体、もう随分とした記憶がない。随分どころか、物心ついてからの記憶すらない。なのにこんな時に、初めて会う人間の前で、意味もわからず顔を見ただけで泣いてしまうなんて。
「もう落ち着いたかい?」
「はい。……本当に、すみませんでした」
「構わないよ。きっと疲れているんだね。学生さんだろう?余り無理をしてはいけないよ」
『彼』はにっこりと微笑んだ。
目の前に座った彼からはふわりと、何か人工の香りがした。夢ではなく現実に、自分の前に彼がいる。夢で見た通りの姿。それに色がついて、息をして、声を発するということに、奇妙な感動を覚えた。
夢の中の衣装とは多少違うが、かっちりとした印象は変わらない。臙脂色のベストが似合っていた。夢の中のあの灰色のジャケットは、多分これと同じ臙脂色をしているのだろう。
「それで、私に何の用なんだい?ええと、……失礼だが、初対面、で良かったかね?」
「はい、そうです」
「そうか、良かった。忘れてしまっているのではないかと焦ったよ。ギルに、今日ここに来いとだけ言われただけでね、すまないが、君が私を呼んだ理由は聞いていないんだ」
初対面の君が私なんかに何の用だろう、と彼は少し首をかしげる。
一瞬迷ったが、綺礼は全てを話すことにした。
毎日見る夢のこと。誰かと話しながら歩く灰色の庭園。少し前を歩く誰か。その誰かが、あなたそっくりであったこと。それを話したギルガメッシュに、あなたを紹介されたこと。夢の中には色がなかったから、あなたの目の色を知りたかったのだということ。
頭がおかしいのではという言葉を予測した。気を悪くし怒られるのではと覚悟もした。当然だ。綺礼自身がもし彼の立場だったとしたら、そう思うだろうから。
だが綺礼の想像は、全て外れた。
「そう、か」
ぽつりと呟いた彼は、綺礼から視線を外して少し考えるような仕草を取ったあと、再度口を開く。
「……実はね、私も君を見た時、妙な既視感を覚えたんだ」
君のように夢に見たとか、そういうことはなかったと思うのだけれど、と彼は言った。
「――もしかしたら、私たちは出会うのが運命だったのかもしれないな」
或いは前世で知り合いだったとか、と言って、彼は碧い目を細めて微笑んだ。
運命。運命か。そんなもの、人を騙し取り入ろうとするときの常套句だと思っていた。決していいイメージを持っていなかったその言葉が今、胸の隙間にすとんと落ちた感覚に戸惑う。
前世。運命。そういった言葉を、初めて信じてみたいと思った。
「――そうだったら、良いですね」
そんな綺礼の返答を、彼は予測していなかったのだろう。碧い瞳をまん丸く開いてまつげを重たげにしばたかせ、そしてくしゃりと表情を崩した。
「ああ、そうだね」
余りにその様子が嬉しそうで、綺礼も思わず笑む。笑んで、今自分が笑っていることに気付いて驚いた。笑うのも、一体何年ぶりだろう。
とても不思議な気分だった。初めて出会う相手の前で表情を崩す自分。自分は彼を夢に見、彼もまた綺礼に既視感を覚えたのだそうだ。前世か、運命か。本当にそう言った言葉で表される関係だったなら、どんなに幸せだろう。
夢で見た彼の横顔と笑み、それを記憶から消したくなくて絵を描いた。そして今色のついた彼に出会い、酷く感情を揺さぶられている自分がいる。これまで出したこともなかったような、正の感情を。
つまり、私は彼に好意を持っているのだ。と、綺礼は自分の感情に結論をつけた。
思い切って、口を開く。
「――あの、もし」
「君さえよければ」
言葉を発したタイミングはぴったり同じだった。驚いた顔を見合わせて口をつぐみ、互いに無言のまましゃべる権利を譲りあう。根負けしたのは彼が先で、眉を下げた苦笑の顔のまま彼は口を開いた。
「……これも、何かの縁だろう。君さえ良ければ、今後とも、仲良くしてもらえるかい?」
思わず綺礼は胸を抑える。高鳴る心臓が表すのは、喜びの感情だ。
「――私も今、それを、貴方に伝えたいと思っていたところです」
「おや!やはり私達は気が合うらしいな」
彼はくすくすと笑う。つられて、綺礼も笑った。
「それでは、よろしく頼むよ。……ええと」
手を差し出しかけて、彼が動きを止める。
彼の沈黙を、綺礼は正確に理解した。この店で出会って三十分程、恐らくはその出会い頭に綺礼が泣いてしまったから逃してしまったタイミング。二人は、互いの名さえ知らぬままに、今後の友情を約束していたのである。
「言峰綺礼です」
「――ことみね、きれいくん?」
彼は一瞬だけ目を見張り、口に慣れないらしいその名を舌に載せた。
「うつくしい、名前だね」
深い声が耳に心地よく、自分の名だというのにひどく尊いもののように聞こえる。初めて、自分の名が美しいという意味を持つ言葉と同じ響きを持っているのだと気付いた。
「私は、遠坂時臣だ」
「遠坂さん」
「何だか恥ずかしいね。時臣でいいよ」
「それでは私のことも、綺礼と」
「――ああ。わかったよ、綺礼くん」
「よろしくお願いします、時臣さん」
改めて差し出された手を、両手で握りしめる。
綺礼の硬い手と比べるととても滑らかで、温かい手のひらだった。
:
:
《《以下R-18部分サンプル(シーンは飛んでいます)》》
「ふ……ぁ、きれい、くん」
長い長いキスをやめると、時臣は湖面のような瞳をとろりととろかせて綺礼を見つめた。濡れた唇を親指で拭ってやると、その親指をぱくりと咥えてくる。口の中で指の腹を舐められると、ぞくぞくと背筋が粟だった。口内から引き抜けば銀糸がかかり、時臣が笑う。もう一度唇にキスを贈って、綺礼は腿の上に座った時臣のシャツのボタンを外していった。
綺礼の部屋、その寝室。数年前に奮発して買った頑丈なセミダブルのベッドは、ぎしぎしと音を立てながらも男二人の体重を受け止めてくれていた。
綺礼と時臣がこういう行為をするのは初めてではない。初めて時臣が綺礼の家に泊まったのが最初で、それからは互いの家へ行く度にそういうことばかりをしている。ただし、ギルガメッシュに言った通り、一度たりとて最後まではできていなかったが。
シャツの前を開け終わった綺礼は今度はベルトへと手を伸ばしながら、同時に時臣の胸の飾りへ舌で触れる。
「ふっ……」
押し殺した声が漏れ、時臣の手が綺礼の後ろ毛を掴む。ゆるく引っ張って抗議を示す時臣だったが、動じる綺礼ではなかった。
「い、嫌だと言っているだろう、そこは、く、くすぐったいし」
「しかしお好きでしょう?私も好きです」
「君が好きでも、っ、ぅあ」
舌の愛撫によってつんと突起が立ち上がれば、今度は逆側へ。吸ったり軽く噛んだりするだけで、簡単に時臣の体は震え始めた。好都合とばかりに綺礼は抜いたベルトを床へ落とす。
「時臣さん」
「そ、そこで喋らないでくれ、息が」
「腰を浮かしてください」
「あ、ああ……」
座った綺礼の足を跨ぐように、のろのろと時臣が膝立ちになる。フロントのホックを外しスラックスを下ろせば、時臣は綺礼の肩にすがりながら片膝ずつを浮かせて、彼がそれを脱がせるのを手伝った。
シャツと靴下と下着だけの格好になった時臣を抱き寄せると、綺礼はそのまま仰向けにベッドの上へ倒れこむ。ぎし、とスプリングが鳴り、安物のマットレスが硬く綺礼の背を受け止める。転がるように体勢を変え、時臣を自らの体の下に敷いた。
「綺礼くん、君も、脱いで」
「はい、時臣さん」
上ずった声に命じられれば従わない道理はない。体を起こし、綺礼はシャツとズボンを脱ぎ捨てる。ちらりと時臣を伺えば自分で下着を脱いでいたので、それにならい綺礼も下着を脱ぎ捨てた。
誘うように伸ばされる腕に従って、もう一度時臣に覆いかぶさる。ぴったりと胸を合わせて互いの頭を抱き寄せて、貪るようなキスを。注いだ唾液は溢れ、時臣の頬や顎を伝って布団へ落ちた。荒くなる息に胸が忙しなく上下し、心臓の音が高鳴る。互いの太ももや腹に当たる性器は、既に高ぶりの片鱗を見せ始めていた。足を絡め擦り合うだけでは、足りない。
「――時臣さん。もっと、貴方に触れたい」
「ん。……じゃあ、どうしたい?」
「今日は……この、体勢で」
再度体勢を入れ替え、さらに時臣の足と頭の位置を逆にさせる。所謂69の姿勢というやつだ。前にも何度かしたことがあるが、時臣が困ったように頬を染めて肩越しに振り返るのが、毎度のことながらとてもかわいらしい。
頭を跨がせたがために目の前に現れた時臣の性器を口に咥える。彼の体で視界が埋まり見えなくなったが、どうやら時臣も綺礼に触れたか咥えたかしたらしい。生温い温度に包まれるのを感じた。
逃げるように浮く腰を押さえつけて深く咥えたり一度口から出して舌で舐めたり好き勝手に弄くれば、素直にどんどんと硬化していく。時臣の方も負けじと舐めまわしているらしく、たまらなく気持ちが良かった。袋の付け根の辺りを指先でくすぐると驚いたのか一際大きく腰が跳ね、抗議のつもりか綺礼の性器に軽く歯が立てられる。その程度の抗議ならばむしろ心地いいほどなので、恐らく時臣の口の中でそれは更に体積を増したのだろう。ふぐ、と不明瞭な呻き声が聞こえた。
そこそこの反応を示すようになったところで、一旦綺礼はそこから口を離した。両足を抱え込む様に手を伸ばし、彼の尻肉に触れる。
「時臣さん」
「……」
「そろそろ、こちらに触れても?」
ぐっと割り開くように力を込める。柔らかい肉の隙間に手を伸ばし、男にとっては口以外で唯一の、他人を受け入れられる可能性がある場所を指先で撫でた。爪先で擽るようにひっかくと、ひくりとそこが動くのが感触でわかる。
「……」
時臣が、綺礼を咥えたままこくりと頷いた。
彼の了承をえた綺礼は、寝転んだままベッドサイドに置いていたローションを手に取る。ぷんと、この部屋には似つかわしくないフローラルな香りが広がるが、これにも慣れたものだ。手のひらにたっぷり出して温めると、もう一度時臣の尻へと手を伸ばす。
「んっ……」
つぷ、と爪先を差し込んだ孔は、力を込めれば一気に指の根元までを飲み込んだ。熱い粘膜が綺礼の指に絡みつく。どくどくとその奥に血潮を流す肉が綺礼の指を包み込む。
その状態で一呼吸置くと、すぐに綺礼は指を動かし始めた。第一関節までをゆっくりと抜き、一気にまた押しこむ。内部を拡張するように指先を曲げる。狭い孔は、段々と綺礼の指に馴染んでいった。
「二本目を入れます。……口が、休んでいますよ」
「む……、んあっ!!」
下半身に意識を集中させてしまい途切れていた舌の動きを再開しようとしたその瞬間、綺礼の太い指が二本目の侵入を果たす。時臣の体に走った衝撃の大きさとは裏腹に、孔の縁は柔軟に伸びてそれを受け入れた。もう一本までならば何度も入れたことがあるが、やはり何度されても苦しい物は苦しい。時臣が苦しげに息を付くのを見て、綺礼は指の動きを止めた。
「……今日は、ここまでにしておきますか」
「嫌だ!」
思わぬ強い声に、綺礼が驚いて目を丸くする。時臣も、自分で思ったよりも大きな声が出てしまったのだろう。どこか狼狽えた調子で、視線を逸らした。
「……き、君を受け入れたいから。続けて、ほしい」
その、何とも甘い誘惑。
抱きしめてキスを出来る体勢でないことが悔しかった。代わりに綺礼は抱き寄せた右足の内腿に、愛情を込めて唇を押し当てる。どこまでも優しく甘い恋人に、自分の同じ思いが伝わるようにと。
――Bの後半、と綺礼がギルガメッシュに言った原因はそこにあった。時臣は元々男に興味があったわけでも変わった性癖があったわけでもないから、初めての行為で、尻の孔に男を受け入れるなどということができるわけはなかったのだ。加えて、綺礼の男性器は一般的なサイズよりも随分大きかったのである。
繋がりたいという欲求が互いになかったわけではない。むしろ、強くあったからこそ繋がれなくても体を重ねていたのである。いつか綺礼自身を受け入れるためと思えば、時臣にとって多少の苦しさも辛いことではなかったし、いつも我慢をさせてしまっていると思えば、綺礼のものを咥えたり舐めたりすることに抵抗だってなかった。
だから時臣はできるだけ力を抜いて後ろの感覚に集中するとともに、口の中の綺礼に精一杯の奉仕をしようとした。張った傘の裏側に舌を滑らせ、とても全ては口内に収めきれない長い竿を両手で擦る。口にすら入らないこの大きさが自分の体内にいつか入るのだと考えると少し恐ろしかったが、これだって綺礼の一部なのだから、時臣を悪いようにはしないだろう。むしろ、時々彼の指先が突付く気持ちいいところを、きっといっぱい弄ってくれるに違いない。
「三本目を、良いですか?」
時臣が頷くのを見て、綺礼は三本目の指を隙間にねじ込んだ。
三本の指によって横長に拡張された孔の縁は赤く伸び、含んだローションに濡れててらてらといやらしくピンク色を光らせる。時臣が荒く呼吸をする度に内部の肉が引きこむような動きを見せ、もはやそこがただの排泄器官ではないのだと知らしめているようだった。
内部で指をばらばらに広げれば甘い声が漏れ、さらなる動きをねだるように腰が揺れる。触れられずとも完全に立ち上がった性器は腰と共に揺れ、先端からとろとろと蜜を滴らせていた。自分の喉元に垂れてきたそれを、綺礼は指先で拭ってべろりと舐める。
「あっ、あ、ふうぅ……っ」
また止まっている舌の動きを咎める気はない。むしろ、その気持ちよさそうな声をずっと聞いていたかった。時臣の声は低く耳に心地よい。それが多分に吐息を含んで掠れるのは、酷く性的だった。綺礼が指先を差し込んでいる孔の立てるくちゃくちゃという音と相まって、綺礼自身も煽られる。
限界だった。
「時臣、さん」
自らの声も掠れている。綺礼の下腹に頬を付けて突っ伏していた時臣がのろのろと顔を上げるのが、彼の両足越しに見えた。
「――――うん。……いいよ」
おいで、と。
とろけた声で誘われ、抗う理由などあるはずもなく。綺礼は時臣にのしかかった。
:
:
: