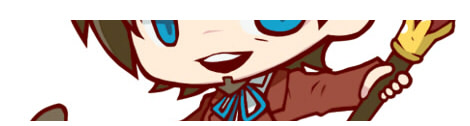
!!! R-18 !!!
フェチズム全開女性物下着ネタ
ご都合主義のイチャラブ時空(ただしラブ分は控えめ)
なおタイトルは「ブラジャー/ショーツ/ベビードール」の略です
フェチズム全開女性物下着ネタ
ご都合主義のイチャラブ時空(ただしラブ分は控えめ)
なおタイトルは「ブラジャー/ショーツ/ベビードール」の略です
BSB
「そうだ、上手だよ綺礼。そのまま集中して……」師の声だけが耳に響く。まるでそれ以外の音がすべて消えてしまったかのように。
遠坂邸、時臣の工房。一年後に来たる戦いで師を支えるため、綺礼は今日も魔術の修行に励んでいた。
上手だと褒められてもまだまだ不安定だ。集中を途切れさせればたちまち崩れてしまうだろう。綺礼は長く息を吐き目を閉じて、両手の間に発生させた魔力に集中した。
「バランスが悪い。偏っているよ、こちらが強すぎる」
――ふいに、熱いものが肩に触れた。
時臣の手。熱さに驚いた体がびくりと跳ねる。――いけない、と思った時には遅かった。
「うあっ……!」
パァンと大きな音、次いで師の声が響いた。慌てて目を開けた綺礼が見たのは、ジャケットの裾を燃やした時臣の姿だった。暗い地下室にオレンジ色の炎が舞い上がる。
「師よ!」
「っ――――、いや、大丈夫だ、綺礼」
椅子から立ち上がった綺礼を時臣は手で制する。素早く脱ぎ捨てられたジャケットがひらりと舞い、そして彼が口の中で何か唱えた瞬間、炎はさらに激しさを増し、ジャケットを包み込んだ。
全て、一瞬のことだった。
完全に燃え尽きたジャケットは灰となって汚れた雪のように舞い落ち、炎の激しさに巻き上げられていたボタンも床に落ちる。音の無くなった地下室に、その音はからからと響いた。
「……」
ふう、と響いたのはどちらの息だったろうか。もしかしたら同時だったかもしれない。
安定を失った力は暴走し、自身や周りに返ってくる。わかってはいるが、常に平静を保つというのはなかなか難しいものだ。余裕を持って優雅たれというこの家の家訓は、そういった戒めの意味を持っているのだろう。
「……気を逸らしたな、綺礼」
ジャケットを失った時臣は大きな机に後ろ手をついて寄りかかり、物憂げな調子で綺礼を見上げた。
「集中力を欠かすことの危うさは、これで理解できたかね?」
呆れたような色が篭ってはいるものの、彼がこんな失敗で弟子を見捨てるような人間ではないことを綺礼は知っている。
知っているからこそ、もう彼をこれ以上失望させる訳にはいかない。
「はい。ですからもう一度。次は必ずうまく――」
ふと違和感を覚え、綺礼は言葉を止めた。
時臣は、ジャケットの下に白いシャツを纏っていたようだ。首元には蝶の形に結んだボウタイがあるのだが、その白いシャツに、何かが透けているのだ。
(……?)
腹のあたりは真っ白のままで、その薄い黒色は胸部辺りを覆っている。何だろう、と綺礼はそれを注視した。ジャケットを着ていれば見えなかった部位である。シャツの下にもう一枚着ているのだろうか。それにしては胸部だけで、腹の辺りに透けていないというのもおかしい。
「――どうした、綺礼?」
弟子の視線がずれていることに気づいたのか、首を傾げて時臣が問う。
「いえ。……、師よ、今日は下に何か着ておられるのですか?」
それは何気ない問いのはずだった。ふとした疑問。世間話の延長のような問いかけ。話題を転換させてしまうかことに対しての叱責はあるかもしれないと発してから思ったが、その程度。
だから時臣の体が大袈裟に跳ね瞳が大きく見開かれるのを、綺礼は状況が掴めないまま眺めているしかなかった。
だが次の瞬間、彼が胸部を抱えるようにして体を翻し逃げようとするのには、反射的に体が動いた。ただ一歩で距離を詰め、肩と腰を後ろから抱えて抱きとめる。
この間、十秒もなかっただろう。綺礼の問いかけから一言すら声が発せられることもなかった。やっと今漏れたのは、いやだ、という頼りない声だった。
綺礼は、不思議な思いを抱きながら腕の中でもがく時臣を見下ろしていた。先程までの余裕はどこへやら、彼は、強く回された腕の拘束を解こうと体を捩っている。揺れる髪の隙間に覗くうなじは朱に染まり、興奮か羞恥か、強い感情を表していた。
「はな、離してくれ……!」
「なぜです。いきなり、一体どうされたのですか」
師がこんなに取り乱すところなど初めて見た。だからその理由が知りたいと、腕を緩めることはない。逃げたがる時臣にとっては残念なことに、綺礼の力は時臣のそれを上回っていたのであった。
「……」
それでも往生際悪くもがく時臣の背が丸まった時、綺礼はその背にそれを見た。
胸元に透けていた黒色が背中側でも、肩甲骨の下あたりを横切るように透けていることを。そして、そのラインから直角にそれぞれの肩に向けて細い紐が伸びていることを。
まさか、と思って背骨の直上、ラインの中央当たりに手を当てる。手触りのいいシャツの下に、ごわりと布の重なった感覚と、布同士を接続する金具の感覚があった。時臣の動きがぎくりと止まる。
「……時臣師。これは、なんですか」
ラインの縁をシャツの上から指先でなぞりながら、固まった背中に問いかける。指でシャツを押し付ければ、一層黒がはっきりと見えた。ごわごわした感覚は、恐らくそれがレースで飾られているからだろう。
綺礼は確信した。まさか、という思いは拭えないが、思い当たるものは一つしかない。
「……」
「時臣師」
時臣は答えない。だが腰のあたりを抱きとめている綺礼の腕には、彼が微かに震えているのが感じられた。
見たこともない師の反応を興味深く思いながら、綺礼は彼の耳に囁きかける。ラインの上にひたりと手を当てて。
「教えていただけないのなら当ててみせましょうか。――師よ、これは女性用の下着ではないのですか?」
びくん、と大きく時臣の体が跳ねた。返事はなかったが、その反応こそが答えそのものと言って良いだろう。
もう一度シャツの布を押し付け、形をなぞりながらそれを観察する。幅広の布はまっすぐに背中を横切り胸の方へと回っている。正面から見たらどんな風になっていたのだろう。
「……て、くれ」
ぽつり、という風に声が溢れる。聞き取れなかった綺礼は、なんですか、と返す。
「も、もう、いいだろう……。離して、くれ……」
抵抗をやめた時臣は自身の腰に回った腕にそっと手を添え、弱々しい声でそう呟いた。うつむいたその表情は見えないが、髪から覗くうなじはやけどでもしたかのように真っ赤だ。ぎゅう、と袖口を掴まれる感覚に、何故か心臓がどくりと脈打つのを感じる。
気付けば、綺礼は答えていた。
「――素敵ですね」
え、と時臣が首をひねってこちらを見る。
「すてき……?」
目が合った。見開かれた蒼の海に綺礼が映っている。羞恥のためか今にも泣きそうなほどに真っ赤に染まった目元、下がった眉、ぽかんと開いた唇。見たこともない彼の表情。
綺礼は、自身の唇からこぼれ落ちた言葉に動揺しながらも頷く。そう。素敵だ――すてきだと、思ったのだ。理由などわからない。
時臣の背に触れていた手を話し、彼の胸元へと回した。慌てたようにその手を払おうとしてくるが、わたわたとした動作は隙だらけである。簡単に抵抗をすり抜け彼の胸元に触れることができた指先で、そのシャツのボタンをいくつか外した。
「や、やめ」
「もっと、見せてください」
首元のタイを残したまま中途半端に寛げられた胸元から手を差し込む。掌で左胸を覆うようにすれば、ごわりとした生地に触れることが出来た。指先で探るに、それは繊細なレースで覆われているらしい。ついでにぎゅっと力を入れて揉んで見ると、布地の下にしっかりとした胸板があることが感じられた。抱きかかえている体がびくりと跳ねる。
手を引きぬき、もう少しボタンを下まで外す。充分に中を覗けるくらいまで開けると、ぐっと合わせ目を開いて肩越しに覗きこんだ。
「黒いブラジャー、ですね」
「……」
白いシャツの内側の胸元は想像通りに、レースがふんだんに使用された下着で覆われていた。色は黒。面積の大きい布地は片胸ずつを広く覆いながら幅広のベルトへとつながっている。これが背中まで回って、さきほど透けていたシルエットとなるのだろう。
カップから伸びるストラップは洒落たレースの意匠が凝らされていて、安物ではないことがわかる。そのカップはあまり立体的になっていないようだ。先ほど触れた感じだとワイヤーも入っていないらしい。膨らまない男の乳房にとっては最適な形状ということなのだろうか。
「……」
時臣の肌の色は濃い。さらに濃いはっきりとした色の下着とは色の相性がよく、いやらしさよりもむしろ清廉な色気を放っているように見えた。
色気。――そう、綺礼は今、男が女性物の下着を身につけているといういっそ滑稽とも言えるようなその姿に、色気を感じている。
「これは、ご自身で買われたのですか?」
すぐ側で喋られるのが嫌だったのか、時臣は押さえつけられた腕で耳を覆おうとした。綺礼の腕に腰と一緒に抱かれているから、それは肘から先がひくりと動いただけに終わったが。
答えない時臣を咎めるように、綺礼は彼の鎖骨のあたりに手を置いた。そこからそっと手のひらを滑らせ、指先をカップの中に潜らせる。
「ひっ」
「答えてください、師よ」
「も、貰ったんだ!」
「貰った? 誰にです」
「昔の知り合いだ……!」
「知り合いにこのような下着を贈られたのですか? それは、どのような知り合いなのです?」
「勘違いしないでくれ、本当にただの知り合いなんだ。ただ彼が、下着のデザインを仕事にしていただけなのだよ。彼は気に入った相手には自身のデザインした下着を贈るという趣味の悪い趣味があって、だから渡されただけだ。私だけが特別扱いされていたわけではない……!」
綺礼に誤解されることがよほど嫌だったのだろう。時臣は言い訳じみた言葉を次々に紡ぎ、髪が乱れるほど強く首を振った。
なるほど、それを手に入れた事情は分かった。が、彼が何故今これを身につけているのかという謎は残ったままだ。趣味の悪い趣味と言い切ったくせに、そのデザイン自体は自分に似合うと思っているのだろうか。だが、ならばもっと胸を張っていいはずだ。気付かれた瞬間に脱兎のごとく逃げ出したのだから、これを後ろめたい姿だと思っているはずなのである。
次はそこを問わねばと考えながら手を引きぬいた綺礼の腕の中で、ふいに時臣が力を抜いた。
「どうしましたか」
「何が、……素敵だって言うんだい……」
その声は小さく、聞き取り損ねた綺礼はもう一度どうしましたかと問う。その瞬間、時臣が振り向いた。視線の鋭さに一瞬たじろぐ。隙を突いて、拘束は振り払われた。
正対した時臣の顔はこれ以上ないほどに真っ赤に染まり、見たことがないほど眉を吊り上げていた。とうとう、羞恥を怒りが上回ったのだろう。
「適当な事を言わないでくれないか。見なさい。こんな姿、滑稽に決まっているだろう…!」
押し殺した声で叫びながら、彼は自身のタイを乱暴に引き抜く。そのまま、開かれかけたボタンの残りを外し、唖然とする綺礼の前でシャツの前を大きく開いてみせたのであった。
白い、開かれたシャツ。バランスよく鍛えられた身体には整った腹筋の陰影が描かれている。くびれた腰が眩しく見えた。だがその胸部はやはり、黒い下着で覆われているのだ。
花をモチーフにしたような灰色のレースで縁取られ、カップやストラップは黒。ふんわりとしているようで、シャツにそのシルエットを響かせないように設計された、計算づくの形。
だがそれは、確かに不自然な姿だった。いくら整った容姿だと云えど、遠坂時臣は男。膨らむはずのない乳房を支えるための下着など付ける必要はない。なのに彼はそれを誰にも言わずにシャツの下に着込んでいたのだ。趣味の悪い趣味だと罵り、自身の姿を滑稽だと形容しながら。
ジャケットさえ脱がれなければ、きっと今も気付かずにいただろう。そのまま今日の一日が終わり、明日も明後日も、きっと永遠にこんな事実など知らないままだった。不思議な運命を感じながら綺礼は、自らシャツの前を開いた時臣の姿を眺めた。
綺礼から反らされた瞳は険しく、シャツを掴む指先は力が入りすぎて震えている。怒りと羞恥の混ざった表情は複雑で、緊張でもしているのか瞬きの回数が多い。せわしない呼吸に、黒いブラジャーに覆われた胸が上下していた。その姿はやはり不自然で、――だが綺礼には、やはり素敵だとしか思えなかった。
彼の知り合いだという下着デザイナーが、これを時臣に贈った気持ちがわかる。きっとその男は、これを付けた時臣の姿を見たがったことだろう。見せたのだろうか。会ったこともないそのデザイナーに、何故だか苛立ちが募る。いや、何故なのかなどわかりきったことだ。時臣に女性物のデザインの下着を贈るという行為をすることができたその男に、綺礼は、つまり、嫉妬心を抱いているのだ。
何も言わない綺礼に業を煮やしたのか、時臣がちらりと目線だけを上げる。
「……若くもなく女性的でもない男が、こんな下着をつけているのだよ。……軽蔑されて当然ではないかね」
軽蔑して欲しいのですか、と言おうとしてやめる。綺礼が伝えたいのはそんなことではないのだから。
それに時臣の怒りも少し薄らいでいるようなので、ここで敢えて蒸し返させるのは得策ではないだろう。綺礼が黙っていることで、怒りは不安へと転換したらしい。先ほどまでつり上がっていた眉はその前までのように情けなく下がって、綺礼の答えを待っているようだった。
「――ですが、私は素敵だと思いました」
「何が素敵なものか……!」
「落ち着いてください、師よ」
また怒りを浮かべ始めた時臣を、綺礼は言葉で制する。
「確かに一般的に見れば貴方のその趣味は軽蔑されるものなのかもしれません。ですが貴方はそれを好んでいて、私も嫌悪感を抱かないという、それだけの話ではないですか」
「わ、私はこんなもの、好んでなど……」
「ペットボトルの紅茶のようなものですよ。貴方はあれを不味いと嫌悪しますが、あれを好む者もいる」
否定する言葉は敢えて無視して言葉を続けた。唐突な喩え話を時臣が理解しようとしている間に、また話を戻す。
「ここにいる二人が偶然、男性が女性下着を着ける行為に対して嫌悪感を抱かなかったという、ただそれだけの話ではないでしょうか」
「……」
困惑したように、時臣は綺礼の目を見ている。軽蔑されると、嫌悪されると思っていたのだろう。当然だ、『一般的に考えれば』受け入れ難い光景のはずだろうから。だが時臣も綺礼も、その一般から外れる感性を持っていたという、それだけの話。
「……君は、こんな私を受け入れてくれるというのかい……?」
「素敵だと思うと言ったでしょう」
自虐的な言葉もばっさりと切り捨てる。
それでやっと時臣も、綺礼が嘘をついたり酔狂で言ったりしているのではないということを理解したらしかった。ほう、と長い大きな息をつく。胸元のシャツを掻き抱き、ぽつりと漏らした。
「――誰にも、知られずにいるつもりだったんだ」
諦めたような、だがどこか安心したような。そんな声音だった。
そんな時臣の隣に寄り添うように立ち、綺礼は彼の手を胸元からどけさせる。掻き抱かれていたシャツがまた左右に割れ、彼の素肌と黒い下着が淡い明るさの下に晒された。
「普段から身につけられていたのですか」
疲れた様子で顔をあげた時臣は、頬を赤らめたまま苦笑して頷く。
「たまに、だけれどね。君や誰かと過ごす時間の多い日は避けていたよ。……今日は、偶然だ」
「私以外に知っている人はいるのですか?」
「いや、君にだって本当は知られたくなどなかったのだよ。……葵や凛にだって、もちろん同じだ」
そう言いながら口止めをする様子もない。言いふらされても仕方がないと言うよりは、綺礼を信頼しているからだろうが。
「何故、それを身につけようと思ったのです」
その問いに、少し悩んだ様子を見せてから口を開いた。
「――初めはなんとなく、だな。付き合いでこれを貰って、それからずっと仕舞いこんだまま忘れていた。それが、この間ふと出てきたのだよ。もうあの男にしつこく付けろと言われることもないし、一度くらいは付けてやってもいいかと思ったんだ。きっと、どうかしていたのだね」
胸元に手をやりながら目を伏せ、時臣は続きを語る。
「だが、それが何故かしっくり来てしまった。何と言えば良いのだろう、私が私でなくなるような。不思議な解放感を覚えたのだよ。……それから、たまにこうして、これを着る癖がついてしまったんだ」
神父として様々な人間と関わってきた綺礼は、昔一人の男の懺悔を聞いたことを思い出した。それは、妻のスカートを彼女 に黙って勝手に着たことがあるというようなものだったと記憶している。その男も時臣と同じように、自身が自身から解放されるような気分だったと語っていた。綺礼は、自身が女性物の服を身に付けることで何か変わるとは思えないが、そういう人間は一定数いるということなのだろうか。
綺礼がそんなことを考えていると、不意に顔を覗き込まれた。青い瞳に自身が丸く映り込んでいるのさえ見えるほど、近い距離。
「素敵だと言ってくれて、軽蔑しないと頷いてくれて、嬉しかったよ綺礼。――だが、もうやめようと思う」
時臣は微笑んでいた。どこかすっきりしたような、だがこちらが不安になるような、儚げな雰囲気で。強く満ちているのは諦念だ。一瞬その雰囲気に飲まれそうになった綺礼は、気付けば時臣の体を自身に向けさせ、その両腕を強く掴んでいた。
「何故ですか」
目を合わせようとしても反らされる。作った笑みを口元に浮かばせながら、時臣は唇を開いた。
「――思い直す良い機会になったよ。たまたま知られたのが君で、君が私を受け入れてくれるような人間だったから良いが、もし、これが数カ月後に控えた戦いで敵対する相手だったらどうする? わざわざ弱みを残したまま戦いに挑むなど、馬鹿のすることだ」
「そんなこと。暴かれなければ良いだけの話でしょう」
時臣の言うことはもっともだ。これからとこれまでの全ての人生を掛けねばならない戦いに、一つでも憂いを残したまま挑むことなどできはしまい。たとえそれが、平静を装ってさえいれば隠し通せる秘密だとしても。
「だが今回のように、事故が起きない保証はないだろう」
実際綺礼はこの重大な秘密を知り、平静を装うことも忘れて逃げ出したりむき出しの感情を覗かせたりする時臣を見てしまった。この先の戦いの重大な局面でそれと同じことが起きないとは限らない。だが、綺礼はそれでも引き下がれなかった。
「それを、貴方の心配を補佐するのが私の役目でしょうに。私をも信頼出来ないというのですか」
「そ――、そんなことは、ないが……」
綺礼の語りはいつになく熱がこもっていて、時臣はまばたきを繰り返すくらいしか反応を返すことが出来なかった。だが、一番驚いているのは綺礼自身だっただろう。
(――この熱意を見ろ。もう否定出来やしない。お前はもっと師のこういう姿を見たいと思っているのだ)
アンバランスで不安定な愛おしさ。もっと時臣の姿を見ていたい。その気持ちが心の中に浮かんでいることに、綺礼は気付いていた。普段余裕ぶった彼の慌てる姿や、紳士然としたその衣服の下に奇妙な下着を着けているような、誰も知らない時臣の姿を。そして出来るならば、誰かに贈られた下着ではなく、――
「――師よ。つかぬことをお伺いしますが」
「何だい」
「これ以外にこういった下着はお持ちなのですか?」
不意に転換した話題についていけず、時臣はまたぱちぱちとまばたきをする。
「いや……、これ一枚だよ。彼は他にも押し付けようとしてきたが、断ってしまった」
「一枚だけでは飽きてしまうのでは?」
「たまにしか着けないと言っただろう。飽きるほど毎日着けているわけはないさ」
「ですが、たまには気分を変えてもいいのでは。――そうですね、私が何か見繕ってきましょうか」
「は?」
ぽかん、と時臣が口を開けた。その抜けた表情も、これまで二年以上一緒にいて見たことがないもの。今日は本当に様々な表情を見せてくれる。綺礼は、そんな反応を楽しいと感じている自分に気付いていた。
「ええ、そうしましょう。表面上の付き合いしかない男より貴方のことを理解している私の方が、貴方の好むものをきっと探し出せるでしょうから」
「や、やめてくれ、綺礼……」
「要らないのですか? お好きなのでしょう」
「好きとは……、一言も言っていないじゃないか」
もごもごと言い募る時臣の顔はまた赤く染まっている。彼の性格からして、本気で綺礼を止めたいのであればもっと強く言うはずだ。だがこうして言い辛そうにしているということは、心からそう思っているわけではないということかもしれない。つまり時臣は、この黒い下着以外の下着を――微かにかもしれないが――着てみたいと思う心があるのだろう。
「それでは、今度時間のあるときに探して参ります。期待していてくださいね」
「期待なんか……」
言いながら視線を逸らす姿は拗ねているようにしか見えない。しかもその前に一瞬、嬉しそうに微笑みそうになっていたのまでしっかり見てしまったのだから、尚更。
むくりと沸きだしたいたずら心に突き動かされるままに横から彼を抱きしめ下着の上から胸に触れると、裏返ったような悲鳴が上がった。悲鳴を上げたきり抵抗がないのをいいことに、綺礼はレースの感触とその下にある肉の弾力をてのひら全体で楽しむ。
時臣が抵抗しないのは、不思議なことに、驚きに体を硬直させているからではないようだった。
綺礼の腕の中に収まって俯いているその項は、相変わらず赤かった。
:
:
最初はメンズブラネタの予定だったのですが、
気付いたら普通の女性用下着ネタに。
両思い感は薄いけどいちゃらぶになったので
結構満足しております。
在庫等の最新情報はpixivを御覧ください。
[pixivのサンプルページヘ]
気付いたら普通の女性用下着ネタに。
両思い感は薄いけどいちゃらぶになったので
結構満足しております。
在庫等の最新情報はpixivを御覧ください。
[pixivのサンプルページヘ]