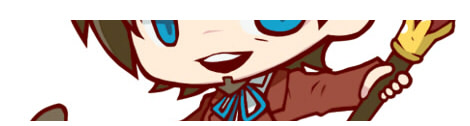
ギル時っぽい描写がありますが、英雄王はちょっかい出してるだけ
綺礼×時臣です
「フハハハハハハ!!!!!!!!」綺礼×時臣です
突然屋敷中に響き渡る哄笑。
この先の戦い方を打ち合わせていた時臣と綺礼は、同時に互いの方を見た。
「この声は……」
「──はい」
「…………拙いな」
「………………拙い、ですね」
綺礼の黒い目を見返す時臣は、かすかに震えていた。当然だろう、と綺礼は思う。その笑い声が響いた後はろくなことにならないと、二人とも知っているのだ。
「おい、時臣!綺礼!出てこい!!!」
「ッ!」
哄笑に続いて、威圧的な声が響く。
命令形の言葉に、次の行動を決めかねて時臣は綺礼を伺い見た。『不測の事態』に怯えている師に、綺礼は頷いてみせる。
「──待たせれば、その分機嫌も悪くなるでしょう」
「ああ……。行くしか無いだろう、ね……」
時臣は濃い眉をひそませ、力なく苦笑した。
いつものこと、と言ってしまえばいつものことである。天上天下唯我独尊を騙るあの英雄王には、一体どれだけ胃を痛めつけられなければいけないの だろうか──。
今日も恐らく何かを思いついた英雄王に振り回されることを予想し、時臣は大きく息を吐いた。
どうせいつも通りの不遜な笑顔で迎えられ、何事か面倒な命令をくだされるのだ。
お菓子がないなら/お菓子があっても
しかし部屋を出た時臣を待ち受けていたのは、全く予想外な景色だった。廊下の真ん中に仁王立ちする金色の彼は鎧姿で、その後ろには輝く『王の財宝(ゲートオブバビロン)』が展開されていたのだ。
「ハッピーハロウィン!さあ受け取れ雑種よ!」
響く王の声と共に、小さな礫がゲートオブバビロンから放たれる。ぱつぱつと何かが当たる衝撃に、時臣は小さく悲鳴を上げて目を閉じ、防御も忘れ 思わず一歩下がった。
トン。その背は、頼り甲斐のある何かにぶつかる。
「…きれい」
怯える時臣の背を支えたのは、綺礼の胸筋だった。
助かった、と安堵の息を付き自分を見上げる師に軽く頷いた後、綺礼は時臣の肩を抱いて廊下の真ん中に堂々と立つギルガメッシュを軽く睨みつける。
「………アーチャー、何をやっている」
射殺せそうな鋭い視線を受け、しかしギルガメッシュは鼻で笑い飛ばした。
「なんだ、綺礼?お前は今日が何の日だか知らんのか?」
「何の日…だと?」
「…あ」
ふいに時臣が腰をかがめ、足元の何かに手を伸ばした。先ほど時臣に襲いかかった小さな礫の一つ。それは、両端を捻ったキャンディだった。
「王、これは………」
「ようやく気づいたか。最初に言ったであろう?『ハッピーハロウィン』と」
にやにやとギルガメッシュが笑う。綺礼は誰にも聞こえないほど小さな音で舌打ちをした。
「王は、ハロウィンもご存知だったのですね」
「ふん。そんなもの、聖杯から知識を受けておるわ」
どこかずれた時臣の問いに、ギルガメッシュは胸を張って答えた。
「王からの慈悲である。光栄に思え」
「ありがとうございます、王よ」
時臣はにっこりと笑う。嬉しそうに。そっと膝をついて、足元に散らばったキャンディに指を伸ばした。
「──さて、時臣」
いつの間にやら時臣の目の前まで移動してきたギルガメッシュが、彼を見下ろす。
綺礼がはっとした時にはもう遅かった。
「我はその菓子を貴様に与えてやったが、貴様は我に何を寄越す?」
鎧姿を解いたギルガメッシュは、少しかがんで時臣の顎を指で持ち上げ、そう聞いた。きょとんとした碧眼がギルガメッシュを映す。
「何を…とは?」
「ハロウィンにはこういうものなのだろう──『トリック・オア・トリート』?」
「あぁ、それは娘たちから聞いたことがあります。確か意味は、お菓子をくれなきゃいたずらするぞ、と、……」
あ、と時臣が気づいて声を上げた。
「つ、つまり王は、お菓子を所望で」
「そういうことだ、時臣。菓子を寄越さねばイタズラ確定だが、どうする?」
そこまで言われて、時臣はやっと今の状況が何を示すのかに気づいたようだった。
「お、王!申し訳ございません、今日が、その、ハロウィンだと、忘れていたもので」
とたんにあたふたとし始める時臣。すでに少々涙目になっている。放っておけばふえええとでも言い出しそうな雰囲気だ。
ギルガメッシュはそんな時臣をにやにやと見下ろし、顎を支えていた指を離して彼の頭をぽんぽんと撫でてやる。
平素の、優雅を信条として完璧に行動する姿はつまらないが、こうして一度崩されて慌てふためく姿は、ギルガメッシュの好むところであるのだ。
「なに、別に菓子の用意がなくとも良い」
「お、王………」
「つまり、イタズラを望むということであろう、時臣ィ?」
「は、え………あ、王ッ!?」
ひょい、と片手で抱え上げられ、時臣が慌てた声を上げる。
「お戯れはお止しください!お菓子がないならパンをって、ひぃ!」
抱え上げたのとは逆の手でするり尻を撫でられ、時臣は悲鳴を上げた。
そのまま向かおうとしている先は寝室である。連れ込まれてしまえば逃げることはできまい。
「き、綺礼ー!きれいー!助けてー!!」
「ええい往生際の悪い。お菓子がないなら仕方あるまい!」
ばたばたと暴れる時臣の両足を抑えこんで、肩に担ぎ直す。そうすると今度は両手でぽかぽかと背中を殴ってくるのだが、これがいっそ面白いほどに 弱い。
全く抵抗にならない抵抗を受けながら、ギルガメッシュが鼻歌交じりに踵を返した時だった。
「時臣師!」
鋭い声とともに飛んでくる何か。呼ばれるがままに、時臣はそれを両手で受け取った。なんだろう、と見てみると、それは。
「あ…、チョコレート?」
製菓用の、砕いて袋詰めにされたチョコレートだった。
師のピンチを見て取った弟子は師を助けるべく、キッチンへと走ってそれを取ってきたのだ。
「──師よ、『お菓子』です」
その、言葉に。
合点のいった時臣は、思いきり身をよじって自分を拘束する腕から何とか抜け出す。
「あ、オイコラ!」
「──王、所望の菓子を用意致しました」
そして、さっきまでばたばたしていたことも忘れたかのように優雅に一礼し、そのチョコレートを恭しく差し出すのであった。
ギルガメッシュはその姿と、背後に控えて無表情を貫いているその弟子を睨みつけるが、先に仕掛けたのは自分である。逃げ道を用意してしまった時点で、負けが決まっていたのだ。
腰を折り顔を伏せる時臣は完全に常を取り戻しており、いつも通りのつまらない男に戻っていた。
音を立てて舌打ちをする。
「…次はこうは行かぬぞ」
無造作に袋ごとチョコレートを受け取り、ギルガメッシュは背を向けた。
その姿が金色の光を振りまきながら霊体化するのを見届け、
「………はぁ…」
時臣は大きく息をついた。
「時臣師」
「あぁ、綺礼。君に助けられたね。ありがとう」
綺礼が呼びかけると振り向いて微笑む。その顔は明らかに安堵の色に染まっており、綺礼への心からの感謝が覗えた。
そんな顔をみていると、イタズラ心が芽生えてしまうのが綺礼である。
「師よ」
「なんだい、綺礼」
「トリック・オア・トリート、と。私も言わせてもらいたく思うのですが」
慌てふためくとばかり思っていた師の反応は、しかし綺礼の予想とは随分と異なった。
時臣は、悠然と微笑んだのだ。
手を出しなさいと言われ、反射のように右手を伸ばす。天井に向けて開かれた手のひらの上に、時臣は何かをころころと乗せる。
「先ほど王から賜ったばかりのものだけどね」
それは、色とりどりのキャンディだった。
ギルガメッシュがゲートオブバビロンから放った、あれだ。
「………」
「色々な味があるようだよ。綺礼はどれが好きかな」
綺礼の大きな手のひらの上へ載せられたそれらを、時臣が覗き込む。
「……師は、どれに」
「私かい?」
「あなたがギルガメッシュに貰ったものでしょう。あなたが先に選ぶのが道理では」
「…そうだな。では、この赤いのにしようか」
綺礼の手のひらから、安っぽい赤色の包みをつまみ上げる。慣れない手つきで、イチゴ味と書かれたその包みを開くのを、綺礼は見ていた。
赤というよりピンク色に近い球形のそれをつまみ上げて、宝石みたいだねと時臣は微笑んだ。指先でそれを口の中に落とすのを、見た。
「甘い。美味しいね。キャンディなんて久しぶりに食べたよ」
コロコロと口の中で転がしているのだろう、頬がその形のままに膨らむのを、見て。
とうとうたまらなくなって、綺礼の口は、考えるより先に動いていた。
「──時臣師」
「うん?何だい?」
「私も、その赤いのが欲しい、です」
言うなり、くちづける。
驚いて閉じた唇を舌でこじ開け、そのまま中へ押し込む。キャンディを持ったままの右手がもどかしい。空いた左手で柔らかい茶色の頭を抱き寄せる。甘ったるい味、キャンディの味だ。いや、師自身の味かもしれない。
夢中で味わっていると、ふいに時臣の舌がするりと動いた。驚いて眼を開けると、ひどく近い位置に濃い茶色の睫毛が見えて、その下から深い色の瞳が綺礼を見つめていた。
「………は」
離れた唇の間から、時臣が小さく息を吐く。唾液の糸が切れる前に、目を合わせたまま彼は、微笑んだ。
「綺礼もこの味が好きだったんだね。私が食べてしまってすまない」
そして今度は彼の側からくちづけてくる。
背の高い綺礼に合わせるようにつま先を伸ばして、下から。輪郭に這わされる指。もう一度、今度は濡れた唇が合わさって、自然口を開く。舌と舌が絡まって、脳髄にまで響く水音。甘い、甘さ。歯や骨まで溶かすような人工の甘さと、口づけの甘さ。
舌と舌の間で踊るキャンディ。このまま全て一つになってしまえばいいのにと深く口を合わせれば抗議するように舌が舌で押されて、その触れ合う感覚にすら肌が粟立つ。
息継ぎのために離れるのも惜しいとばかりに離れたがるのを追って唇ごと覆って、まるで獲物を窒息させようとする獣のようだ。後頭部を強く引き寄せて、上から押さえつけるようにして。吐息すら逃さぬように。
そうしてどれほどが過ぎただろうか。ふいに、歯ではない固いものが綺礼の口の中に送り込まれた。
「──そこまでだよ、綺礼」
それは、いわずもがなキャンディだ。
二人の口内で暖められ、若干ぬくもりをもったそれは、舌で確かめれば最初よりも随分と小さくなっている。
「あとは、一人で味わうといい」
離れた時臣は、綺礼に向かって微笑む。その笑顔は綺礼に魔術を教えるときの表情に似ていたが唇だけは艶めかしく赤く濡れていて、綺礼は少しだけ動揺した。
「ときおみ、し」
「ちゃんと甘いお菓子を上げただろう?──その口に」
「っ、」
手を伸ばしかけた綺礼の唇に、触れる人差し指。それだけで、言葉は封じられる。
「これ以上は『イタズラ』だと見なすよ。それはルール違反だ」
ルールも何も、と綺礼は思う。だが、そういった基準を作りたがるのが、彼の魔術師たる所以なのかもしれない。
無理やりその手を掴んでもう一度唇を奪うことも、そのまま引き倒すことも、先程の誰かのように抱え上げて連れ去ることも、綺礼ならばできる。
だが、彼がルールだというのなら。
「…わかりました、時臣師」
引いて、承知を。
「いい子だね、綺礼」
褒められて、微笑む彼の顔を見ることが出来るのだから、それを選択するのも悪くない。
温かい手が伸ばされて、綺礼の輪郭を一度だけ撫でた。
「…さて、そろそろ休もうか。だいぶ疲れてしまったよ」
「ああ、それでしたらベッドの用意を」
「いや、いいよ。別に布団が曲がっていたって眠れる」
それではおやすみ、と師は背を向けた。
見送る綺礼はその背に向けてもう一度礼をする。しばらくして上げた視線の向こうには、もう彼はいない。
口の中のキャンディは相変わらず甘ったるく、未だ彼の暖かさを残しているようで。
大事に最後まで、その形がなくなるまで、舐めて溶かしてしまいたいと思った。
ちょっかい出す英雄王といちゃらぶ師弟。
こう、繰り広げられるマボワ劇場の前で
すごい白い目してる感じの英雄王とかすごい苦労人っぽくて好きです。
こう、繰り広げられるマボワ劇場の前で
すごい白い目してる感じの英雄王とかすごい苦労人っぽくて好きです。