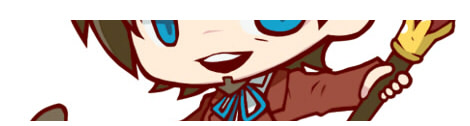
時臣と綺礼が聖剣伝説LOMの『珠魅』という設定のパラレル
色々と設定がふんわりしているので、適当にお読み下さい
色々と設定がふんわりしているので、適当にお読み下さい
ほうせきのひとたち
最後の一人が部屋から出てきたのを見て、綺礼はやっとその部屋に入ることができた。外側にしか鍵のない扉の、頑丈なノブを押し開ける。中に、ぼんやりと虚空を見上げている男の姿が見えた。
「時臣師」
「…ああ、綺礼」
胸に燦然と輝く紅い石。ルビーの核を持つ彼は、綺礼のパートナーである時臣だった。
ぼんやりとした瞳が綺礼を捉えて微笑む。その目尻を染める赤、それから頬に残る水の跡に、綺礼はこっそりと歯噛みした。
彼は、また泣いたのだ。
珠魅とは、心臓の代わりに『核』と呼ばれる石を持つ種族だ。心臓の代わりなので、当然その石が傷付けば死んでしまう。それを癒すことが出来るのが、唯一、同胞たちが流す涙から生成される『涙石』と呼ばれるものだった。
ただし、彼ら──珠魅たちから、昨今涙は失われつつある。
美しい核を持つばかりに他者から攻められ蹂躙されるばかりだった彼らが隠れ住み初めて百数年。平和な暮らしに慣れきった彼らは、いつしか戦いも、それを癒すすべも忘れてしまったのだ。
いや、これは神からの鉄槌なのだと言うものもいる。腕が飛ぼうと胸を突かれようと、肉体すら失おうとも、核すら無事ならば不死であるが故に、無謀こそを栄誉と捉える好戦的な種族への。
何にせよ、だがまだ、完全に失われたわけではない。蛍姫という珠魅を中心に、涙の枯れていない者たちは煌めきの都市深部に、ひっそりと幽閉されていたのだった。
このまま運命に従って静かに滅びを待つのか、それとも、打開策があるのか。同族だというのに争い合う珠魅たちのために、泣くために。
だが、涙石は単なる涙ではない。流す者の生命力を分け与える行為なのだ。
涙を流せば流すだけ涙石は生成され、誰かの核が癒える。だが、涙を流せば流すだけ彼らの命は流れだし、彼らの核は傷つく。
涙を流し人を癒す『姫』、それを守り戦う『騎士』。その役割分担ができている時代ならばよかった。だが、涙の失われつつある今では。涙を失っていない数少ない姫にばかり負担がかかり、既に幾人かは、涙を流しすぎて壊れてしまったという噂も聞く。
綺礼は、この制度を厭う一人だった。
未だ涙を流すことができ、幽閉されている姫の中に、綺礼のパートナーである時臣もいた。
綺礼は時臣を愛していた。美しい核の紅い色も、それと正反対の青い瞳も。落ち着いた声も、深い知識も、穏やかな人柄も、柔らかい髪も、暖かい体も、全て愛していた。
彼の隣に立ちたいという思いが、単なる薄汚れた黒曜石であった綺礼を珠魅にしたのだと思う。
時臣と、騎士と姫の関係であることは、とても幸福だった。
彼のために振るう拳や刃の一振り一振りが誇りだったし、その背に時臣をかばって負った傷を癒される時の喜びは尋常なものではない。
この生命のすべてを彼のために使いたいと思ったし、彼の命の全てを自分に与えて欲しいと思っていた。出来る限り長く。出来るならば永遠に。
だからこそ、この現状は。
誰のためともわからぬままに、都市の奥底に押し込められ、日がな涙を流し命を削り続けることを強要される姫たちの姿に。それを、種族のためだと諦めている時臣に。
綺礼は、憤っていた。
「───ああ綺礼。怖い顔はいけないよ」
物思いに沈んでいた綺礼の頬に、そっと指先が伸ばされる。
日に当たらぬゆえに白く細い指先。時臣の指だ。それは綺礼の輪郭をそっと撫でて、離れていった。
綺礼に触れるために乗り出した身を戻し、元の通り、床に敷かれた柔らかそうなクッションの中に、彼は埋もれるようにして座リ直した。
暗めの照明の中でも、彼の紅い核は存在を主張するように輝く。
その核には、細かなヒビが縦横無尽に走っているのだ。
綺礼のためではなく。時臣自身のためでもなく。争い続ける、どこかの屑石のために。
「隣においで」
自分の隣を指先で指し示し、時臣は穏やかな声で言う。綺礼は素直に従って、柔らかいクッションを踏み越えて彼の隣に腰掛けた。その肩に、時臣がもたれて来る。
無理をしていたのかもしれないし、単純に甘えたがっているだけかもしれない。綺礼の視界からでは時臣の旋毛くらいしか見えず、彼がどんな顔をしているのか伺うことはできなかった。
肩に柔らかい髪が擦り付けられる。その頭を抱き寄せると、くすりと笑う気配があった。目元に指を伸ばし、しずくを拭う。目を閉じた気配があった。
そのまま、二人の間には静寂が満ちた。だがそれは決して居心地の悪いものではない。肩にかかる重さと暖かさを噛み締めながら、綺礼は時臣の髪を撫で続ける。時臣はそうされながら、微笑んでじっとしていた。
どれくらい経っただろうか。ふいにぽつりと時臣が口を開いた。
「そうだ、綺礼。雁夜のことは話したかな」
「雁夜……ですか」
「うん」
それは時臣の友人の一人であり、彼と同じ幽閉されていた姫の一人でもあった。『あった』というのは、過去形の言葉である。
「核を抜き取られたと聞きましたが」
煌めきの都市から気晴らしにと外に出た時、珠魅専門の盗賊に襲われたのだという。丁度別件で出ており彼を護ることのできなかった彼の騎士が、酷く怒り狂っていたのを覚えている。
「彼の騎士が彼の核を取り戻してきたんだ。傷だらけになって、一人で」
「それは……」
「彼のオパールはね、壊されてはいなかったよ。涙石さえあれば、回復することが出来るだろう」
本当に良かった。そう、時臣は心の底から安堵したような声を出した。
───涙石さえあれば。
核だけとなったその珠魅も、まだ生きているのだ。肉体を取り戻し、再び人のように振る舞うことができるのだ。涙石さえあれば。誰かのいのちのかけらを、与えられれば。
単純な怪我とは違い、肉体を失った珠魅を回復させるためには相当な涙石が必要なはずだ。涙を流すものたちの命も大きく削られる。
それを与えるのは姫たちであり、その中には時臣も含まれる。
雁夜は回復するよ、良かったね、と。なのに彼は微笑むのだ。
綺礼は、時臣をきつく抱きしめた。かつん、とぶつかり合う核の音。
「ッ、苦しいよ、綺礼」
「───もしも」
喉の奥から絞り出す声は、掠れている。だがその小さな声に、時臣が耳を傾けてくれているのを感じた。
「もしも私が、貴方を攫って逃げたいと言ったら」
「駄目だ」
綺礼の言葉は遮られる。
唇に触れる、冷たいゆびさき。
そっと、体が離される。体と体の間に、冷たい空気が流れ込んだ。
薄暗い照明に浮かぶ、彼の紅い石。暗い色の青い瞳。真っ直ぐにそれは、綺礼の漆黒の石と漆黒の瞳を映した。
「私は、まだここに必要とされているから」
傷を負った珠魅たちに。核だけとなった雁夜や彼の騎士に。
彼らを癒すだけの存在として。涙をながすだけの存在として。ただの、道具として。
「…口に出してはいけないんだよ、その、望みは」
そんな存在として必要だというのなら、私のほうがどれだけ貴方を必要としているか!綺礼は心の中で叫ぶ。
あなたのいない世界など考えられない。あなたと共に歩めない世界ならば滅びてしまえばいい。そんな世界から、あなたを連れ出したい。あなたをあなたとあなたを愛する私だけのために生きて行ける世界に連れ去ってしまいたい。───だが、そんな望みすら、彼は聞き届けてくれないのだ。
「さあ、綺礼」
時臣の手が、未だ自分を抱きしめていた綺礼の腕をそっと外す。外された綺礼の手を、だが包んだまま時臣は微かに微笑んだ。
「もう遅いから、そろそろ帰りなさい」
「ですが」
「私も、今日は少し疲れてしまったから。休まないと」
ね、と言われてしまえば、首をふることはできなくなる。何よりも大事なのは時臣の体だ。
「…時臣師」
せめて最後に、と顔を近づければ、合点がいったのか時臣は困ったように微笑み、自身からも顔を近づけて目を閉じる。
触れ合う唇。
そっと触れ合うだけで、貪るような激しさはない。そのまま数秒の、啄むような接触。
「………明日も、また来ます」
「ああ、待っているよ」
柔らかそうなクッションの中にぽつりと座ったまま、時臣が小さく手を降った。
おやすみ、とその唇が動き、綺礼は礼をして部屋から辞去した。
重々しい音を立てて閉じたその扉は、外側からしか鍵のかからない構造になっている。
──駄目だ、と。
触れられた指先の冷たさが未だ唇に残っている。口づけですら消してはくれなかった、その冷たさ。
時臣がいくらその言葉を聞き届けなかろうと、近いうちに自分が辛抱できなくなるだろうことを、綺礼は感じていた。
いつか、いつの日にか。
滅び行く都市に背を向けて、彼を抱き上げどこまでも走る、妄想を。
綺礼は、抱いていた。
胸に大きなルビーが輝いている時臣さんとか素敵じゃないですか…
いつか外へ攫った話とかも書いてみたいです
時臣師をガトとかに連れて行きたい
いつか外へ攫った話とかも書いてみたいです
時臣師をガトとかに連れて行きたい