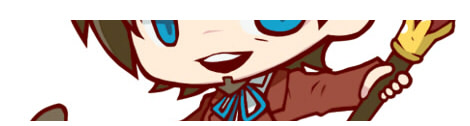
「いえ。───もとより、ケーキの予約などしておりませんので」
この日、遠坂邸ではパーティが企画されていた。
パーティ、とはいえささやかなものである。出席者は遠坂家の面々とそれから時臣の弟子である綺礼だけで、後は話を聞きつけたギルガメッシュが我も参加するぞ面白そうだから、と言った程度。
ただ、どうせやるのならば準備も念入りにと、時臣と綺礼、それから巻き込まれたギルガメッシュはパーティに向けて準備を進めていた。
いや、進めていたはず、だった。
「え?」
綺礼の言葉に、パーティのための部屋の飾りつけを進めていた時臣が振り返った。両手に壁に飾る紙輪の飾りを持ったままぽかんとした表情の彼に、綺礼は愉悦!と叫びたくなるのを堪える。
冒頭のそれは、「そう言えばケーキは何時に取りに行けばいいんだったかな。予約の時間に間に合うといいんだが」という時臣の発言に対する回答である。唐突に放たれたその一撃は、どうやら時臣に致命的なダメージを与えたらしい。
「い、今何て、綺礼?」
「ですから、ケーキの予約などしておりませんと言ったのです」
ぱた、と時臣の手から紙輪が落ちた。
「え?…いや、だって私お願いしたよね?ヴィタメールのショコラ・クロンヌ予約しといてって言ったよね?」
「ああ、そう仰っていたんですか。すみません、よく聞こえなくてヴィトンのショルダーバック買って来ました」
「えええ!?どうやったらそう聞き間違えられるんだい!?」
ちら、と肩からかけた鞄を示してみせると、時臣がすごい勢いで駆け寄ってきた。
こんな師見たこと無い!と心中で愉悦を覚えている綺礼をよそに、時臣は綺礼の胸ぐらを掴んでぐいぐいと揺さぶってきた。ただ、そう力が強くない上に相手はガチムチ神父。服の首元が多少伸びる程度で、綺礼は微動だにしない。
「ど、どうするんだ!クリスマスは、もう今日だぞ!」
「いやあすみません。うっかりうっかり」
「ケーキがなかったら葵や凛が悲しむじゃないか!」
ぐ、と揺さぶられるのが止まる。綺礼を見上げる碧い目の濃いまつげに、水分が溜まっていた。すみませんを繰り返しながら、その目尻に小さくキスを贈る。
「ん、」
無味の水分を舐めとると、綺礼は自分の首元を未だ握りしめている時臣の手をそっと外させた。片手でその手を握りしめながら顔を覗き込み、もう片方の手で肩にかけていた鞄を器用に外して時臣の方へ差し出す。
「すみませんでした。代わりに、この鞄は差し上げます」
「…そんなことで、ほだされる私だと思うなよ」
むすっとして涙を浮かべた表情のまま、それでも時臣はそれを受け取って、ありがとう、と言った。
「おい時臣!ツリーの飾り付けが足りな───」
がちゃ!と大きな音を立ててドアが開き、ギルガメッシュが現れたのはその直後。
綺礼が涙目の時臣の手を握りしめて妙に接近している、という光景が繰り広げられているその瞬間だった。
数分後、ギルガメッシュは時臣の手を掴んで雑踏を歩いていた。
「ま、待ってください英雄王!」
大股でずんずんと行くギルガメッシュに、時臣はついていくので精一杯である。手を引かれるままに小走りで付いて行く彼は、彼の王がどこへ向かおうとしているのかすら聞いていない。
しかも、屋敷から出てから一回も言葉を交わしていないのだ。屋敷でも、出かけるぞ、すぐに支度しろの二言だけだった。
「あっ、あ、マフラーが」
短時間で身支度させられたことが仇となり、巻いていた赤いマフラーが解けかかる。時臣が慌てて直そうとするも、ギルガメッシュの速度についていくのに集中していては、上手く巻き直せない。
ちっ、という舌打ちが聞こえてきて、やっと足は止まった。
「貸せ」
「え、英雄王の御手を煩わせるわけには」
「我がやると言っておるのだ。静止は聞かん」
掴んでいた手をとき、ギルガメッシュは振り返って時臣の方を向く。崩れて解けかけたマフラーをきっちりと巻き直し、その端を黒い外套の襟元に押し込んでやった。
「これで大丈夫か」
「あ、ありがとうございます」
礼を言った時臣は、巻き直されたマフラーを抑え、少々戸惑った様子である。
「…どうした」
「いえ、その…」
「はっきりしろ」
「はい。…その、英雄王は、どうやら苛立っているようですので、その理由を…」
言葉の最後は小さくなって消えた。ギルガメッシュの赤い瞳が、時臣を睨みつけている。何か、不興を買ってしまったことだけは確からしいと知るも、その原因は時臣には全くわからなかった。真っ直ぐに見つめる赤い瞳から逃れる理由を探すべく、あちこちに碧眼を走らせることしかできない。
しばらく時臣を睨みつけていたギルガメッシュは、しかし、はぁ、と唐突に嘆息する。
「お前な、我の恋人ならば、その自覚を少しは持て」
「?それは………」
「不用意にあんな危険な男にあんなに接近を許しおって」
「あんな危険な男?」
「貴様の弟子だ!先程抱き合っていたであろう!」
「綺礼ですか?別に綺礼は危険ではないですよ、可愛い私の弟子です。それに先程のことなら、私が綺礼を問い詰めていただけで別に抱き合っていたわけでは」
「そうでなかったとしても、そう見える態度を取るなと言っておるのだ!」
「ああ…。………つまり」
そこで、時臣は微笑んだ。
何かを納得したようなその表情に、一瞬ギルガメッシュはたじろぐ。
「英雄王は、嫉妬してくださっていたのですか?」
「ば………っ」
馬鹿なことを言うな、と言いかけた言葉は飲み込まれ、本心は、みるみるうちに赤くなるその顔色が示していた。
「………ふふ」
時臣の声が溢れる。
「あんまり王が怖い顔をなさっているので、嫌われてしまったかと思いました」
「我が貴様を嫌うわけがなかろう」
「ええ、それは良かったです」
くすくすと笑い続ける時臣に、怒気もすっかり抜かれ、ギルガメッシュはふてくされた表情を浮かべるしか無い。
「…フン。行くぞ」
今度は指を絡めて時臣の手を握り、ギルガメッシュは歩き出す。先程よりも落ちたスピードに、時臣は彼の隣に並んで歩くことができた。
「そう言えばお聞きしそびれておりました。私たちはどこへ向かっているのです?」
「ケーキ屋だ」
「ケーキ屋?」
「先程、貴様が綺礼を問い詰めていたのであろうが。奴はケーキの予約をしていなかったのだろう?」
「ああ、そうでした」
途端に時臣がしょんぼりとした顔をする。
「ヴィタメールで、ケーキを予約しようと思っていたのです。リースの形をした可愛らしいムースで…。きっと、葵も凛も気に入るだろうと思って選んだのですが」
「…綺礼の奴には、後でもう一度罰を与えてやらねばならんな」
「罰…ですか?でも、綺礼もうっかり聞き間違えただけだと言っていましたし」
「………貴様、あんまり奴のこと信頼しすぎるなよ」
恐らくは騙されているのであろう時臣に、ギルガメッシュはそれくらいしか言ってやることができなかった。
ギルガメッシュの嫌そうな態度に、やはり心当たりはないのだろう。時臣はきょとんと首を傾げて彼の王の横顔を眺めていたが、やがて話題を変えるようにぽつりと漏らした。
「…しかし、今から出かけて、まだケーキが残っているのでしょうか?」
予約を受け付けているくらいなのだから、やはりクリスマスはケーキがよく売れるのだろうし、時間は既に17時を回ろうとしている。
不安げな時臣をちらりと見て、ギルガメッシュは答えた。
「さあな。行ってみて、もう残っていなければ作るしかあるまい」
「作る…ですか。できれば、ご遠慮したいところですね」
王の提案に、時臣は困った顔をする。時臣は料理が苦手なのだ。炎を自身の属性としているためか、物を焼く位ならば得意なのだが細かい作業が苦手だ。うっかり包丁で指を切りそうになったり、測りかけの砂糖をこぼしたりする。それに、レンジやオーブンの類は機械が苦手であるため触りたくない。ケーキを焼くとなれば「測る」やオーブンが必要となることはわかりきったことだ。
不安そうな色合いを濃くする時臣の手を、ギルガメッシュは強めに握り、励ましてやった。
「フン、貴様が料理を不得手としていることくらいは知っておるわ。我が手伝ってやる」
「ああ、でも綺礼は得意ですよ。彼にも手伝ってもらいましょう」
「奴はやめておけ」
「嫉妬ですか?」
「………嫉妬だ」
「ふふ、では、やめておきますね」
途端に機嫌を直しふわふわと笑う時臣と、時臣の望むままに言葉を紡がされ不機嫌になるギルガメッシュ。
二人の足は、いつの間にかとある建物の前にたどり着いていた。見上げた看板には「不二家」とある。
「ここですか?」
「ああ」
店先に立つ少女の像を時臣は眺める。デフォルメされたキャラクターの少女は、クリスマスらしい赤い服に身を包み、舌をちょこんと出してプラスチックの瞳で時臣を見返した。
「入るぞ」
「あ、はい」
ギルガメッシュに手を引かれるままに、時臣はその店に一歩足を踏み入れた。
狭い店は、混雑していた。
「お、王…」
人波にぎゅうぎゅう押されながら、不安そうに時臣がギルガメッシュを見上げる。
「こっちだ。並ぶぞ、時臣」
ケーキの陳列されたガラスケースの前には所狭しと人が並び、全く中を伺うことが出来ない。大人も子供も老人もいる。
入店した瞬間に「いらっしゃいませ!」の掛け声とともに渡された紙はどうやら、見えないガラスケースの代わりらしい。様々なケーキの写真がプリントされ、どうやら、注文のために並んでいる間にそこから選べということらしかった。
列の最後尾につくとやっと満足に立てる程度のスペースが確保でき、時臣はふうと肺に溜まっていた息を吐きだした。
「ほれ時臣、これを見ろ」
ギルガメッシュは、入り口で受け取ったメニュー紙を時臣の目の前に晒す。
「こういうのがあるようだぞ」
「…………色々なものがあるのですねぇ」
白いクリームのショートケーキ。黒いクリームのチョコケーキ。そこまでならば時臣でも想像できる範囲だったが、キャラクターをモチーフにしたデコレーションケーキ、カットケーキを組み合わせたミックスケーキなどになると、想像の範囲外だった。というか、4分の1に切ったホールケーキを組み合わせて1つのホールケーキにするなどといった発想がまずない。
人たちの列がじり、と進む。ギルガメッシュは未だ握ったままの時臣の手を引き、1歩足を進めた。
「どれにするのだ?」
「どれが良いのでしょうか…」
予想よりも多い数の写真に、途方に暮れたように時臣は首を傾げた。
「これも、これも、美味しそうですね。こちらは可愛らしくて…凛が喜びそうだ」
一つ一つ指差し、どれがいいのでしょうねと困ったような声で呟くくせに、その表情はとても楽しそうだ。視線はメニューの上の写真に固定され、きらきらとした瞳がケーキを映す。その横顔が歳相応以上に幼く見えて、ギルガメッシュはにやつきそうになる口元を慌てて引き締めた。
遠坂家当主として家訓を守るべく、常に優雅を心がけて行動する時臣はいつだって完璧で、退屈でつまらない。だが、今はその仮面が剥がれている。イベントに浮かれているのか、それとも自分と二人きりだからなのかは分からないが、後者であればいいとギルガメッシュは思う。
また列が進んで、ギルガメッシュはメニューに夢中になっている時臣の手を引いてやった。
「選べぬのなら全て買えば良かろう」
「そんなに量は食べられませんよ」
うーん、と時臣が唸っている間も、どんどんと列は進んでいく。何気なくギルガメッシュが振り向くと、最初に彼らが入ってきて並んだ最後尾の位置には、また新しく列が続いていた。
「おい時臣。もうすぐレジだぞ」
「はい、ああ、でも………どうしましょう」
「どれで迷っておるのだ」
「これと…それからこれと………、ああ、でもこちらも素敵ですね…」
時臣は、完全にケーキに夢中である。問いに答える声も心ここにあらずといった風で、ギルガメッシュは少し面白くない。
「そんなもの、どれでもよかろう」
「どれでも…とは…。しかし、葵や凛の喜ぶものを」
「それならこれで良かろう」
ギルガメッシュが適当に指さしたのは、プティフールのセットだった。生クリームがある、チョコクリームがある。いちごの乗ったもの、抹茶味、様々な味の小さなケーキの詰め合わせである。
「あ………」
時臣の目から溢れていたものだった。クリスマスと言えばケーキ、ケーキといえばホールケーキ、という発想に捕らわれていたのだ。
確かに、カラフルで様々なケーキは目を楽しませてくれるし、好きな味のものを選ぶというたのしみもある。一瞬で、時臣の心は決まった。
「そうですね、これにしましょう」
「ん、良いのか?貴様、かなり悩んでおったではないか」
「ええ。ですが、他ならぬ私の王が選んで下さったものですから」
にこ、と笑んだ瞳で見上げられ、ギルガメッシュの頬も緩む。
折よく、次のお客様、と呼ばれる声がした。
帰路、である。
ギルガメッシュの手には、ついでに寄った雑貨屋で買い込んだクリスマスの飾りが、時臣の手には15個入りのプティフールの袋があった。
「さあ、早く帰らないと。葵たちが来る時間になってしまいます」
綺礼も待っているでしょうし、と自分を引っ張ろうとする時臣を、ギルガメッシュが後ろから眺めていた。
「まあいいではないか、少しくらい遅刻をしても」
二人の空いた手は未だしっかりとつなぎ合わされており、離れる気配はない。ぐいぐいと時臣に引かれる手を見て、ギルガメッシュは行きとは正反対だ、と思う。
「駄目ですよ、凛に示しが付きません」
「もう少し二人で歩きたいという我の気持ちを無下にするのか?」
そんな冗談を言ってみると、ふ、と足が止まった。振り向いた碧は驚いたように見開かれていた。それを受け止める赤も、そんな反応を期待していたわけではなかったので、同じように開かれる。
しばらくの沈黙の後、時臣がぽつりと呟いた。
「……………もしかしてこれは、デートだったのでしょうか?」
恋人同士が二人きり、クリスマスイブに手をつないで。
それは、デートだったのか、と。
自覚した瞬間、ギルガメッシュの頬が熱くなる。それを見た時臣の頬も、ぱっと染まった。
「あ………、その」
「いい!何も言うな!」
とたんに落ち着かな気に視線を足元に向ける時臣。そんな時臣を正視することができなくなるギルガメッシュは、ぐい、と繋いだままの手を引き寄せた。
「わっ」
胸元にぽすんと落ちてくる体重。繋いだ手を一旦離して、背を抱く。片手に持ったままの荷物が忌々しい。おずおずと、向こうからも手を回されるのを感じた。
「…………んっ」
どちらからとも無く見つめ合い、寄せた唇は冷たい。ちゅ、と、男二人の間に立つには可愛らしすぎるリップ音を立て、二つは離れた。時臣の伏せていた睫毛がそっと開けられ、碧玉が紅玉を映す。
「…………だったらどうする」
ギルガメッシュの言葉は、先程の時臣の問いへの回答だ。
ぎゅ、と背を抱く腕に力が込められたのを、時臣は感じた。
「………王」
その顔をしばらく見上げ、。
「…それならば、もう少しゆっくり歩きましょうか」
「………ああ」
そして時臣は抱き寄せられた胸元に、頬を擦りつけた。背を抱く腕の暖かさに、身を預けて。
「時臣」
「はい」
「今宵は聖夜だな」
「ええ、そうですね」
「だからな、……今宵の貴様を、我が予約しておこう」
「予約、ですか?………ふふ、まるでケーキのようですね」
「甘い貴様に最適ではないか」
「甘いかどうかはわかりませんが…。ふふ、ですが、我が王」
「うん?」
「予約などせずとも、私はこんなに素晴らしいケーキを買うことが出来ました」
「…ああ」
「ですから、予約などしない方が美味しいものを味わえることもあるということですね」
「…何が言いたい?」
「………予約などされずとも、今宵は私の方からお伺いしようと思いましたのに」
「…………………。…今宵は寝かさぬぞ。覚悟しておけ」
「ええ。王の慈悲に感謝いたします」
帰路を往く二つの影は、繋いだ手で一つにつながっている。
導師の帰りが遅いのを心配した弟子によって、その手が勢い良く外されるまで、あと数分。
ご予約はお早めに
12月24日。この日、遠坂邸ではパーティが企画されていた。
パーティ、とはいえささやかなものである。出席者は遠坂家の面々とそれから時臣の弟子である綺礼だけで、後は話を聞きつけたギルガメッシュが我も参加するぞ面白そうだから、と言った程度。
ただ、どうせやるのならば準備も念入りにと、時臣と綺礼、それから巻き込まれたギルガメッシュはパーティに向けて準備を進めていた。
いや、進めていたはず、だった。
「え?」
綺礼の言葉に、パーティのための部屋の飾りつけを進めていた時臣が振り返った。両手に壁に飾る紙輪の飾りを持ったままぽかんとした表情の彼に、綺礼は愉悦!と叫びたくなるのを堪える。
冒頭のそれは、「そう言えばケーキは何時に取りに行けばいいんだったかな。予約の時間に間に合うといいんだが」という時臣の発言に対する回答である。唐突に放たれたその一撃は、どうやら時臣に致命的なダメージを与えたらしい。
「い、今何て、綺礼?」
「ですから、ケーキの予約などしておりませんと言ったのです」
ぱた、と時臣の手から紙輪が落ちた。
「え?…いや、だって私お願いしたよね?ヴィタメールのショコラ・クロンヌ予約しといてって言ったよね?」
「ああ、そう仰っていたんですか。すみません、よく聞こえなくてヴィトンのショルダーバック買って来ました」
「えええ!?どうやったらそう聞き間違えられるんだい!?」
ちら、と肩からかけた鞄を示してみせると、時臣がすごい勢いで駆け寄ってきた。
こんな師見たこと無い!と心中で愉悦を覚えている綺礼をよそに、時臣は綺礼の胸ぐらを掴んでぐいぐいと揺さぶってきた。ただ、そう力が強くない上に相手はガチムチ神父。服の首元が多少伸びる程度で、綺礼は微動だにしない。
「ど、どうするんだ!クリスマスは、もう今日だぞ!」
「いやあすみません。うっかりうっかり」
「ケーキがなかったら葵や凛が悲しむじゃないか!」
ぐ、と揺さぶられるのが止まる。綺礼を見上げる碧い目の濃いまつげに、水分が溜まっていた。すみませんを繰り返しながら、その目尻に小さくキスを贈る。
「ん、」
無味の水分を舐めとると、綺礼は自分の首元を未だ握りしめている時臣の手をそっと外させた。片手でその手を握りしめながら顔を覗き込み、もう片方の手で肩にかけていた鞄を器用に外して時臣の方へ差し出す。
「すみませんでした。代わりに、この鞄は差し上げます」
「…そんなことで、ほだされる私だと思うなよ」
むすっとして涙を浮かべた表情のまま、それでも時臣はそれを受け取って、ありがとう、と言った。
「おい時臣!ツリーの飾り付けが足りな───」
がちゃ!と大きな音を立ててドアが開き、ギルガメッシュが現れたのはその直後。
綺礼が涙目の時臣の手を握りしめて妙に接近している、という光景が繰り広げられているその瞬間だった。
数分後、ギルガメッシュは時臣の手を掴んで雑踏を歩いていた。
「ま、待ってください英雄王!」
大股でずんずんと行くギルガメッシュに、時臣はついていくので精一杯である。手を引かれるままに小走りで付いて行く彼は、彼の王がどこへ向かおうとしているのかすら聞いていない。
しかも、屋敷から出てから一回も言葉を交わしていないのだ。屋敷でも、出かけるぞ、すぐに支度しろの二言だけだった。
「あっ、あ、マフラーが」
短時間で身支度させられたことが仇となり、巻いていた赤いマフラーが解けかかる。時臣が慌てて直そうとするも、ギルガメッシュの速度についていくのに集中していては、上手く巻き直せない。
ちっ、という舌打ちが聞こえてきて、やっと足は止まった。
「貸せ」
「え、英雄王の御手を煩わせるわけには」
「我がやると言っておるのだ。静止は聞かん」
掴んでいた手をとき、ギルガメッシュは振り返って時臣の方を向く。崩れて解けかけたマフラーをきっちりと巻き直し、その端を黒い外套の襟元に押し込んでやった。
「これで大丈夫か」
「あ、ありがとうございます」
礼を言った時臣は、巻き直されたマフラーを抑え、少々戸惑った様子である。
「…どうした」
「いえ、その…」
「はっきりしろ」
「はい。…その、英雄王は、どうやら苛立っているようですので、その理由を…」
言葉の最後は小さくなって消えた。ギルガメッシュの赤い瞳が、時臣を睨みつけている。何か、不興を買ってしまったことだけは確からしいと知るも、その原因は時臣には全くわからなかった。真っ直ぐに見つめる赤い瞳から逃れる理由を探すべく、あちこちに碧眼を走らせることしかできない。
しばらく時臣を睨みつけていたギルガメッシュは、しかし、はぁ、と唐突に嘆息する。
「お前な、我の恋人ならば、その自覚を少しは持て」
「?それは………」
「不用意にあんな危険な男にあんなに接近を許しおって」
「あんな危険な男?」
「貴様の弟子だ!先程抱き合っていたであろう!」
「綺礼ですか?別に綺礼は危険ではないですよ、可愛い私の弟子です。それに先程のことなら、私が綺礼を問い詰めていただけで別に抱き合っていたわけでは」
「そうでなかったとしても、そう見える態度を取るなと言っておるのだ!」
「ああ…。………つまり」
そこで、時臣は微笑んだ。
何かを納得したようなその表情に、一瞬ギルガメッシュはたじろぐ。
「英雄王は、嫉妬してくださっていたのですか?」
「ば………っ」
馬鹿なことを言うな、と言いかけた言葉は飲み込まれ、本心は、みるみるうちに赤くなるその顔色が示していた。
「………ふふ」
時臣の声が溢れる。
「あんまり王が怖い顔をなさっているので、嫌われてしまったかと思いました」
「我が貴様を嫌うわけがなかろう」
「ええ、それは良かったです」
くすくすと笑い続ける時臣に、怒気もすっかり抜かれ、ギルガメッシュはふてくされた表情を浮かべるしか無い。
「…フン。行くぞ」
今度は指を絡めて時臣の手を握り、ギルガメッシュは歩き出す。先程よりも落ちたスピードに、時臣は彼の隣に並んで歩くことができた。
「そう言えばお聞きしそびれておりました。私たちはどこへ向かっているのです?」
「ケーキ屋だ」
「ケーキ屋?」
「先程、貴様が綺礼を問い詰めていたのであろうが。奴はケーキの予約をしていなかったのだろう?」
「ああ、そうでした」
途端に時臣がしょんぼりとした顔をする。
「ヴィタメールで、ケーキを予約しようと思っていたのです。リースの形をした可愛らしいムースで…。きっと、葵も凛も気に入るだろうと思って選んだのですが」
「…綺礼の奴には、後でもう一度罰を与えてやらねばならんな」
「罰…ですか?でも、綺礼もうっかり聞き間違えただけだと言っていましたし」
「………貴様、あんまり奴のこと信頼しすぎるなよ」
恐らくは騙されているのであろう時臣に、ギルガメッシュはそれくらいしか言ってやることができなかった。
ギルガメッシュの嫌そうな態度に、やはり心当たりはないのだろう。時臣はきょとんと首を傾げて彼の王の横顔を眺めていたが、やがて話題を変えるようにぽつりと漏らした。
「…しかし、今から出かけて、まだケーキが残っているのでしょうか?」
予約を受け付けているくらいなのだから、やはりクリスマスはケーキがよく売れるのだろうし、時間は既に17時を回ろうとしている。
不安げな時臣をちらりと見て、ギルガメッシュは答えた。
「さあな。行ってみて、もう残っていなければ作るしかあるまい」
「作る…ですか。できれば、ご遠慮したいところですね」
王の提案に、時臣は困った顔をする。時臣は料理が苦手なのだ。炎を自身の属性としているためか、物を焼く位ならば得意なのだが細かい作業が苦手だ。うっかり包丁で指を切りそうになったり、測りかけの砂糖をこぼしたりする。それに、レンジやオーブンの類は機械が苦手であるため触りたくない。ケーキを焼くとなれば「測る」やオーブンが必要となることはわかりきったことだ。
不安そうな色合いを濃くする時臣の手を、ギルガメッシュは強めに握り、励ましてやった。
「フン、貴様が料理を不得手としていることくらいは知っておるわ。我が手伝ってやる」
「ああ、でも綺礼は得意ですよ。彼にも手伝ってもらいましょう」
「奴はやめておけ」
「嫉妬ですか?」
「………嫉妬だ」
「ふふ、では、やめておきますね」
途端に機嫌を直しふわふわと笑う時臣と、時臣の望むままに言葉を紡がされ不機嫌になるギルガメッシュ。
二人の足は、いつの間にかとある建物の前にたどり着いていた。見上げた看板には「不二家」とある。
「ここですか?」
「ああ」
店先に立つ少女の像を時臣は眺める。デフォルメされたキャラクターの少女は、クリスマスらしい赤い服に身を包み、舌をちょこんと出してプラスチックの瞳で時臣を見返した。
「入るぞ」
「あ、はい」
ギルガメッシュに手を引かれるままに、時臣はその店に一歩足を踏み入れた。
狭い店は、混雑していた。
「お、王…」
人波にぎゅうぎゅう押されながら、不安そうに時臣がギルガメッシュを見上げる。
「こっちだ。並ぶぞ、時臣」
ケーキの陳列されたガラスケースの前には所狭しと人が並び、全く中を伺うことが出来ない。大人も子供も老人もいる。
入店した瞬間に「いらっしゃいませ!」の掛け声とともに渡された紙はどうやら、見えないガラスケースの代わりらしい。様々なケーキの写真がプリントされ、どうやら、注文のために並んでいる間にそこから選べということらしかった。
列の最後尾につくとやっと満足に立てる程度のスペースが確保でき、時臣はふうと肺に溜まっていた息を吐きだした。
「ほれ時臣、これを見ろ」
ギルガメッシュは、入り口で受け取ったメニュー紙を時臣の目の前に晒す。
「こういうのがあるようだぞ」
「…………色々なものがあるのですねぇ」
白いクリームのショートケーキ。黒いクリームのチョコケーキ。そこまでならば時臣でも想像できる範囲だったが、キャラクターをモチーフにしたデコレーションケーキ、カットケーキを組み合わせたミックスケーキなどになると、想像の範囲外だった。というか、4分の1に切ったホールケーキを組み合わせて1つのホールケーキにするなどといった発想がまずない。
人たちの列がじり、と進む。ギルガメッシュは未だ握ったままの時臣の手を引き、1歩足を進めた。
「どれにするのだ?」
「どれが良いのでしょうか…」
予想よりも多い数の写真に、途方に暮れたように時臣は首を傾げた。
「これも、これも、美味しそうですね。こちらは可愛らしくて…凛が喜びそうだ」
一つ一つ指差し、どれがいいのでしょうねと困ったような声で呟くくせに、その表情はとても楽しそうだ。視線はメニューの上の写真に固定され、きらきらとした瞳がケーキを映す。その横顔が歳相応以上に幼く見えて、ギルガメッシュはにやつきそうになる口元を慌てて引き締めた。
遠坂家当主として家訓を守るべく、常に優雅を心がけて行動する時臣はいつだって完璧で、退屈でつまらない。だが、今はその仮面が剥がれている。イベントに浮かれているのか、それとも自分と二人きりだからなのかは分からないが、後者であればいいとギルガメッシュは思う。
また列が進んで、ギルガメッシュはメニューに夢中になっている時臣の手を引いてやった。
「選べぬのなら全て買えば良かろう」
「そんなに量は食べられませんよ」
うーん、と時臣が唸っている間も、どんどんと列は進んでいく。何気なくギルガメッシュが振り向くと、最初に彼らが入ってきて並んだ最後尾の位置には、また新しく列が続いていた。
「おい時臣。もうすぐレジだぞ」
「はい、ああ、でも………どうしましょう」
「どれで迷っておるのだ」
「これと…それからこれと………、ああ、でもこちらも素敵ですね…」
時臣は、完全にケーキに夢中である。問いに答える声も心ここにあらずといった風で、ギルガメッシュは少し面白くない。
「そんなもの、どれでもよかろう」
「どれでも…とは…。しかし、葵や凛の喜ぶものを」
「それならこれで良かろう」
ギルガメッシュが適当に指さしたのは、プティフールのセットだった。生クリームがある、チョコクリームがある。いちごの乗ったもの、抹茶味、様々な味の小さなケーキの詰め合わせである。
「あ………」
時臣の目から溢れていたものだった。クリスマスと言えばケーキ、ケーキといえばホールケーキ、という発想に捕らわれていたのだ。
確かに、カラフルで様々なケーキは目を楽しませてくれるし、好きな味のものを選ぶというたのしみもある。一瞬で、時臣の心は決まった。
「そうですね、これにしましょう」
「ん、良いのか?貴様、かなり悩んでおったではないか」
「ええ。ですが、他ならぬ私の王が選んで下さったものですから」
にこ、と笑んだ瞳で見上げられ、ギルガメッシュの頬も緩む。
折よく、次のお客様、と呼ばれる声がした。
帰路、である。
ギルガメッシュの手には、ついでに寄った雑貨屋で買い込んだクリスマスの飾りが、時臣の手には15個入りのプティフールの袋があった。
「さあ、早く帰らないと。葵たちが来る時間になってしまいます」
綺礼も待っているでしょうし、と自分を引っ張ろうとする時臣を、ギルガメッシュが後ろから眺めていた。
「まあいいではないか、少しくらい遅刻をしても」
二人の空いた手は未だしっかりとつなぎ合わされており、離れる気配はない。ぐいぐいと時臣に引かれる手を見て、ギルガメッシュは行きとは正反対だ、と思う。
「駄目ですよ、凛に示しが付きません」
「もう少し二人で歩きたいという我の気持ちを無下にするのか?」
そんな冗談を言ってみると、ふ、と足が止まった。振り向いた碧は驚いたように見開かれていた。それを受け止める赤も、そんな反応を期待していたわけではなかったので、同じように開かれる。
しばらくの沈黙の後、時臣がぽつりと呟いた。
「……………もしかしてこれは、デートだったのでしょうか?」
恋人同士が二人きり、クリスマスイブに手をつないで。
それは、デートだったのか、と。
自覚した瞬間、ギルガメッシュの頬が熱くなる。それを見た時臣の頬も、ぱっと染まった。
「あ………、その」
「いい!何も言うな!」
とたんに落ち着かな気に視線を足元に向ける時臣。そんな時臣を正視することができなくなるギルガメッシュは、ぐい、と繋いだままの手を引き寄せた。
「わっ」
胸元にぽすんと落ちてくる体重。繋いだ手を一旦離して、背を抱く。片手に持ったままの荷物が忌々しい。おずおずと、向こうからも手を回されるのを感じた。
「…………んっ」
どちらからとも無く見つめ合い、寄せた唇は冷たい。ちゅ、と、男二人の間に立つには可愛らしすぎるリップ音を立て、二つは離れた。時臣の伏せていた睫毛がそっと開けられ、碧玉が紅玉を映す。
「…………だったらどうする」
ギルガメッシュの言葉は、先程の時臣の問いへの回答だ。
ぎゅ、と背を抱く腕に力が込められたのを、時臣は感じた。
「………王」
その顔をしばらく見上げ、。
「…それならば、もう少しゆっくり歩きましょうか」
「………ああ」
そして時臣は抱き寄せられた胸元に、頬を擦りつけた。背を抱く腕の暖かさに、身を預けて。
「時臣」
「はい」
「今宵は聖夜だな」
「ええ、そうですね」
「だからな、……今宵の貴様を、我が予約しておこう」
「予約、ですか?………ふふ、まるでケーキのようですね」
「甘い貴様に最適ではないか」
「甘いかどうかはわかりませんが…。ふふ、ですが、我が王」
「うん?」
「予約などせずとも、私はこんなに素晴らしいケーキを買うことが出来ました」
「…ああ」
「ですから、予約などしない方が美味しいものを味わえることもあるということですね」
「…何が言いたい?」
「………予約などされずとも、今宵は私の方からお伺いしようと思いましたのに」
「…………………。…今宵は寝かさぬぞ。覚悟しておけ」
「ええ。王の慈悲に感謝いたします」
帰路を往く二つの影は、繋いだ手で一つにつながっている。
導師の帰りが遅いのを心配した弟子によって、その手が勢い良く外されるまで、あと数分。
珍しくギル時ちゃん!
ギル時はギャグテイストな感じがすきです
あと時臣師が綺礼ちゃん信頼しててギル様がぐぬぬってるギル時すごいすき
2012年のケーキ参考にして書いた。
でも貴族的ケーキってわからんよ…
庶民ケーキ選ばせちゃってごめんね時臣師
ギル時はギャグテイストな感じがすきです
あと時臣師が綺礼ちゃん信頼しててギル様がぐぬぬってるギル時すごいすき
2012年のケーキ参考にして書いた。
でも貴族的ケーキってわからんよ…
庶民ケーキ選ばせちゃってごめんね時臣師