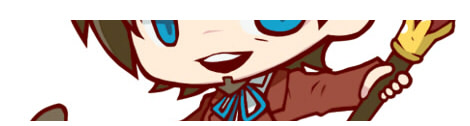
───爆発音、そして振動。
その日綺礼を目覚めさせたのは、そんな非日常的なものだった。
(敵襲?──いや…まさか)
まだ聖杯戦争は始まってすらいない。それにここは魔術師・遠坂時臣の屋敷だ。そう簡単に敵の襲撃を許すとは思えない。
(ならば、一体何事が…)
思考よりも早く、綺礼の体は動いていた。爆発音は1階、キッチンの方角からである。黒鍵を手にし、綺礼は走り出した。
そしてたどり着いた先で見たものを理解した瞬間、綺礼はぽかんとすることしかできなかった。
何故なら、綺礼の目にした光景は。
──真っ黒に煤けた壁と天井、それからそれらを前に佇む、導師の姿。
「ああ……。すまない綺礼。起こしてしまったかな」
壁や天井と同じく煤けた顔をしかし優雅に微笑ませて振り返る導師、それからこの惨状の中心にある壊れたオーブンの存在を見止め。
…状況をなんとなく理解した綺礼は、頭を抱えたくなった。
とりあえずは、すすで汚れた時臣の顔を洗い、服に散ったものもはたき落とした。それから、指先に負っていた火傷を治療してやる。
綺礼は随分治癒がうまくなったねぇとのんびりと言う時臣に、もう一度、説明してくださいますねと繰り返す。碧い目は揺れて逸らされた。
「その……料理をしようと思って」
「料理、ですか」
その言葉に思い出す。そういえば、この家で料理を司る家主の妻は、現在娘たちを連れて帰省中だったのだと。
「それならば、使用人に任せれば…」
いいかけて、嫌な予感に口をつぐむ。綺礼は気づいてしまった。家の中に、自分と導師の二人だけの気配しかないことに。果たして、時臣の口から衝撃的な事実がもたらされる。
「ああ……。…実は、うっかり今日は全員に暇を出してしまっていてね」
「………………………」
うっかりとかそういうレベルではないでしょう、と突っ込みたくなる気持ちを押し殺す。そんなことは、彼に師事して1週間目くらいの時からわかっていた事だ。
「………大体のことはわかりました」
キッチンの惨状を改めて見る。
オーブンを中心に、壁と天井が真っ黒に焦げている。トーストを焼こうとしたのかミルクを温めようとしたのかは知らないが、時臣はこの可哀想なオーブンに対してスキル『機械音痴:EX』を遺憾なく発揮したのだろう。焦げてドアの外れたオーブンは、いっそ芸術的にさえ見えた。
唯一幸運だったことは、これがそろそろ買い替え時の家電だったことだ。既に古くなって動作も不安定にはなっていたから、買い換える明確な理由ができて、彼の妻などは逆に喜ぶかもしれない。
「…あとは私がやります。片付けはあとにして、とりあえずは朝食を取りましょう」
「じゃあ、私は……」
「時臣師は、先に席についていてください」
「え、でも」
「次は何を壊すおつもりですか?冷蔵庫ですか、それともコーヒーメーカーですか?」
我ながら意地悪な言葉だ、と綺礼は思う。だが、これくらいは言わなければ、彼は善意で手伝おうとし、そして何かしらうっかりをやらかすのだろう。それの後始末をするのは、どう考えても自分になるのだ。できれば避けたい、と思うのは当然のことだ。
見るからに肩を落とした時臣をさすがに見かね、綺礼は口調を少しだけ柔らかくして続けた。
「朝から災難でしたね。朝食はパンでよろしいですか?」
「あ、ああ。トーストにしてくれるかな」
「バターもたっぷり載せておきますよ」
「意地悪だな、君は。私が最近体重を気にしていることを知っているくせに」
「でも、お好きでしょう?」
そう聞けば、ふてくされたような顔のまま小さな頷きが返ってきて、綺礼は満足する。
「それでは、先にテーブルへ。後はお任せください」
「分かった。……くれぐれも気をつけてくれよ」
朝食を作る相手に向けるには見当違いなセリフを残し、時臣はリビングに向かった。あとには、焦げたキッチンと綺礼だけが残される。
(さてと…)
惨状を再度一瞥し、嘆息。
とりあえずは宣言通りに朝食の用意をするため、綺礼は冷蔵庫へ向き直った。
戸棚から食パンの塊を取り上げる。既に何回か包丁を入れられているそれは半分ほどしか残っていないが、綺礼と時臣、2人分であるならば余るほど。
それを厚ぼったく3枚切り、内1枚をさらに縦半分に切る。1枚半、それがちょうどいい量なのだ。冷蔵庫からバターを取り出してきて、バターナイフで適当に載せる。どうせ溶ければどのように載せたかなんてわからないだろうから。
3枚分バターを載せ終わると、無造作にトースターに突っ込んでいく。タイマーを合わせスタートのボタンを押した。これで、あとトーストは待つだけだ。
その間にサラダでも作ろうか、と思い立った。体重を気にかけていると時臣が言っていたのが記憶の隅に残っていたのかもしれない。
冷蔵庫下段の野菜室からレタスとトマトを取り出し、軽く洗ってざくざくと刻む。さらにキュウリを取り出して、こちらは薄めのスライスに。食器棚から高級そうなガラスの器を取り出して、刻んだ野菜を適当に盛った。こういう時、器の力はすごいと思う。綺礼が適当に刻んだ野菜が、高級そうなサラダに見えるのだ。
ドレッシングは、と冷蔵庫を再度漁ると、手作りらしいフレンチドレッシングの瓶をみつけた。綺礼も食卓でよく見かけるものである。取り出して、サラダの器の横に置いた。後で一緒に運ぼう。
「………」
折よくトースターが鳴る。焼けたパンを取り出し、用意しておいた平皿に手早く載せる。その耳がカリカリといい色に色付いているのを見て、やはりいいトースターで焼くとこうも違うものなのかと思い知った。綺礼の持っているものは1つ2つ古い型の、しかも値段の安いタイプなので、熱の調整がうまく行かず、良く端から焦げてしまうのだ。
返す返すも、こんなにいい家電の持ち主があんなにも機械音痴であることが悔やまれる。
(本当に、何故あの人はトーストの1枚も────?)
満足に焼けないのか、と心の中の愚痴は、違和感により遮られた。
トースターを見る。綺礼が使ったままの状態で、静かにそれはそこにあった。視線を巡らし焦げた壁を見れば、そちらにはひしゃげてドアの開いたオーブンがある。
(………オーブン?)
先程は疑問にも思わなかったことが、急に気になりだした。
パンを焼くだけなら、操作が簡単なトースターで十分。ミルクを暖めたいのなら、時臣ならばオーブンなどという未知の道具に頼らず鍋で温める手段を取るはずだということに気がついたのである。
だったら、このオーブンは何故爆発した?
「…………」
焼け焦げた家電の成れの果てに近づき、よく見ようとした時だった。
「……綺礼?」
遠慮がちにかけられた声に振り返る。綺礼の視線にびくりと震えたその姿は、もちろん、先にリビングへ行っていたはずの時臣で。
「その……、結構時間がかかっているみたいだから。やっぱり何か手伝えることはないかと思って来たんだが」
ドアの影から覗く姿は、まゆを下げ、まるで親に怒られることを怯える子供のような雰囲気だ。
思わず苦笑に似たものが漏れる。彼を完璧な紳士だと信じ込んでいる彼の娘に見せてやりたい表情だ。なぜこの人は、自分に対しこんなに無防備なのだろうと綺礼は時々思う。それが、魔術師、なのだろうか。
「ああ、時臣師。ちょうどいい所に。サラダを作ったのですよ」
「へえ、美味しそうだね」
革靴の音を軽快に立てて、時臣が綺礼の隣まで歩いてくる。ボウルを覗きこんでそんな声を上げた。野菜を切っただけのものに美味しそうも何もないように思うが、それも器の力なのだろう。
「これと、あとパンと。一人では運べませんので、申し訳ありませんが手伝ってくださいますか」
「もちろんだよ。何を持って行こうか」
「それでは、サラダをお願いします」
「ああ、わかった。任せてくれたまえ」
ガラスの器を両手で1つずつ持ち上げ、時臣が微笑む。役に立てたことが嬉しいとでも言うような、自然な表情だった。
珍しい表情を見た、と綺礼は、表面上はなんの変化もないままに思う。何だか今日の導師は変だ。
「………」
オーブンの件もある。あとで聞こうと、と取り敢えずは焼けたばかりのトーストの皿とドレッシングを両手に持って、綺礼も時臣の後を追った。
テーブルの上には時臣の運んだサラダの器と、それから彼が入れたらしいコーヒーが並んでいた。テーブルクロスも綺麗に伸ばされている。これも、彼がやったのだろうか。
ぴんとした白いテーブルクロスの上に、パンの皿とドレッシングを下ろす。トースト、サラダ、ドレッシング、コーヒー。型にはめたような、美味しそうな朝食の光景が出来上がった。
朝の明るい光、白いテーブルクロスが眩しい。きらきらと光を受け水気を光らせるサラダ、湯気を立てるコーヒー。トーストのバターの匂い。
「美味しそうだな」
その食卓を前に、窓を背にして微笑む導師。カーテンの白、彼の服の赤。コントラスト。
「はい」
眩しくて、目を細める。
二人きりの食卓は静かになるだろうと綺礼は考えていたが、そうはならなかった。
「綺礼はトーストが上手だな」
「時臣師も、トースターは使えるでしょう」
「使えるが…駄目だね。すぐに焦げてしまうんだ」
「焦げる、ですか?温度の調整が間違っているのではないですか」
「温度?ううん、よくわからないな。今度教えてくれないだろうか、」
「私で宜しければ」
「ありがとう、助かるよ綺礼」
妻や娘がいる前では、彼らの見本となるべく、食器の音はたてず、背筋を伸ばして座り、口にものが入っている時に喋らず、テーブルマナーを心がけて振る舞う時臣は、綺礼と二人きりだからと大分その優雅さを崩していた。片手でトーストを持ったままではドレッシングの蓋を開けられないと、トーストを口に咥えて両手を空けるのを見た時には、さすがに綺礼もぽかんとしてしまった。しかし、時臣自身には敢えて普段と違うように振舞っているという自覚はないらしい。その仕草は、自然に見えた。
つつがなく、朝食の時間は進んでいく。
「………ああ、そうでした、時臣師」
「うん、何だい?」
うっかり触ってしまって指についたバターを舐めとる、という姿を晒している時臣に、綺礼は話しかけた。
「先程のオーブンの件なのですが」
「ああ………」
とたんに、その眉間に皺が寄る。
「…買い換えないとね。いや、その前に掃除か。随分と壁が黒くなってしまったからね…」
「いえ、掃除ならば明日誰かに任せれば良いでしょう。…それより」
「ん?」
「師は、なぜオーブンなど使われたのです?貴方が、あれに用事があるとは思えないのですが」
時臣が、少し首を傾げたまま固まる。
綺礼も同じ角度に首を傾げ、答えを待った。
「………」
「………」
「………………」
「………………」
「…………………………………ああ!いや、少し、使ってみたくなってね!」
「そんな理由で貴方があれに手を出すとは思えませんが」
すごく長い沈黙の挙句、視線をあちこちに走らせ、やっと言い訳を思いついたとばかりに発せられた言葉を冷たく切り払う。
時臣の機械嫌いは半端なものではないのだ。そんなちょっとした思いつきでオーブンなどという大掛かりなものに触れるとは思えない。良くて、テレビかラジオだろう。あれらが現代社会では便利なものらしいということくらいは、知っているだろうから。
綺礼の冷たさに、あーとかうーとか声を漏らしながら、時臣はまた視線をうろつかせる。答えを待ちながら、綺礼は思い出す言葉があった。
「…そういえば、料理をしていたと仰っていましたね」
それは、今日最初の会話だったはずだ。
爆発音に綺礼が飛び起きて、煤まみれの時臣と哀れなオーブンを見つけ、その理由を問いただした時の。
「何を作ろうとしていたのですか」
「う」
「こちらを向いてください」
びくり、と肩を弾ませて、時臣はさらに視線を逸らす。冷や汗がたらりと頬に流れるのが見えた。
「ええと、その、………トーストを」
「トーストならトースターで焼きますよね」
「コーヒーを」
「先程出して下さったコーヒーは、こちらのコーヒーメーカーでお淹れされたと思うのですが」
言い訳もだんだんと苦しくなる。
綺礼は意外に思った。この導師がこんなにも必死に嘘をつこうとしている姿など、初めて見た。いったい何が、彼をこんなにも必死にさせているのか───興味が、沸く。
ここまで問い詰めても態度が変わらないのならば、攻め方を変えるしかない。綺礼は、別の方向から攻めることにする。
「…そんなに、私に言いたくないようなことをしていたのですか」
「…………っ」
いわゆる、泣き落とし、というものだ。
眉尻を下げ、少しうつむき、声をワントーン落とす。涙の一つも故意に浮かべられれば良かったのだが、あいにくそういう器用な芸当は綺礼には出来ない。だが、身内に甘すぎる導師にとっては十分すぎる演技だったようだった。
「いや、その。そういうわけではないんだ」
「では、どういうわけなのですか。教えてくださらないのは、私が至らないせいですか」
「そんなわけないだろう!違うんだよ」
何が至らなければオーブンを使った理由を教えない理由になるのだろうか。めったに感情を見せない弟子が今にも泣きそうという状況を前に、時臣は会話の正当性すら認識できなくなっているらしい。全ては綺礼の思惑通りだというのに。
「ああ、もう、わかったよ。言えばいいのだろう」
それから2,3どうでもいい対話を重ね、折れたのは時臣だった。
教えてくださるのですか、と言えば、うん、と少し不貞腐れたような答え。
「………ケーキを、作ろうと思ったんだ」
「ケーキ、ですか?」
綺礼の脳裏をよぎるのは、時臣が好む優雅なティタイムであった。午後の3時頃、仕事を中断して家族や弟子と取るその時間を、彼が大切にしていることを知っている。その時間を楽しむために、とっておきの紅茶葉を取り寄せたり、妻や娘が好むスイーツを用意したりしていることも。そして、よく選ばれるスイーツが、彼の妻が特に好むフルーツケーキなのだ。生地にドライフルーツを混ぜて焼いたそれが、最初に思い浮かんだのである。
そんなことを綺礼が考えているのを知ってか知らずか、時臣は、いや、お茶の時間に食べるものではないんだよ、と言った。
「こう…もっと豪華な。クリームやフルーツの乗っている」
「ああ、デコレーションケーキですか」
「そう。そういうものが作りたかったんだよ」
「祝いの席の…例えば、バースデイケーキのような?」
それは、綺礼にすれば会話のキャッチボールの中の一つの言葉だったにすぎない。
だが、時臣を驚かせるには十分な言葉だった。
「綺礼、きみ…。…………わかってて、私に言わせようとしていたのかい」
「え?」
「人が悪いなぁ………」
一人で納得したようにうなずき、苦笑する時臣に、綺礼はついて行けない。首をかしげるも、時臣の中では既に綺礼は、全て知っていてその上で自分を試そうとした意地悪な人、という風になっているようだった。
「うっかり全員に暇を出してしまったし、タイミング悪く葵もいないし、それならば私がやるしかないだろう?」
何の話なのか。置いていかれた綺礼は言葉をはさもうとするが、時臣はそれを察せず続ける。
「これでもね、がんばろうと思ったんだよ。本だって、朝電話して葵に借りたのだし」
「本、ですか」
「そうさ。粉を分量通り測ってね、混ぜて、オーブンで焼くんだ」
測って混ぜて、と、ジェスチャーをつけながら時臣が言う。
「だけど、まさか爆発するなんてな…。おかげで君にバレてしまった」
「私にバレるとまずいことでも?」
「まずいわけではないがね。こういうのは普通、サプライズのためにこっそりとやるだろう?」
ほら案の定君はこんなに落ち着いているじゃないか、と時臣は悲しそうな顔ををする。
「サプライズ…?」
「もうバレてしまったのだから、サプライズにはならないだろうが。君の」
君の誕生日を祝うケーキなんて。と。
時臣はそう言った。
時臣は、その企みがバレてしまった悲しさを嘆いている。せっかくケーキを作って祝おうとしていたのに、と。君の欲しいものを知らないから、せめてケーキはと。しかし綺礼にはその言葉は届いていなかった。その直前の衝撃が尾を引いていたので。
君の誕生日を祝うケーキ、と時臣は言った。「君」なんて言葉は目の前にいる相手に対して使われる二人称で、今現在時臣の前にいるのは綺礼ただ一人。であるなら、綺礼に向けられた言葉なのだろう、君の誕生日を祝う、というのは。綺礼に向けた言葉なのだ。
「しかし、やはり慣れないことは難しいね。今度から私も───」
「師、時臣師」
未だ喋り続けていた時臣の声を遮る。食卓さえなければ、飛び出していただろう。
「今のは、今のは本当ですか」
「今の?少しは私も料理を出来るようになったほうがいいかという話かい?」
「違います、その前の」
会話がもどかしい。確認したい。
「ああ、君の誕生日のケーキの話かな」
さらりと、何事でもないかのように、時臣は言った。
綺礼の誕生日。12月28日。
確かにそれは、今日だった。
「何だ、当てずっぽうで言ったのかい?最初からバレていた上で問い詰められていると思ったのだが」
ぽかんとした様子の綺礼に、少々毒気が抜かれたような表情で、時臣が言った。
「………ていました」
「うん?」
「忘れて、いました」
自分ですら忘れていたそれを、時臣は覚えていたのだ。覚えていて、祝おうとしてくれたのだ。慣れぬ事をしてまで。
「すみません、でした」
ぽつりと、こぼれるような言葉に、時臣は苦笑する。
「何で謝るんだい。君は何も悪いことをしていないじゃないか」
「貴方の心を、貴方を、勘違いしていました」
「君の中の私が一体どんな存在なのか気になる発言だね」
くすくすと時臣が笑う。綺礼は、萎縮していた。
「でも、実際私は何も出来ていやしないんだからね。ケーキを焼くどころかオーブンを壊し、朝食の支度だって君に任せっぱなしだ」
「ですが、貴方は私を祝おうとしてくださいました」
「それなら、なおさら謝るところではないだろう。まあ、当人が言うことでもないが、もう少しふさわしい言葉があるのではないかな」
綺礼は少し考えて、ありがとうございます、と言った。
それに時臣は、どういたしまして、と返した。
「私には、ケーキを焼くのはどうやら敷居が高いようだからね。後で、二人で買いに行こう」
「はい」
「どんなケーキがいいかな。昔凛のケーキを買った時みたいに、名前を入れてくれるサービスはあるのかな」
「…それは、さすがに恥ずかしいです」
「ふふ。それから、もうバレてしまったから聞くが、君は何か欲しい物があるのかな」
「それを、望んでも良いのですか?」
「言ってごらん。…まあ、余り入手の難しい品はすぐには用意できないだろうけど」
「それならば、師よ。一つだけ」
「なんだい、綺礼?」
「今日は、使用人も、それから奥方もご子女も、誰もおらず、屋敷内は寂しいので」
「ああ」
「………今日は一日ずっと、お側において頂けますか」
「そんなこと!」
こんな特別な日じゃなくたっていつだって、私の方から望みたいくらいだよ、と時臣は言った。
「だから、そうだな、もう少し、高い望みを言ってごらん」
「それならば、師よ」
「なんだい」
「これからもずっと。お側において頂けますか」
「それだって、全然特別なことじゃないじゃないか」
でも、そうだな、と時臣は言う。
「それが、君の一番欲しいものならば。君が、そんな顔をしてまで欲しいものだというのなら、それをプレゼントにさせてくれるかい」
これからも、ずっと共に。
握手でも誘うかのように伸ばされた時臣の右手を両手で握りしめ、綺礼はもう一度ありがとうございますと言った。
握りしめて唇を落とす、赤い印の浮いたその手の甲は暖かく。
その暖かさに、永遠を見た、ような気がした。
その日綺礼を目覚めさせたのは、そんな非日常的なものだった。
(敵襲?──いや…まさか)
まだ聖杯戦争は始まってすらいない。それにここは魔術師・遠坂時臣の屋敷だ。そう簡単に敵の襲撃を許すとは思えない。
(ならば、一体何事が…)
思考よりも早く、綺礼の体は動いていた。爆発音は1階、キッチンの方角からである。黒鍵を手にし、綺礼は走り出した。
そしてたどり着いた先で見たものを理解した瞬間、綺礼はぽかんとすることしかできなかった。
何故なら、綺礼の目にした光景は。
──真っ黒に煤けた壁と天井、それからそれらを前に佇む、導師の姿。
「ああ……。すまない綺礼。起こしてしまったかな」
壁や天井と同じく煤けた顔をしかし優雅に微笑ませて振り返る導師、それからこの惨状の中心にある壊れたオーブンの存在を見止め。
…状況をなんとなく理解した綺礼は、頭を抱えたくなった。
ひとつ、君と。
「一体何事があったのか。──説明してくださいますね」とりあえずは、すすで汚れた時臣の顔を洗い、服に散ったものもはたき落とした。それから、指先に負っていた火傷を治療してやる。
綺礼は随分治癒がうまくなったねぇとのんびりと言う時臣に、もう一度、説明してくださいますねと繰り返す。碧い目は揺れて逸らされた。
「その……料理をしようと思って」
「料理、ですか」
その言葉に思い出す。そういえば、この家で料理を司る家主の妻は、現在娘たちを連れて帰省中だったのだと。
「それならば、使用人に任せれば…」
いいかけて、嫌な予感に口をつぐむ。綺礼は気づいてしまった。家の中に、自分と導師の二人だけの気配しかないことに。果たして、時臣の口から衝撃的な事実がもたらされる。
「ああ……。…実は、うっかり今日は全員に暇を出してしまっていてね」
「………………………」
うっかりとかそういうレベルではないでしょう、と突っ込みたくなる気持ちを押し殺す。そんなことは、彼に師事して1週間目くらいの時からわかっていた事だ。
「………大体のことはわかりました」
キッチンの惨状を改めて見る。
オーブンを中心に、壁と天井が真っ黒に焦げている。トーストを焼こうとしたのかミルクを温めようとしたのかは知らないが、時臣はこの可哀想なオーブンに対してスキル『機械音痴:EX』を遺憾なく発揮したのだろう。焦げてドアの外れたオーブンは、いっそ芸術的にさえ見えた。
唯一幸運だったことは、これがそろそろ買い替え時の家電だったことだ。既に古くなって動作も不安定にはなっていたから、買い換える明確な理由ができて、彼の妻などは逆に喜ぶかもしれない。
「…あとは私がやります。片付けはあとにして、とりあえずは朝食を取りましょう」
「じゃあ、私は……」
「時臣師は、先に席についていてください」
「え、でも」
「次は何を壊すおつもりですか?冷蔵庫ですか、それともコーヒーメーカーですか?」
我ながら意地悪な言葉だ、と綺礼は思う。だが、これくらいは言わなければ、彼は善意で手伝おうとし、そして何かしらうっかりをやらかすのだろう。それの後始末をするのは、どう考えても自分になるのだ。できれば避けたい、と思うのは当然のことだ。
見るからに肩を落とした時臣をさすがに見かね、綺礼は口調を少しだけ柔らかくして続けた。
「朝から災難でしたね。朝食はパンでよろしいですか?」
「あ、ああ。トーストにしてくれるかな」
「バターもたっぷり載せておきますよ」
「意地悪だな、君は。私が最近体重を気にしていることを知っているくせに」
「でも、お好きでしょう?」
そう聞けば、ふてくされたような顔のまま小さな頷きが返ってきて、綺礼は満足する。
「それでは、先にテーブルへ。後はお任せください」
「分かった。……くれぐれも気をつけてくれよ」
朝食を作る相手に向けるには見当違いなセリフを残し、時臣はリビングに向かった。あとには、焦げたキッチンと綺礼だけが残される。
(さてと…)
惨状を再度一瞥し、嘆息。
とりあえずは宣言通りに朝食の用意をするため、綺礼は冷蔵庫へ向き直った。
戸棚から食パンの塊を取り上げる。既に何回か包丁を入れられているそれは半分ほどしか残っていないが、綺礼と時臣、2人分であるならば余るほど。
それを厚ぼったく3枚切り、内1枚をさらに縦半分に切る。1枚半、それがちょうどいい量なのだ。冷蔵庫からバターを取り出してきて、バターナイフで適当に載せる。どうせ溶ければどのように載せたかなんてわからないだろうから。
3枚分バターを載せ終わると、無造作にトースターに突っ込んでいく。タイマーを合わせスタートのボタンを押した。これで、あとトーストは待つだけだ。
その間にサラダでも作ろうか、と思い立った。体重を気にかけていると時臣が言っていたのが記憶の隅に残っていたのかもしれない。
冷蔵庫下段の野菜室からレタスとトマトを取り出し、軽く洗ってざくざくと刻む。さらにキュウリを取り出して、こちらは薄めのスライスに。食器棚から高級そうなガラスの器を取り出して、刻んだ野菜を適当に盛った。こういう時、器の力はすごいと思う。綺礼が適当に刻んだ野菜が、高級そうなサラダに見えるのだ。
ドレッシングは、と冷蔵庫を再度漁ると、手作りらしいフレンチドレッシングの瓶をみつけた。綺礼も食卓でよく見かけるものである。取り出して、サラダの器の横に置いた。後で一緒に運ぼう。
「………」
折よくトースターが鳴る。焼けたパンを取り出し、用意しておいた平皿に手早く載せる。その耳がカリカリといい色に色付いているのを見て、やはりいいトースターで焼くとこうも違うものなのかと思い知った。綺礼の持っているものは1つ2つ古い型の、しかも値段の安いタイプなので、熱の調整がうまく行かず、良く端から焦げてしまうのだ。
返す返すも、こんなにいい家電の持ち主があんなにも機械音痴であることが悔やまれる。
(本当に、何故あの人はトーストの1枚も────?)
満足に焼けないのか、と心の中の愚痴は、違和感により遮られた。
トースターを見る。綺礼が使ったままの状態で、静かにそれはそこにあった。視線を巡らし焦げた壁を見れば、そちらにはひしゃげてドアの開いたオーブンがある。
(………オーブン?)
先程は疑問にも思わなかったことが、急に気になりだした。
パンを焼くだけなら、操作が簡単なトースターで十分。ミルクを暖めたいのなら、時臣ならばオーブンなどという未知の道具に頼らず鍋で温める手段を取るはずだということに気がついたのである。
だったら、このオーブンは何故爆発した?
「…………」
焼け焦げた家電の成れの果てに近づき、よく見ようとした時だった。
「……綺礼?」
遠慮がちにかけられた声に振り返る。綺礼の視線にびくりと震えたその姿は、もちろん、先にリビングへ行っていたはずの時臣で。
「その……、結構時間がかかっているみたいだから。やっぱり何か手伝えることはないかと思って来たんだが」
ドアの影から覗く姿は、まゆを下げ、まるで親に怒られることを怯える子供のような雰囲気だ。
思わず苦笑に似たものが漏れる。彼を完璧な紳士だと信じ込んでいる彼の娘に見せてやりたい表情だ。なぜこの人は、自分に対しこんなに無防備なのだろうと綺礼は時々思う。それが、魔術師、なのだろうか。
「ああ、時臣師。ちょうどいい所に。サラダを作ったのですよ」
「へえ、美味しそうだね」
革靴の音を軽快に立てて、時臣が綺礼の隣まで歩いてくる。ボウルを覗きこんでそんな声を上げた。野菜を切っただけのものに美味しそうも何もないように思うが、それも器の力なのだろう。
「これと、あとパンと。一人では運べませんので、申し訳ありませんが手伝ってくださいますか」
「もちろんだよ。何を持って行こうか」
「それでは、サラダをお願いします」
「ああ、わかった。任せてくれたまえ」
ガラスの器を両手で1つずつ持ち上げ、時臣が微笑む。役に立てたことが嬉しいとでも言うような、自然な表情だった。
珍しい表情を見た、と綺礼は、表面上はなんの変化もないままに思う。何だか今日の導師は変だ。
「………」
オーブンの件もある。あとで聞こうと、と取り敢えずは焼けたばかりのトーストの皿とドレッシングを両手に持って、綺礼も時臣の後を追った。
テーブルの上には時臣の運んだサラダの器と、それから彼が入れたらしいコーヒーが並んでいた。テーブルクロスも綺麗に伸ばされている。これも、彼がやったのだろうか。
ぴんとした白いテーブルクロスの上に、パンの皿とドレッシングを下ろす。トースト、サラダ、ドレッシング、コーヒー。型にはめたような、美味しそうな朝食の光景が出来上がった。
朝の明るい光、白いテーブルクロスが眩しい。きらきらと光を受け水気を光らせるサラダ、湯気を立てるコーヒー。トーストのバターの匂い。
「美味しそうだな」
その食卓を前に、窓を背にして微笑む導師。カーテンの白、彼の服の赤。コントラスト。
「はい」
眩しくて、目を細める。
二人きりの食卓は静かになるだろうと綺礼は考えていたが、そうはならなかった。
「綺礼はトーストが上手だな」
「時臣師も、トースターは使えるでしょう」
「使えるが…駄目だね。すぐに焦げてしまうんだ」
「焦げる、ですか?温度の調整が間違っているのではないですか」
「温度?ううん、よくわからないな。今度教えてくれないだろうか、」
「私で宜しければ」
「ありがとう、助かるよ綺礼」
妻や娘がいる前では、彼らの見本となるべく、食器の音はたてず、背筋を伸ばして座り、口にものが入っている時に喋らず、テーブルマナーを心がけて振る舞う時臣は、綺礼と二人きりだからと大分その優雅さを崩していた。片手でトーストを持ったままではドレッシングの蓋を開けられないと、トーストを口に咥えて両手を空けるのを見た時には、さすがに綺礼もぽかんとしてしまった。しかし、時臣自身には敢えて普段と違うように振舞っているという自覚はないらしい。その仕草は、自然に見えた。
つつがなく、朝食の時間は進んでいく。
「………ああ、そうでした、時臣師」
「うん、何だい?」
うっかり触ってしまって指についたバターを舐めとる、という姿を晒している時臣に、綺礼は話しかけた。
「先程のオーブンの件なのですが」
「ああ………」
とたんに、その眉間に皺が寄る。
「…買い換えないとね。いや、その前に掃除か。随分と壁が黒くなってしまったからね…」
「いえ、掃除ならば明日誰かに任せれば良いでしょう。…それより」
「ん?」
「師は、なぜオーブンなど使われたのです?貴方が、あれに用事があるとは思えないのですが」
時臣が、少し首を傾げたまま固まる。
綺礼も同じ角度に首を傾げ、答えを待った。
「………」
「………」
「………………」
「………………」
「…………………………………ああ!いや、少し、使ってみたくなってね!」
「そんな理由で貴方があれに手を出すとは思えませんが」
すごく長い沈黙の挙句、視線をあちこちに走らせ、やっと言い訳を思いついたとばかりに発せられた言葉を冷たく切り払う。
時臣の機械嫌いは半端なものではないのだ。そんなちょっとした思いつきでオーブンなどという大掛かりなものに触れるとは思えない。良くて、テレビかラジオだろう。あれらが現代社会では便利なものらしいということくらいは、知っているだろうから。
綺礼の冷たさに、あーとかうーとか声を漏らしながら、時臣はまた視線をうろつかせる。答えを待ちながら、綺礼は思い出す言葉があった。
「…そういえば、料理をしていたと仰っていましたね」
それは、今日最初の会話だったはずだ。
爆発音に綺礼が飛び起きて、煤まみれの時臣と哀れなオーブンを見つけ、その理由を問いただした時の。
「何を作ろうとしていたのですか」
「う」
「こちらを向いてください」
びくり、と肩を弾ませて、時臣はさらに視線を逸らす。冷や汗がたらりと頬に流れるのが見えた。
「ええと、その、………トーストを」
「トーストならトースターで焼きますよね」
「コーヒーを」
「先程出して下さったコーヒーは、こちらのコーヒーメーカーでお淹れされたと思うのですが」
言い訳もだんだんと苦しくなる。
綺礼は意外に思った。この導師がこんなにも必死に嘘をつこうとしている姿など、初めて見た。いったい何が、彼をこんなにも必死にさせているのか───興味が、沸く。
ここまで問い詰めても態度が変わらないのならば、攻め方を変えるしかない。綺礼は、別の方向から攻めることにする。
「…そんなに、私に言いたくないようなことをしていたのですか」
「…………っ」
いわゆる、泣き落とし、というものだ。
眉尻を下げ、少しうつむき、声をワントーン落とす。涙の一つも故意に浮かべられれば良かったのだが、あいにくそういう器用な芸当は綺礼には出来ない。だが、身内に甘すぎる導師にとっては十分すぎる演技だったようだった。
「いや、その。そういうわけではないんだ」
「では、どういうわけなのですか。教えてくださらないのは、私が至らないせいですか」
「そんなわけないだろう!違うんだよ」
何が至らなければオーブンを使った理由を教えない理由になるのだろうか。めったに感情を見せない弟子が今にも泣きそうという状況を前に、時臣は会話の正当性すら認識できなくなっているらしい。全ては綺礼の思惑通りだというのに。
「ああ、もう、わかったよ。言えばいいのだろう」
それから2,3どうでもいい対話を重ね、折れたのは時臣だった。
教えてくださるのですか、と言えば、うん、と少し不貞腐れたような答え。
「………ケーキを、作ろうと思ったんだ」
「ケーキ、ですか?」
綺礼の脳裏をよぎるのは、時臣が好む優雅なティタイムであった。午後の3時頃、仕事を中断して家族や弟子と取るその時間を、彼が大切にしていることを知っている。その時間を楽しむために、とっておきの紅茶葉を取り寄せたり、妻や娘が好むスイーツを用意したりしていることも。そして、よく選ばれるスイーツが、彼の妻が特に好むフルーツケーキなのだ。生地にドライフルーツを混ぜて焼いたそれが、最初に思い浮かんだのである。
そんなことを綺礼が考えているのを知ってか知らずか、時臣は、いや、お茶の時間に食べるものではないんだよ、と言った。
「こう…もっと豪華な。クリームやフルーツの乗っている」
「ああ、デコレーションケーキですか」
「そう。そういうものが作りたかったんだよ」
「祝いの席の…例えば、バースデイケーキのような?」
それは、綺礼にすれば会話のキャッチボールの中の一つの言葉だったにすぎない。
だが、時臣を驚かせるには十分な言葉だった。
「綺礼、きみ…。…………わかってて、私に言わせようとしていたのかい」
「え?」
「人が悪いなぁ………」
一人で納得したようにうなずき、苦笑する時臣に、綺礼はついて行けない。首をかしげるも、時臣の中では既に綺礼は、全て知っていてその上で自分を試そうとした意地悪な人、という風になっているようだった。
「うっかり全員に暇を出してしまったし、タイミング悪く葵もいないし、それならば私がやるしかないだろう?」
何の話なのか。置いていかれた綺礼は言葉をはさもうとするが、時臣はそれを察せず続ける。
「これでもね、がんばろうと思ったんだよ。本だって、朝電話して葵に借りたのだし」
「本、ですか」
「そうさ。粉を分量通り測ってね、混ぜて、オーブンで焼くんだ」
測って混ぜて、と、ジェスチャーをつけながら時臣が言う。
「だけど、まさか爆発するなんてな…。おかげで君にバレてしまった」
「私にバレるとまずいことでも?」
「まずいわけではないがね。こういうのは普通、サプライズのためにこっそりとやるだろう?」
ほら案の定君はこんなに落ち着いているじゃないか、と時臣は悲しそうな顔ををする。
「サプライズ…?」
「もうバレてしまったのだから、サプライズにはならないだろうが。君の」
君の誕生日を祝うケーキなんて。と。
時臣はそう言った。
時臣は、その企みがバレてしまった悲しさを嘆いている。せっかくケーキを作って祝おうとしていたのに、と。君の欲しいものを知らないから、せめてケーキはと。しかし綺礼にはその言葉は届いていなかった。その直前の衝撃が尾を引いていたので。
君の誕生日を祝うケーキ、と時臣は言った。「君」なんて言葉は目の前にいる相手に対して使われる二人称で、今現在時臣の前にいるのは綺礼ただ一人。であるなら、綺礼に向けられた言葉なのだろう、君の誕生日を祝う、というのは。綺礼に向けた言葉なのだ。
「しかし、やはり慣れないことは難しいね。今度から私も───」
「師、時臣師」
未だ喋り続けていた時臣の声を遮る。食卓さえなければ、飛び出していただろう。
「今のは、今のは本当ですか」
「今の?少しは私も料理を出来るようになったほうがいいかという話かい?」
「違います、その前の」
会話がもどかしい。確認したい。
「ああ、君の誕生日のケーキの話かな」
さらりと、何事でもないかのように、時臣は言った。
綺礼の誕生日。12月28日。
確かにそれは、今日だった。
「何だ、当てずっぽうで言ったのかい?最初からバレていた上で問い詰められていると思ったのだが」
ぽかんとした様子の綺礼に、少々毒気が抜かれたような表情で、時臣が言った。
「………ていました」
「うん?」
「忘れて、いました」
自分ですら忘れていたそれを、時臣は覚えていたのだ。覚えていて、祝おうとしてくれたのだ。慣れぬ事をしてまで。
「すみません、でした」
ぽつりと、こぼれるような言葉に、時臣は苦笑する。
「何で謝るんだい。君は何も悪いことをしていないじゃないか」
「貴方の心を、貴方を、勘違いしていました」
「君の中の私が一体どんな存在なのか気になる発言だね」
くすくすと時臣が笑う。綺礼は、萎縮していた。
「でも、実際私は何も出来ていやしないんだからね。ケーキを焼くどころかオーブンを壊し、朝食の支度だって君に任せっぱなしだ」
「ですが、貴方は私を祝おうとしてくださいました」
「それなら、なおさら謝るところではないだろう。まあ、当人が言うことでもないが、もう少しふさわしい言葉があるのではないかな」
綺礼は少し考えて、ありがとうございます、と言った。
それに時臣は、どういたしまして、と返した。
「私には、ケーキを焼くのはどうやら敷居が高いようだからね。後で、二人で買いに行こう」
「はい」
「どんなケーキがいいかな。昔凛のケーキを買った時みたいに、名前を入れてくれるサービスはあるのかな」
「…それは、さすがに恥ずかしいです」
「ふふ。それから、もうバレてしまったから聞くが、君は何か欲しい物があるのかな」
「それを、望んでも良いのですか?」
「言ってごらん。…まあ、余り入手の難しい品はすぐには用意できないだろうけど」
「それならば、師よ。一つだけ」
「なんだい、綺礼?」
「今日は、使用人も、それから奥方もご子女も、誰もおらず、屋敷内は寂しいので」
「ああ」
「………今日は一日ずっと、お側において頂けますか」
「そんなこと!」
こんな特別な日じゃなくたっていつだって、私の方から望みたいくらいだよ、と時臣は言った。
「だから、そうだな、もう少し、高い望みを言ってごらん」
「それならば、師よ」
「なんだい」
「これからもずっと。お側において頂けますか」
「それだって、全然特別なことじゃないじゃないか」
でも、そうだな、と時臣は言う。
「それが、君の一番欲しいものならば。君が、そんな顔をしてまで欲しいものだというのなら、それをプレゼントにさせてくれるかい」
これからも、ずっと共に。
握手でも誘うかのように伸ばされた時臣の右手を両手で握りしめ、綺礼はもう一度ありがとうございますと言った。
握りしめて唇を落とす、赤い印の浮いたその手の甲は暖かく。
その暖かさに、永遠を見た、ような気がした。
2012綺礼誕生日に。
仲良師弟が好きなんです…仕方ないんです…
あと綺礼の料理の腕に夢を見ている。
仲良師弟が好きなんです…仕方ないんです…
あと綺礼の料理の腕に夢を見ている。