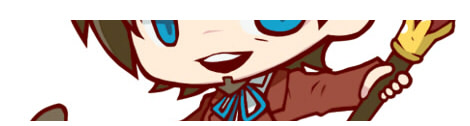
時臣師が靴擦れになる話
「あ…」小さく呟いて、時臣が足を止める。
綺礼は数歩先を行って、彼の姿が完全に自分の肩に隠れたところでやっと振り返った。
「………」
「どうかしましたか」
「いや…うん」
時臣は立ち止まって首を傾げ、何やらしきりに足元を見ている。問いかけても、どこか不明瞭な返事が帰ってくるだけで。もう一度どうしましたかと問いかけてやっと、時臣は綺礼を見た。
「どうもね、…やっぱり、靴が足に合わなかったようだ」
困ったように眉をハの字にし、上目遣い。怒られるのを覚悟したような表情だった。
というのも、先程までいた店で一悶着あったからである。
デザインが気に入って時臣が数週間前に注文したその靴は、オーダーメイドで作ったはずなのに僅かに小さく出来てしまった。文句を言って交換すればいいものを、だがこの貴族のくせに少々けちくさい男は、まあ履けないわけじゃないから、と受け取ってしまったのだった。履いているうちに馴染むだろう、と。
そして、家から履いてきた靴を一旦靴屋に預けて新しい靴を履き、綺礼を供にして足慣らしにと近場を散歩してみることにしたのである。
…が。やはり、こうなってしまった。
予想通りの展開に、綺礼は怒る気もなく嘆息する。
人通りの多くはない道ではあるが、少ない、というわけでもない。長く立ち止まっていれば通行人の邪魔になってしまうだろう。
「歩き辛いですか」
「うーん、少し、歩き辛いね」
「手をお貸ししましょう」
「ありがとう、助かるよ」
時臣は嬉しそうに笑ってこちらへ手を差し出してきた。が、一歩も動こうとしない彼にもう一つ嘆息して、綺礼は自分から歩み寄ってその手を取ってやった。
綺礼の筋肉の付いた太い腕に、時臣のしなやかな腕が巻き付く。
ぐ、と掴まれた綺礼の左腕に体重がかかる。もちろん時臣は全体重をかけてきているわけではないが、遠慮なく頼られればさすがに重たい。綺礼の鍛えた体にとっては、苦痛でもなんでもないのだが。
そんなことよりも、頭が近かった。視界の少し下、肩の辺りで頼りなさげに揺れる髪はきっと冷たいだろう。暖かければ汗に乗ってその整髪料の香りが届くのだろうが、残念ながら乾いた風にそれを期待することはできなそうだった。
そんな風に寄り添って二人で二三歩歩いたところで、時臣はまた困ったように綺礼を見上げた。家族にすら絶対に見せない、弱った顔だ。
「いかがされました」
「…靴ずれになってしまったようなんだ」
見れば、時臣は右足を靴の中で不自然に持ち上げているようである。もう一度数歩進もうとすれば、平常を装ってはいるものの、僅かにびっこを引いているのがわかった。
「治癒しますか」
「…こんな町中では、やめておいた方が懸命だろうね」
綺礼の言葉に、時臣は小さく首を振る。
「優雅じゃない………」
はぁ、と溜息をつく時臣に、自業自得ですよと思いつつも、綺礼は別の言葉をかけた。
「先ほど見かけたのですが、近くに薬局が有ります。絆創膏でも買いましょうか」
「ほう」
時臣の顔がわかりやすく輝く。
「それはいい考えだね綺礼。すぐに行こう」
「そこまで歩けますか」
「ああ、少し痛いが…」
今度煌めいたのは綺礼の目だった。
「それなら私がお連れしましょう。おんぶと抱っこはどちらがよろしいですか。抱っこもコアラスタイルと姫抱きがありますが」
「急に饒舌だね君。というかコアラスタイルというのは初めて聞いたよ」
「駅弁スタイル、と言ったほうが宜しかったでしょうか」
人が変わったかのようにスラスラしゃべり始める弟子に、話の内容が理解できないながらも何かからかわれているらしいことに気付き、時臣は嘆息した。
「私はここで待っているよ。綺礼、君に頼めるかな」
綺礼の腕を離し、ふらりと歩き出す。道端には都合よくベンチがあり、彼はその端の方に腰掛けた。指を組んで膝の上に置き、すっと背筋を伸ばして少し首を傾ける。それだけで古ぼけたベンチもアンティークのように見えた。
昼間の強い日差しにきらきら、細く柔らかな髪が光り、長めの前髪の下、影になった青い瞳が綺礼を見上げる。
「…わかりました。お任せを、導師」
「ああ。頼んだよ、綺礼」
ふ、と時臣の細めた瞳が眩しくて、綺礼は、何だかんだ考えたり言ったりしつつも自分が師には逆らえないのだと知る。
彼のことが、好きなので。
靴ずれ専用という何やらピンポイントな用途の絆創膏があったのでそれを購入し、先程の場所へと綺礼は戻った。先程と同じ場所に座っている時臣の姿が見える。
「───あ」
行き交う人々を眺めていた時臣が綺礼に気づき、顔をあげる。綺礼は、足を早めて彼に近づいた。
「お帰り。どうだったかい、綺礼?」
「はい、こちらを購入してきました」
青いパッケージのそれを薬局の袋から取り出すと、時臣は満足したように頷いた。
「ありがとう。料金は後で払うよ」
そのまま差し出してくる時臣の手からパッケージを逃れさせる。目測を誤ったかと再度伸ばされる手からも、すいっと遠ざけた。2回受け取るのに失敗して、やっと綺礼が自分の届かないところへ動かしているのだと気づいた時臣が睨みつけてきた。
「………何の真似だね、綺礼」
「いえ」
むっとした表情の師を見下ろしながら手袋を外し、絆創膏のパッケージを開ける。一枚につながったのを切り離し、一回分を残してしまい直した。パッケージも薬局の袋に戻し、一枚だけ手元に残ったそれの中身を取り出して時臣に示す。時臣が手を伸ばしてくるのを躱しながら、ベンチに座る彼の前に膝をついた。先ほどと一転、綺礼が時臣を見上げる形になる。
「かなり貼り辛いように思えますので、僭越ながら、私にやらせていただければと」
ご自分で綺麗に貼れるという自信がおありなのでしたらお任せしますが、と、時臣を気遣うような内容でありながら、綺礼の口調は揶揄するようなものに聞こえた。
しかし、絆創膏という特性上、下手に扱えばぐちゃぐちゃにくっついてしまう。それを、かかとという自分の目では見辛い場所に貼るというのだ。時臣は不器用というわけではないが、上手く貼れる自信があるわけでもない。綺礼がやってくれるというのなら、断る理由はないのだ。
「………ああ、頼むよ」
「それでは、足を」
ああ、と頷いた時臣が靴を脱ごうとすると、綺礼が手で制してきた。何かと思えば動きを止めれば、綺礼は上げていた手を伸ばし、足首を持って時臣の右足を持ち上げた。そのままそっと靴が脱がされる。
「………」
酷く丁寧な手つきに、妙に緊張して落ち着かない。
「導師」
「っ、うん?」
「靴下に、血が。少々痛むかもしれませんが、堪えてくださいね」
別にそのくらい、と言い返そうとするより、綺礼の動作のほうが早かった。左手で時臣の右足首を支えたまま、左手でふくらはぎまである紺色の靴下を巻き取るように外される。かかとを通過するときだけ、靴下と足の間に指を入れ、浮かせるように。靴と靴下に隠されていた素肌にひんやりとした綺礼の指が、触れる。その冷たさに慣れるよりも先に、ぴりっとした痛みが走った。出血が靴下に滲み乾いたのが、綺礼の指によって剥がされたようだった。
「……っ」
「…痛みますか」
「………いや、君の指が余りに冷たいのでね」
堪えたつもりだったが綺礼にはバレてしまったらしい。そんな言い訳をすると、綺礼が口の端を歪めた。どうやら笑っているらしい、と時臣は思う。基本的に表情といえば無表情の一つしか持っていない綺礼なので、そう言った小さな変化で機嫌を読み取れるのだ。
綺礼は一瞬でその笑みを消すと、時臣の足先から靴下を取り去った。遠坂の家が洋風であるが故に、ほぼ常に隠されている素肌が綺礼の前に晒される。青白い皮膚とそこに浮く血管。長めの足指の先には、手指と同じ桜色の整えられた爪がある。綺礼は、右手で足首を捧げ持ったまま靴下を立てた膝の上に置いて、空いた指先でその爪をそっと撫ぜる。ぴく、と足指が揺れた。
「…綺礼」
「はい」
「……、………寒いから、早くやってくれないかな」
恐らくは別のことを言おうとしたのだろう。だがその言葉を飲み込み、時臣は綺礼から視線を逸らしてそんなことを言った。綺礼はまた口の端を歪めるが、目をそらしている時臣は気づかない。
そっと足首を持ち上げかかとを覗く。想像通り、そこには皮が剥け真っ赤に染まった傷口があった。剥けてしまった皮は靴下にへばりついて取れてしまったようで、傷口は妙につるりとしている。しかし、見ているうちにもじくじくと体液と血液が染み出しているのだ。綺礼は、それをしばらく見て、それから持っていた時臣の右足を少し高く上げた。
「うわっ」
バランスを崩した時臣が慌ててベンチの背もたれに掴まる。
そんな時臣を尻目に、綺礼は持ち上げた右足に顔を近づけ、傷口に舌を押し付けた。
「きっ、綺礼!?」
痛みよりも、衝撃が勝る。時臣は足を引っ込めようとするも、足首をしっかりと掴まれていて動けなかった。それどころか、抵抗したことが気に触ったのか綺礼の舌は傷口を抉るように動き、びりっとした鈍い痛みが走る。
「………消毒です」
「しょ、しょうどくって綺礼、だけど君がそんなことをする必要は」
「消毒液など買っておりませんので」
もう一度ぺろりと舐め、つぅっと足の甲まで舌を走らせる。そのまま小さく跡を残そうとした時、時臣が反撃に出た。
「っ………」
「もっ、もういいだろう!そこの消毒は必要ない!」
蹴り上げる力は弱々しいものではあったが、油断していた綺礼はバランスを崩しそうになったのをなんとか耐え、時臣の顔を見上げる。綺礼を睨みつける眼光こそ強いものの、時臣の頬は怒りとは違う赤に完全に染まっていた。その表情を見て、綺礼は満足する。
「…失礼いたしました」
ぺこりと頭を下げ、形ばかりの謝罪。時臣が何か口を挟む前に、綺礼は絆創膏の裏側の紙を剥がしてパッドの部分を傷口にあてがった。丸い形をしたテープ部分をかかとの形に沿って貼り付けていく。面積ばかり大きな傷口は、すぐに絆創膏の下に隠れた。しっかりと貼り付いたことを指先で確認すると、元の通りに靴下と靴を履かせ直す。ずっと掴みっ放しだった右足を地面に下ろすと、ようやく力が抜ける。
「左足を」
「………ああ」
なにか言う気もなくしたのか、時臣は投げやり気味にもう片方の足を差し出してきた。
もう一度同じ手順。傷の『消毒』まで同じようにやれば同じように顎を蹴りあげられたが、特に問題もなく時臣の両かかとには適切な処置が行われた。
「………ありがとう」
「いいえ、これしきの事」
随分と不貞腐れた礼の言葉ではあったが、綺礼は慇懃な態度で言葉を返した。
「しかし、残念だな」
靴屋に戻り元の靴に履き替え、帰路についた時臣が言葉をこぼした。
「何がですか」
「あのデザインはかなり気に入っていたんだ。だが、あのサイズではねえ…」
「ですが、作りなおすのでしょう」
かかとに絆創膏を貼って靴屋に戻った時臣は、やはりもう少し大きいほうが都合がいいようだと靴屋の主人に言ったのだ。遠まわしに作り直しを要求された店側は、しかしサイズ間違いが自分たちの手違いであるため丁重にわび、料金は要りませんとまで言った。時臣はそんな言葉を笑って許して再度の採寸に応じ、店はお得意様を一人失うことを避けられた。
「ああ、今度こそ足に合うように作ってもらえるといいのだが」
自然、視線は足元に向かう。
「まだ痛みますか」
「少しね」
「手をお貸ししましょうか」
「それには及ばないよ」
でもありがとう、君がいて助かった、と時臣は言った。
靴ずれ程度で歩けなくなるとは思わないし、目の前のこの師が、例えば一人だったり家族か仕事の相手等といるときに、先程の自分に対するような態度を取るとは思えない、と綺礼は思う。
「早く、あの靴ができるといいですね」
「そうだね。そうしたら、また取りに来ないと。その時も付き合ってくれるかい」
「貴方が望むのならば、喜んで」
時臣はああ、と答えて微笑んだ。
「───その時はまた、貴方の足に絆創膏を貼る栄誉を頂けることを、楽しみにしていますよ」
「…君は何を馬鹿なことを言っているのだね。あの靴屋が同じ過ちを繰り返すというのかい」
呆れたような口調で言う時臣は、綺礼の心をわかっていないらしい。
それはそれでいい、と、綺礼は、少し早足になった時臣の隣につくべく、歩幅を大きくして歩みだした。
なんとなくくつずれ話
でもお貴族様のオーダーメイドシューズとか
よくわかんなかったので適当になってしまったよ…
そういうのはちゃんと調べないと駄目ね
でもお貴族様のオーダーメイドシューズとか
よくわかんなかったので適当になってしまったよ…
そういうのはちゃんと調べないと駄目ね