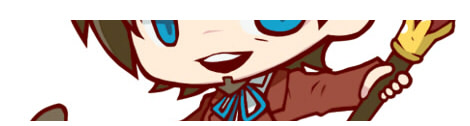
その日は珍しく、綺礼の部屋に朝早くから訪れるものがあった。時臣である。微妙に空気の読めない彼の来訪を受け、綺礼は寝間着のまま、身支度の手を一旦止めて彼を出迎えなければならなかった。
「おはよう、綺礼。今良いかね?」
何故完全に部屋に入ってから問うのか。こうした小さなところにも、彼の癖であるうっかりが覗く。頷くしかない綺礼の心中など察することもなく、時臣はにこりと微笑んだ。
彼は既に普段の服に着替えている。さすがに家の中ともあってジャケットまで着込んでいないが、それにしてもシャツ一枚という動きやすい格好をしていることに、少々嫌な予感がよぎる。
「…何でしょうか」
警戒する綺礼の様子に気づかず、時臣は平静なままで答えた。
「オーブンの使い方を教えて欲しいんだ」
「………オーブン?」
全く想像もしていなかった言葉に、綺礼は思わず首を傾げた。何故か時臣までつられて同じ角度に首を傾げる。
オーブンと言われて思い出すのは昨年末。時臣が誰にも内緒でケーキを焼こうとし失敗して爆発させた事件である。あれに懲りて、あれ以来時臣はキッチンには近づかないようになっていたと思っていたのだが。
「…何を焼こうというのです」
「いや、ケーキをね」
念の為に聞けば予想通りの答え。ああ彼は懲りていなかった!昨年末の忙しい時期に買い換えられたばかりの新品のオーブンは、壊してしまったからという負い目からか、時臣は葵に進められるがままにかなり高級なものを買ったようである。なのに、あの銀色のぴかぴかした巨大な機械もまた、彼の手によって爆発させられてしまうのだろうか。それも、ケーキを焼こうとしたという同じ理由で。なんという悲劇だ!
「…綺礼、今何か失礼なことを考えているだろう」
「いえ、特には」
胡乱な目で睨みつけてきた時臣から綺礼は視線を逸らす。
「…………まあ、いいだろう」
しばらくその状態が続くも、先に折れたのは時臣だった。折れるも何も、最初から折るべき主張も何もなかったわけだが。
「それで、綺礼。私にオーブンを教えてくれるのかね?」
嫌、ということもできるはずだった。
だが、あの日の煤に塗れた可哀想なオーブンのことを考えてしまえば、新しいあのオーブンが同じ目に合うことを想像してしまい、拒みきれない。それに、とふと思う。
「今度は、何のためのケーキです?」
あの日は綺礼の誕生日を祝うために、という理由だったはずだ。ならば今日は?娘二人の誕生日は先月今月ともう終わっているし、妻である葵の誕生日は半年も先。時臣自身の誕生日にだって、まだ時はあるはずだ。
「何、バレンタインには凛と桜、葵からチョコレートを貰ったからね。そのお返しをな」
「───なるほど。」
つまり、ホワイトデーだ。愛する娘と妻のために、今度はその手を煩わせてオーブンを爆発──いや、ケーキを焼こうというのか。理解をした綺礼が時臣に頷こうとした、その瞬間。
「ああ、そうだ、綺礼」
「…なんでしょうか」
「君も、三人からチョコレートをもらっていたね。ならば、君もお返しを用意せねばなるまい」
だから君は私を手伝うしかないな、と、時臣はにっこり微笑む。
「キッチンはもう取ってあるんだ。三人とも買い物に出ていて夕方まで帰ってこないし、だから、綺礼」
綺礼は心の中で両手を上げ、はい、わかりました、と答えた。
「…」
「………?」
「…………とりあえず着替えたいので、先に行っていて頂きますか」
「あっ、す、すまない!」
そしてようやく、綺礼は寝間着に別れを告げることが出来て、そして───
「卵白と砂糖を混ぜてメレンゲを作っています」
「メレンゲ?ケーキを作るのではないのかい?」
「これくらいにしておいてから小麦粉と混ぜると、スポンジがふわふわになるのですよ」
「へえ、そうなのか」
魔術師のキッチンである。電動ハンドミキサーなんてもちろんないので、綺礼は上腕二頭筋から発揮する力に任せてヘラを回していた。ボウルの中には泡だった卵白。まだ少し、硬さが足りない。時臣は、興味津々という視線で手元を覗きこんでいた。暇なのだろうか。やろうと誘ってきたのは彼自身なのに、どうやら指示を待っているようだった。
「………師よ、申し訳ありませんが、他の準備をお願い出来ますか」
「ああ、わかった。任せてくれ」
自信ありげに微笑んで力強く頷く時臣に、若干の不安を覚えないわけではなかったが。
だが綺礼のその不安に反し、時臣は、料理自体が苦手なわけではないようだった。
ボウルや皿などを用意し小麦粉を測る手つきは、少々危なげもあるものの、それは慣れない作業だからというだけで、別に不器用だというわけではない。時折耳にするメシマズの特徴である、突拍子のないようなものを混ぜることもないし、料理本のレシピから逸脱した手順をとるわけでもない。ごくごく基本に則った、悪く言えば面白みのない手つきである。
ただ、綺礼にとっては新鮮な光景ではあった。
アイボリーの清潔な色をしたエプロンは、時臣のものである。何かの折に妻とお揃いで誰かから贈られたようなのだが、彼がそれをつけているところは初めて見た。葵の、淡い桃色のエプロン姿は何度か見たことがあるのだが。
時臣は少し屈んで真剣な目で秤を睨みつけている。バターをあと10g用意したいらしい。少しナイフで取り分けては器に移し、真剣な目で秤を見つめていた。背をかがめたせいで突き出した腰にはエプロンのリボンが揺れている。
さらに、少し長めの後ろ毛を、青い紐で縛っているのも少々目の毒だった。いつもは晒されない項が、白い。
ちなみに綺礼はいつも通りの黒尽くめだった。特に、エプロンなどを持ってはいないので。
その時、ふいに時臣の肩が震えた。上がる声。
「あっ」
「どうかしましたか、時臣師」
「バターが41gになってしまった…」
本には、40gと書いてあったから、1gのオーバーだ。それくらい、と綺礼は思うが、料理に慣れていない上に完璧主義者である時臣には、どうやらかなりの絶望だったようだった。振り向いた表情は、眉が下がりとても情けない。
「…1gくらいならば、問題はありませんよ」
「そういうものなのかい…?」
「ええ。私はいつも麻婆豆腐を作る際、レシピの5倍は香辛料を入れておりますが、全く問題はありません」
「…あれとは、余り比べたくないかな」
せっかくの綺礼の慰めに引きつった笑みを返す時臣であった。
「……まあ、綺礼が言うのであれば、大丈夫なのかな」
「ええ、大丈夫でしょう」
良かった、と表情をゆるめ、時臣は41gになったバターの器を秤から下ろした。
■■■
綺礼の混ぜていた卵白がメレンゲ状になったので、時臣の測った小麦粉と混ぜる。鍋に入れて火にかけ溶かしたバターも合わせて、綺礼がまた上腕二頭筋に物を言わせてがっつりと混ぜあわせた。
切るようにさっくりと混ぜ合わされた生地は、だまもなく、とろりと丸い型に移された。
「…さて」
その、生地を流し込んだ型を眺めて、時臣が真剣な声を上げる。
「………ここからが、第二局面だ」
そんなに真剣になる必要があるのか、綺礼にはわからない。というより、ケーキの作成であるならば、生地づくりが一番大事だろう。もちろん焼き方も大事ではあるが、生地がしっかり出来ていなければどんなに上手に焼いた所でふっくらとはいかない。だが時臣にとっては、ケーキを焼くという目的よりも、オーブンを使うという手段のほうが重要なのであった。
「……………オーブン」
自らが3ヶ月ほど前に爆発させた場所には、新しく設置された大きな機械。既にあの時の煤やらゴミやらは残っていないが、サプライズを散らされたという憎さは残っている。
「…とりあえず、やってみましょうか」
「………ああ」
ごくり、と時臣は唾液を飲み込んだ。
そろそろと、何を示すのかよくわからないダイヤルに手を伸ばす。触れるか触れないか、というところで指を止めた。前は、中に生地を入れて何かのボタンを押した瞬間に爆発したのだ。今回も、どこで爆発するかわからない。何だか、既に熱気を発しているような気がするし。………熱気?
「すでに私が温めておきましたので、あとは中に入れるだけで大丈夫ですよ」
「…えっ」
■■■
結果として、時臣は今回もオーブン克服には至らなかった。出来る弟子が全ての準備をしてしまっていたので、本当に中に型に流し込んだ生地を入れるだけで終わってしまったのだ。
「………」
ここで覚えておけば、今年の綺礼の誕生日こそ祝ってあげる事ができるのに。少々、へそを曲げた時臣の前で、しかし綺礼は作業を止める気配を見せない。
「…何をやっているんだい?」
好奇心に負けた時臣は、また綺礼の手元を覗きこむことにした。
先ほどと同じように彼はボウルを抱え込んで、上腕二頭筋に力を込めて何かを混ぜているのである。
「ホイップクリームを作っています」
「クリーム…かい?あれ、それは買ってきていなかったかな」
時臣の記憶では、「ホイップ」と書かれたものが冷蔵庫に入っていたはずである。綺礼は、それを見逃してしまったのだろうか。
「…いえ、師よ。あれはそのままでは使えないのです」
「そうなのかい?」
「はい。あれはまだ液状なので、泡立てないとケーキに載せることはできないのです」
「へえ…そうなのか。一つ賢くなったよ」
ありがとう、と言うも、綺礼は特に表情を変えはしなかった。
ボウルの中にはふわりと泡立ったクリームができつつある。こんなに精悍な男が力強くかき混ぜて、出来るのがこんなにやさしい姿のものだ。ギャップに、思わず時臣はくすりと笑う。
「…何ですか?」
「いや、別に」
何だか綺礼が可愛く見えてね、などといえば彼が不機嫌になるのは目に見えているので、時臣は口をつぐんだ。
「…焼きあがるまでは、まだ時間はありそうだな。私はイチゴの用意をしておこう」
「時臣師、指を切らないようにお気をつけを」
「…君は、少し私を見くびりすぎじゃあないかな?」
無表情のまま力任せにクリームをかき回す綺礼を横目に睨みながら、冷蔵庫からイチゴを取り出す。旬の果物だけあって、大粒でみずみずしい色合いをしていた。
一つ一つ取り出しては、へたを落とし、3分にスライス。レシピの飾り付け例を眺めながら、いくつかは上に飾るために、丸のまま残しておく。すぐに指先が赤い果汁に塗れるが、ここで洗ったとして次の一つに包丁を入れればまた同じことになってしまうから、我慢をした。最後の一つのへたを取り終え、やっと手を流せる、と息をつく。
だが、洗う前に。
イチゴの果汁に濡れた指先をぺろりと舐めた。甘い。甘酸っぱい。とてつもなく美味しい。
「…綺礼」
「どうかしましたか」
「甘みと酸味のバランスが素晴らしいイチゴだったよ」
「…つまみ食いですか」
「違うさ、切っていたら指に果汁がついてしまったから、」
振り向くと、思ったよりも近い位置に綺礼がいて、少し驚く。
時臣が驚いている隙に、綺礼はその指先を、
「あ」
「本当だ、甘い、ですね」
ぱくり、と咥えてしまった。
指先をぬるりと滑る舌の感触、少々舌足らずなこもった声に、時臣の背筋が震える。
「き、綺礼。その指にはもうイチゴはついてないよ、私が舐めてしまったから」
「ならば、これは師の味ということですか。やはり、甘く私には感じます」
「っ、綺礼!!」
何かに耐え切れそうになくて、時臣は慌てて指を引き寄せる。一瞬つながる銀糸に幻想、綺礼を睨みつける視線に迫力は足らず。
くくっと喉の奥で笑いながら、綺礼は時臣に一歩近づく。反射的にか時臣は一歩下がるがシンクに邪魔されてそれ以上は下がれない。綺礼が、その頬に指を伸ばした時だった。
チン!
小気味いい音が響く。
それはオーブンが発した音だった。そろそろ焼き加減を確かめてくださいという、高機能オーブンの主張である。
機械ごときにいい雰囲気をぶち壊しにされた綺礼は舌打ちをし、反対に時臣は機械に助けられたことに感謝するのであった。
■■■
それからレシピに則って2,3の手順が発生したが、それらの行い方についても特に問題はなかったようだった。
数十分後、ミトンをはめた綺礼の手がオーブンから取り出したそれは、型から盛り上がるように膨らんで、砂糖とバターの良い匂いを辺りに漂わせる。きつね色の柔らかそうな丘。竹串で焼け具合を確かめれば、おどろくほどすんなりと刺さり、またすんなりと抜ける。中まで十分に火が通っているようだった。
焼きあがったスポンジを、シンクに引いた濡れ布巾の上に下ろす。ナイフを軽く入れれば簡単に型から外れ、その全身が姿を表した。
「──美味しそうだな」
「美味しそうですね」
時臣が思わず顔をほころばせ手を叩くと、珍しいことに綺礼も微笑んだ。二人、揃って大きく息を吸う。幸せな香りが肺に満ちた。
しばらく、そのまま置いておくのだとレシピには会った。濡れ布巾をかけて常温で熱を冷ますのがコツのようである。
その隙にと散らばった材料や皿を片付けることにする。綺礼は、自分がやると申し出たのだが、片付けまでが料理だからね、と時臣は、一端のコックのような答えをした。
二人でやれば効率よく行くもので、スポンジの粗熱がとれる頃にはほとんど、もう使わぬ物の片付けは済んでしまった。
「それでは、仕上げと行こうか」
「はい」
丸いケーキに綺礼が包丁を入れる。まるで黒鍵を操るような物騒な動きではあるが、スポンジは上下に美しく分割された。時臣はヘラを取り、上下を離したスポンジに先程綺礼が作ったクリームを挟んでいく。ヘラですくったクリームは調度良い硬さで、茶色のスポンジを白く彩った。
「ああ、それくらいに、導師」
「少なくないかな?」
「イチゴを乗せて、それからもう一度上に塗るのが良いかと」
「なるほど」
綺礼が、イチゴを菜箸でつまみ上げた。手で載せていくより綺麗に載せられるからである。無骨な指ではせっかく時臣が綺麗に塗りつけたクリームを潰してしまうかもしれないし、果汁が指に付けば洗わなければならない。最も、もしそんなことになったら時臣師に舐めて欲しいが、と綺礼は心の中で思うが、あくまで思うだけに留めておいた。
そんなことを妄想しているうちにも淀みなく綺礼の手は動き、器用な箸がまんべんなくイチゴを敷き詰めていく。その隙にと、時臣はイチゴとイチゴの間にクリームを落としていった。
「これくらいで、いいかな」
クリーム、イチゴ、クリーム。白と赤のコントラストを、黄金色のスポンジで上下から囲う。未完成のそれは、それでもケーキ以外の何者にも見えない。焼きたてのスポンジはいい匂いだし、イチゴからも甘い香りが立ち昇るし、もうすぐにでも手を出してしまいたい雰囲気が漂っていた。
「…時臣師」
「…………っ」
そんなに物欲しそうに見ていただろうか。綺礼に横目でじとっと見られて、慌てて時臣はケーキから視線を外した。
「あ、あとはどうすればよいのかな」
「周りにもクリームを塗りましょう。それから、これで」
綺礼が取り出したのは搾り出し袋だった。中には、先程間に挟んだのと同じクリームが入っている。
「飾りつけましょう」
「ああ、面白そうだね」
「私がクリームを塗りますので、時臣師にはこちらを」
時臣に絞り袋を差し出し、代わりに綺礼はボウルを受け取った。
「任せなさい」
やはり時臣は自信ありげに頷く。先程の材料を分量する時の様子を見れば、特に問題はないだろう。綺礼は頷き返し、ボウルの中のヘラを手にとった。
白いクリームをヘラで掬い上げ、スポンジの上に盛り、平らに伸ばす伸ばす。自慢の上腕二頭筋に力を込め過ぎないように、綺礼はクリームを塗りたくっていった。柔らかそうな黄金色が徐々に隠れ、平らな白に染め上げられていく。間に挟んだし絞り袋にも分けてあるというのに、少々量が多すぎた。まあ、余った分は後で別にコーヒーにでも入れればいいのだが。
そして綺礼がクリームを塗り終えると、時臣が場所を変わって絞り袋でケーキを彩っていった。塗りたくった白と同じ色であるはずなのに、複雑な星形の口金から溢れだした立体感のあるクリームの模様は、随分と平らなだけのケーキの印象を変えていく。上の平らな面には少し押し付けるようにして丸く、ツノを立てて。横の局面には、くねくねと曲線を描いて。初めてだろうに無難な手つきに、綺礼は安堵する。こういうところでうっかりをやらかすと思っていたからだ。そっと、顔を見る。
「…………」
真剣な横顔。いつもならば魔術書など小難しいものしか映さない碧眼には、きらりと光る搾り出し袋の口と、そこからあふれだす白いクリームだけを映している。慣れぬ手つき、少々緊張しているようにも見えた。珍しい姿である。常に優雅を心がける彼が、真剣な瞳で菓子作りをしているなど。綺礼は、自分がどんなに柔らかい顔をしているかにも気づかずに、その横顔を眺めていた。
ケーキの円周をぐるり、飾りつけ終えて、ようやく時臣はほっと息を吐いた。
「…どうだろうか」
「お見事です、師よ。とても素晴らしいケーキになりましたね」
「優雅かい?」
「………優雅です」
意味がわからぬままに肯定してみれば、それは良かった!と時臣のテンションはわかりやすく上がった。優雅なケーキとは一体どんなものなのだろう、という綺礼の疑問は解決されそうになさそうだ。
やはりクリームは作りすぎてしまったようだった。未だ時臣の手にある絞り袋の中にも、半ばまで白いモノが残っている。もし次があるならば間違わないようにしなければ、と綺礼は思った。
「あとは、上にイチゴを載せれば終わりかな」
「そうですね」
綺礼に肯定され高いテンションのまま、にこにこと時臣が片手でイチゴを取る。
「一緒にやろう、綺礼」
「わかりました」
綺礼も、イチゴを一つ手にとった。時臣の手で綺麗にへたの取られた大きな一粒。真っ赤でつややかで、断面から甘い香りが漂う。
へたの切り口を下に、時臣が上面を飾るように絞り出したクリームの上にイチゴを飾りつけていく。このへんでいいでしょうか、もう少し距離を開けたほうが良いのではないかな、そんな会話を交わしながら、ひとつ、ひとつ、白いクリームの上に鮮やかな赤が載せられていって。
とうとう最後の一粒が時臣の手によってその中央に配置され、それは完成する。
「…できたな」
「…できましたね」
ぴたりと手を止めて、二人でそれを見下ろす。
市販品ほどの出来…とは、残念ながら言えないだろう。時臣の飾りつけたクリームは綺麗に仕上がってはいるが、やはり慣れぬ雰囲気をどこか醸し出している。二人で載せたイチゴも、時臣のものはマシなのだが、綺礼のものは少々強く押し付けすぎてしまってクリームに埋もれているところがあった。
手作り感あふれるそれは、完璧な父たる遠坂時臣が作成したにしては余りにも、手作り感が溢れすぎていた。
だが。
「葵と、凛と、桜は、喜んでくれるだろうか?」
「もちろんでしょうね」
だからこそ。
と、綺礼は強く頷いてみせた。
時臣が、微笑んだ。
■■■■■■
「さて、あとはこれだが」
時臣が搾り出し袋を手に取る。綺礼は、ボウルに残った方にラップをかけ冷蔵庫にしまいながら振り返った。
「コーヒーにでも混ぜるのが良いのでは」
「ウィンナコーヒーか。美味しそうだね」
だが、それにしても少々量が多そうだ。クッキー等に載せて食べるしかないだろうか。それはそれで、娘たちが喜びそうではある。しかし、他に使い道は…そう考えた時に、時臣の目は、クリーム本体ではなく絞り袋を見た。
「…そうだ、綺礼」
「何でしょうか」
「左手を出して」
「…?」
意味がわからないながらも手のひらを差し出すと、こっちだよ、とひっくり返された。骨の浮いた大きな手の甲がさらされる。そして、あろうことか時臣は、その手の甲にクリームを絞り出し始めたのだ。
「時臣師、何を、」
「ああ、動かないでくれたまえ。もうちょっとで、………」
どこか楽しそうな顔をしながら時臣は、遠慮せずに綺礼の手の甲にクリームを出していく。柔らかいクリームが触れる感触がくすぐったくて、綺礼は眉をひそめた。
「…できた」
3分もかからなかっただろう。時臣が絞り袋を綺礼の手から離す。綺礼が目をやれば、そこに白く描かれた模様は、時臣の右手の甲にある赤い印と同じ形をしていた。
「ふふ、面白いかと思ってね」
「………………」
「本当は君のを描きたかったのだが、その、君の令呪の形は複雑だろう?だから、おそろいだよ」
三画の、令呪。
時臣から与えられた、まっしろの。
「時臣師」
「何だい?」
「これは、使えるのですか?」
「使いたいのかい?」
時臣の目が細められる。挑戦的な、挑発的な青。瞳孔が縦に細長く、綺礼を射抜く。
「…令呪を持って命じます」
綺礼は、時臣の問に答えぬままに口を開いた。
「時臣師、是非先程の続きを」
「先程?」
ちらりとイチゴの入っていたボウルに目を向ければ、意図が伝わったのか時臣の顔がぱっと赤くなる。
「重ねて命じます。消えるべき令呪は、貴方の舌で消しとって頂きたい」
少し目を見開いた時臣の前で、三度綺礼は口を開く。
「──重ねて命じます。奥方とご息女がご帰宅なされるまでの貴方の時間を、どうか私に」
沈黙。ぽかんとしたような顔をして固まっている時臣に、少々からかい過ぎたかと知る。
そう、からかってみただけなのだ。こんな無防備なことをする師に、こういう目に合うこともあるのだぞ、と。
だからその後に取った時臣の行動に、うろたえたのは綺礼の方だった。
「なッ!?」
差し出していた綺礼の左手を時臣がそっと取り、顔を近づけて、──舌を。
ぬるぬると這いまわる感触に、綺礼の全身が熱くなる。
「………了解した、マスター」
上げられた視線は青く、挑戦的な色を崩さないままに綺礼を映す。
呼名の新鮮さに、自分と彼との関係に、綺礼は夢中で手を伸ばした。
「時お」
「だがな、マスター」
抱きすくめようとした胸元は押されて離され、時臣の目が至近距離で綺礼を見上げる。その色が、いつの間にか変わっているように見えて、綺礼の熱が一気に冷めた。
「マスターとして、その令呪の使い方は失敗だ。一度に三画全てを使ってしまったら、その後の戦いに支障が出るだろう」
なんということだろう、青の瞳は、いつの間にか魔術師の色をしていたのである!
「それに、自分の欲求のために使うというのも減点だ。勝利を目指すため、状況を読んで使い給え」
「……はい」
「今回は遊びのようなものだからいいが、右手にあるそれを同じように使うなよ。いいかい、綺礼?」
声色もしっかりして、まるで魔術修行の時間のようだ。時臣側から仕掛けてきたことだというのに、これは酷い。これが人間のやることかよ、などという台詞が胸をめぐる。
「……………承知いたしました」
不貞腐れた綺礼の返事に、よろしい、と微笑んで。
時臣は。
「─────ッ!」
不意打ちのキスに、綺礼が驚いて目を見開く。
その視界いっぱいに、してやったりというような時臣の笑顔。
「しかし令呪で命じられては仕方がない」
さあ、続きをしようか、と言葉が耳に届いて。
次の瞬間綺礼から仕掛けたキスは、クリームの、甘い甘い味がした。
「おはよう、綺礼。今良いかね?」
何故完全に部屋に入ってから問うのか。こうした小さなところにも、彼の癖であるうっかりが覗く。頷くしかない綺礼の心中など察することもなく、時臣はにこりと微笑んだ。
彼は既に普段の服に着替えている。さすがに家の中ともあってジャケットまで着込んでいないが、それにしてもシャツ一枚という動きやすい格好をしていることに、少々嫌な予感がよぎる。
「…何でしょうか」
警戒する綺礼の様子に気づかず、時臣は平静なままで答えた。
「オーブンの使い方を教えて欲しいんだ」
「………オーブン?」
全く想像もしていなかった言葉に、綺礼は思わず首を傾げた。何故か時臣までつられて同じ角度に首を傾げる。
オーブンと言われて思い出すのは昨年末。時臣が誰にも内緒でケーキを焼こうとし失敗して爆発させた事件である。あれに懲りて、あれ以来時臣はキッチンには近づかないようになっていたと思っていたのだが。
「…何を焼こうというのです」
「いや、ケーキをね」
念の為に聞けば予想通りの答え。ああ彼は懲りていなかった!昨年末の忙しい時期に買い換えられたばかりの新品のオーブンは、壊してしまったからという負い目からか、時臣は葵に進められるがままにかなり高級なものを買ったようである。なのに、あの銀色のぴかぴかした巨大な機械もまた、彼の手によって爆発させられてしまうのだろうか。それも、ケーキを焼こうとしたという同じ理由で。なんという悲劇だ!
「…綺礼、今何か失礼なことを考えているだろう」
「いえ、特には」
胡乱な目で睨みつけてきた時臣から綺礼は視線を逸らす。
「…………まあ、いいだろう」
しばらくその状態が続くも、先に折れたのは時臣だった。折れるも何も、最初から折るべき主張も何もなかったわけだが。
「それで、綺礼。私にオーブンを教えてくれるのかね?」
嫌、ということもできるはずだった。
だが、あの日の煤に塗れた可哀想なオーブンのことを考えてしまえば、新しいあのオーブンが同じ目に合うことを想像してしまい、拒みきれない。それに、とふと思う。
「今度は、何のためのケーキです?」
あの日は綺礼の誕生日を祝うために、という理由だったはずだ。ならば今日は?娘二人の誕生日は先月今月ともう終わっているし、妻である葵の誕生日は半年も先。時臣自身の誕生日にだって、まだ時はあるはずだ。
「何、バレンタインには凛と桜、葵からチョコレートを貰ったからね。そのお返しをな」
「───なるほど。」
つまり、ホワイトデーだ。愛する娘と妻のために、今度はその手を煩わせてオーブンを爆発──いや、ケーキを焼こうというのか。理解をした綺礼が時臣に頷こうとした、その瞬間。
「ああ、そうだ、綺礼」
「…なんでしょうか」
「君も、三人からチョコレートをもらっていたね。ならば、君もお返しを用意せねばなるまい」
だから君は私を手伝うしかないな、と、時臣はにっこり微笑む。
「キッチンはもう取ってあるんだ。三人とも買い物に出ていて夕方まで帰ってこないし、だから、綺礼」
綺礼は心の中で両手を上げ、はい、わかりました、と答えた。
「…」
「………?」
「…………とりあえず着替えたいので、先に行っていて頂きますか」
「あっ、す、すまない!」
そしてようやく、綺礼は寝間着に別れを告げることが出来て、そして───
ホワイトデーだからケーキ作るよ!
「それは何をしているんだい?」「卵白と砂糖を混ぜてメレンゲを作っています」
「メレンゲ?ケーキを作るのではないのかい?」
「これくらいにしておいてから小麦粉と混ぜると、スポンジがふわふわになるのですよ」
「へえ、そうなのか」
魔術師のキッチンである。電動ハンドミキサーなんてもちろんないので、綺礼は上腕二頭筋から発揮する力に任せてヘラを回していた。ボウルの中には泡だった卵白。まだ少し、硬さが足りない。時臣は、興味津々という視線で手元を覗きこんでいた。暇なのだろうか。やろうと誘ってきたのは彼自身なのに、どうやら指示を待っているようだった。
「………師よ、申し訳ありませんが、他の準備をお願い出来ますか」
「ああ、わかった。任せてくれ」
自信ありげに微笑んで力強く頷く時臣に、若干の不安を覚えないわけではなかったが。
だが綺礼のその不安に反し、時臣は、料理自体が苦手なわけではないようだった。
ボウルや皿などを用意し小麦粉を測る手つきは、少々危なげもあるものの、それは慣れない作業だからというだけで、別に不器用だというわけではない。時折耳にするメシマズの特徴である、突拍子のないようなものを混ぜることもないし、料理本のレシピから逸脱した手順をとるわけでもない。ごくごく基本に則った、悪く言えば面白みのない手つきである。
ただ、綺礼にとっては新鮮な光景ではあった。
アイボリーの清潔な色をしたエプロンは、時臣のものである。何かの折に妻とお揃いで誰かから贈られたようなのだが、彼がそれをつけているところは初めて見た。葵の、淡い桃色のエプロン姿は何度か見たことがあるのだが。
時臣は少し屈んで真剣な目で秤を睨みつけている。バターをあと10g用意したいらしい。少しナイフで取り分けては器に移し、真剣な目で秤を見つめていた。背をかがめたせいで突き出した腰にはエプロンのリボンが揺れている。
さらに、少し長めの後ろ毛を、青い紐で縛っているのも少々目の毒だった。いつもは晒されない項が、白い。
ちなみに綺礼はいつも通りの黒尽くめだった。特に、エプロンなどを持ってはいないので。
その時、ふいに時臣の肩が震えた。上がる声。
「あっ」
「どうかしましたか、時臣師」
「バターが41gになってしまった…」
本には、40gと書いてあったから、1gのオーバーだ。それくらい、と綺礼は思うが、料理に慣れていない上に完璧主義者である時臣には、どうやらかなりの絶望だったようだった。振り向いた表情は、眉が下がりとても情けない。
「…1gくらいならば、問題はありませんよ」
「そういうものなのかい…?」
「ええ。私はいつも麻婆豆腐を作る際、レシピの5倍は香辛料を入れておりますが、全く問題はありません」
「…あれとは、余り比べたくないかな」
せっかくの綺礼の慰めに引きつった笑みを返す時臣であった。
「……まあ、綺礼が言うのであれば、大丈夫なのかな」
「ええ、大丈夫でしょう」
良かった、と表情をゆるめ、時臣は41gになったバターの器を秤から下ろした。
■■■
綺礼の混ぜていた卵白がメレンゲ状になったので、時臣の測った小麦粉と混ぜる。鍋に入れて火にかけ溶かしたバターも合わせて、綺礼がまた上腕二頭筋に物を言わせてがっつりと混ぜあわせた。
切るようにさっくりと混ぜ合わされた生地は、だまもなく、とろりと丸い型に移された。
「…さて」
その、生地を流し込んだ型を眺めて、時臣が真剣な声を上げる。
「………ここからが、第二局面だ」
そんなに真剣になる必要があるのか、綺礼にはわからない。というより、ケーキの作成であるならば、生地づくりが一番大事だろう。もちろん焼き方も大事ではあるが、生地がしっかり出来ていなければどんなに上手に焼いた所でふっくらとはいかない。だが時臣にとっては、ケーキを焼くという目的よりも、オーブンを使うという手段のほうが重要なのであった。
「……………オーブン」
自らが3ヶ月ほど前に爆発させた場所には、新しく設置された大きな機械。既にあの時の煤やらゴミやらは残っていないが、サプライズを散らされたという憎さは残っている。
「…とりあえず、やってみましょうか」
「………ああ」
ごくり、と時臣は唾液を飲み込んだ。
そろそろと、何を示すのかよくわからないダイヤルに手を伸ばす。触れるか触れないか、というところで指を止めた。前は、中に生地を入れて何かのボタンを押した瞬間に爆発したのだ。今回も、どこで爆発するかわからない。何だか、既に熱気を発しているような気がするし。………熱気?
「すでに私が温めておきましたので、あとは中に入れるだけで大丈夫ですよ」
「…えっ」
■■■
結果として、時臣は今回もオーブン克服には至らなかった。出来る弟子が全ての準備をしてしまっていたので、本当に中に型に流し込んだ生地を入れるだけで終わってしまったのだ。
「………」
ここで覚えておけば、今年の綺礼の誕生日こそ祝ってあげる事ができるのに。少々、へそを曲げた時臣の前で、しかし綺礼は作業を止める気配を見せない。
「…何をやっているんだい?」
好奇心に負けた時臣は、また綺礼の手元を覗きこむことにした。
先ほどと同じように彼はボウルを抱え込んで、上腕二頭筋に力を込めて何かを混ぜているのである。
「ホイップクリームを作っています」
「クリーム…かい?あれ、それは買ってきていなかったかな」
時臣の記憶では、「ホイップ」と書かれたものが冷蔵庫に入っていたはずである。綺礼は、それを見逃してしまったのだろうか。
「…いえ、師よ。あれはそのままでは使えないのです」
「そうなのかい?」
「はい。あれはまだ液状なので、泡立てないとケーキに載せることはできないのです」
「へえ…そうなのか。一つ賢くなったよ」
ありがとう、と言うも、綺礼は特に表情を変えはしなかった。
ボウルの中にはふわりと泡立ったクリームができつつある。こんなに精悍な男が力強くかき混ぜて、出来るのがこんなにやさしい姿のものだ。ギャップに、思わず時臣はくすりと笑う。
「…何ですか?」
「いや、別に」
何だか綺礼が可愛く見えてね、などといえば彼が不機嫌になるのは目に見えているので、時臣は口をつぐんだ。
「…焼きあがるまでは、まだ時間はありそうだな。私はイチゴの用意をしておこう」
「時臣師、指を切らないようにお気をつけを」
「…君は、少し私を見くびりすぎじゃあないかな?」
無表情のまま力任せにクリームをかき回す綺礼を横目に睨みながら、冷蔵庫からイチゴを取り出す。旬の果物だけあって、大粒でみずみずしい色合いをしていた。
一つ一つ取り出しては、へたを落とし、3分にスライス。レシピの飾り付け例を眺めながら、いくつかは上に飾るために、丸のまま残しておく。すぐに指先が赤い果汁に塗れるが、ここで洗ったとして次の一つに包丁を入れればまた同じことになってしまうから、我慢をした。最後の一つのへたを取り終え、やっと手を流せる、と息をつく。
だが、洗う前に。
イチゴの果汁に濡れた指先をぺろりと舐めた。甘い。甘酸っぱい。とてつもなく美味しい。
「…綺礼」
「どうかしましたか」
「甘みと酸味のバランスが素晴らしいイチゴだったよ」
「…つまみ食いですか」
「違うさ、切っていたら指に果汁がついてしまったから、」
振り向くと、思ったよりも近い位置に綺礼がいて、少し驚く。
時臣が驚いている隙に、綺礼はその指先を、
「あ」
「本当だ、甘い、ですね」
ぱくり、と咥えてしまった。
指先をぬるりと滑る舌の感触、少々舌足らずなこもった声に、時臣の背筋が震える。
「き、綺礼。その指にはもうイチゴはついてないよ、私が舐めてしまったから」
「ならば、これは師の味ということですか。やはり、甘く私には感じます」
「っ、綺礼!!」
何かに耐え切れそうになくて、時臣は慌てて指を引き寄せる。一瞬つながる銀糸に幻想、綺礼を睨みつける視線に迫力は足らず。
くくっと喉の奥で笑いながら、綺礼は時臣に一歩近づく。反射的にか時臣は一歩下がるがシンクに邪魔されてそれ以上は下がれない。綺礼が、その頬に指を伸ばした時だった。
チン!
小気味いい音が響く。
それはオーブンが発した音だった。そろそろ焼き加減を確かめてくださいという、高機能オーブンの主張である。
機械ごときにいい雰囲気をぶち壊しにされた綺礼は舌打ちをし、反対に時臣は機械に助けられたことに感謝するのであった。
■■■
それからレシピに則って2,3の手順が発生したが、それらの行い方についても特に問題はなかったようだった。
数十分後、ミトンをはめた綺礼の手がオーブンから取り出したそれは、型から盛り上がるように膨らんで、砂糖とバターの良い匂いを辺りに漂わせる。きつね色の柔らかそうな丘。竹串で焼け具合を確かめれば、おどろくほどすんなりと刺さり、またすんなりと抜ける。中まで十分に火が通っているようだった。
焼きあがったスポンジを、シンクに引いた濡れ布巾の上に下ろす。ナイフを軽く入れれば簡単に型から外れ、その全身が姿を表した。
「──美味しそうだな」
「美味しそうですね」
時臣が思わず顔をほころばせ手を叩くと、珍しいことに綺礼も微笑んだ。二人、揃って大きく息を吸う。幸せな香りが肺に満ちた。
しばらく、そのまま置いておくのだとレシピには会った。濡れ布巾をかけて常温で熱を冷ますのがコツのようである。
その隙にと散らばった材料や皿を片付けることにする。綺礼は、自分がやると申し出たのだが、片付けまでが料理だからね、と時臣は、一端のコックのような答えをした。
二人でやれば効率よく行くもので、スポンジの粗熱がとれる頃にはほとんど、もう使わぬ物の片付けは済んでしまった。
「それでは、仕上げと行こうか」
「はい」
丸いケーキに綺礼が包丁を入れる。まるで黒鍵を操るような物騒な動きではあるが、スポンジは上下に美しく分割された。時臣はヘラを取り、上下を離したスポンジに先程綺礼が作ったクリームを挟んでいく。ヘラですくったクリームは調度良い硬さで、茶色のスポンジを白く彩った。
「ああ、それくらいに、導師」
「少なくないかな?」
「イチゴを乗せて、それからもう一度上に塗るのが良いかと」
「なるほど」
綺礼が、イチゴを菜箸でつまみ上げた。手で載せていくより綺麗に載せられるからである。無骨な指ではせっかく時臣が綺麗に塗りつけたクリームを潰してしまうかもしれないし、果汁が指に付けば洗わなければならない。最も、もしそんなことになったら時臣師に舐めて欲しいが、と綺礼は心の中で思うが、あくまで思うだけに留めておいた。
そんなことを妄想しているうちにも淀みなく綺礼の手は動き、器用な箸がまんべんなくイチゴを敷き詰めていく。その隙にと、時臣はイチゴとイチゴの間にクリームを落としていった。
「これくらいで、いいかな」
クリーム、イチゴ、クリーム。白と赤のコントラストを、黄金色のスポンジで上下から囲う。未完成のそれは、それでもケーキ以外の何者にも見えない。焼きたてのスポンジはいい匂いだし、イチゴからも甘い香りが立ち昇るし、もうすぐにでも手を出してしまいたい雰囲気が漂っていた。
「…時臣師」
「…………っ」
そんなに物欲しそうに見ていただろうか。綺礼に横目でじとっと見られて、慌てて時臣はケーキから視線を外した。
「あ、あとはどうすればよいのかな」
「周りにもクリームを塗りましょう。それから、これで」
綺礼が取り出したのは搾り出し袋だった。中には、先程間に挟んだのと同じクリームが入っている。
「飾りつけましょう」
「ああ、面白そうだね」
「私がクリームを塗りますので、時臣師にはこちらを」
時臣に絞り袋を差し出し、代わりに綺礼はボウルを受け取った。
「任せなさい」
やはり時臣は自信ありげに頷く。先程の材料を分量する時の様子を見れば、特に問題はないだろう。綺礼は頷き返し、ボウルの中のヘラを手にとった。
白いクリームをヘラで掬い上げ、スポンジの上に盛り、平らに伸ばす伸ばす。自慢の上腕二頭筋に力を込め過ぎないように、綺礼はクリームを塗りたくっていった。柔らかそうな黄金色が徐々に隠れ、平らな白に染め上げられていく。間に挟んだし絞り袋にも分けてあるというのに、少々量が多すぎた。まあ、余った分は後で別にコーヒーにでも入れればいいのだが。
そして綺礼がクリームを塗り終えると、時臣が場所を変わって絞り袋でケーキを彩っていった。塗りたくった白と同じ色であるはずなのに、複雑な星形の口金から溢れだした立体感のあるクリームの模様は、随分と平らなだけのケーキの印象を変えていく。上の平らな面には少し押し付けるようにして丸く、ツノを立てて。横の局面には、くねくねと曲線を描いて。初めてだろうに無難な手つきに、綺礼は安堵する。こういうところでうっかりをやらかすと思っていたからだ。そっと、顔を見る。
「…………」
真剣な横顔。いつもならば魔術書など小難しいものしか映さない碧眼には、きらりと光る搾り出し袋の口と、そこからあふれだす白いクリームだけを映している。慣れぬ手つき、少々緊張しているようにも見えた。珍しい姿である。常に優雅を心がける彼が、真剣な瞳で菓子作りをしているなど。綺礼は、自分がどんなに柔らかい顔をしているかにも気づかずに、その横顔を眺めていた。
ケーキの円周をぐるり、飾りつけ終えて、ようやく時臣はほっと息を吐いた。
「…どうだろうか」
「お見事です、師よ。とても素晴らしいケーキになりましたね」
「優雅かい?」
「………優雅です」
意味がわからぬままに肯定してみれば、それは良かった!と時臣のテンションはわかりやすく上がった。優雅なケーキとは一体どんなものなのだろう、という綺礼の疑問は解決されそうになさそうだ。
やはりクリームは作りすぎてしまったようだった。未だ時臣の手にある絞り袋の中にも、半ばまで白いモノが残っている。もし次があるならば間違わないようにしなければ、と綺礼は思った。
「あとは、上にイチゴを載せれば終わりかな」
「そうですね」
綺礼に肯定され高いテンションのまま、にこにこと時臣が片手でイチゴを取る。
「一緒にやろう、綺礼」
「わかりました」
綺礼も、イチゴを一つ手にとった。時臣の手で綺麗にへたの取られた大きな一粒。真っ赤でつややかで、断面から甘い香りが漂う。
へたの切り口を下に、時臣が上面を飾るように絞り出したクリームの上にイチゴを飾りつけていく。このへんでいいでしょうか、もう少し距離を開けたほうが良いのではないかな、そんな会話を交わしながら、ひとつ、ひとつ、白いクリームの上に鮮やかな赤が載せられていって。
とうとう最後の一粒が時臣の手によってその中央に配置され、それは完成する。
「…できたな」
「…できましたね」
ぴたりと手を止めて、二人でそれを見下ろす。
市販品ほどの出来…とは、残念ながら言えないだろう。時臣の飾りつけたクリームは綺麗に仕上がってはいるが、やはり慣れぬ雰囲気をどこか醸し出している。二人で載せたイチゴも、時臣のものはマシなのだが、綺礼のものは少々強く押し付けすぎてしまってクリームに埋もれているところがあった。
手作り感あふれるそれは、完璧な父たる遠坂時臣が作成したにしては余りにも、手作り感が溢れすぎていた。
だが。
「葵と、凛と、桜は、喜んでくれるだろうか?」
「もちろんでしょうね」
だからこそ。
と、綺礼は強く頷いてみせた。
時臣が、微笑んだ。
■■■■■■
「さて、あとはこれだが」
時臣が搾り出し袋を手に取る。綺礼は、ボウルに残った方にラップをかけ冷蔵庫にしまいながら振り返った。
「コーヒーにでも混ぜるのが良いのでは」
「ウィンナコーヒーか。美味しそうだね」
だが、それにしても少々量が多そうだ。クッキー等に載せて食べるしかないだろうか。それはそれで、娘たちが喜びそうではある。しかし、他に使い道は…そう考えた時に、時臣の目は、クリーム本体ではなく絞り袋を見た。
「…そうだ、綺礼」
「何でしょうか」
「左手を出して」
「…?」
意味がわからないながらも手のひらを差し出すと、こっちだよ、とひっくり返された。骨の浮いた大きな手の甲がさらされる。そして、あろうことか時臣は、その手の甲にクリームを絞り出し始めたのだ。
「時臣師、何を、」
「ああ、動かないでくれたまえ。もうちょっとで、………」
どこか楽しそうな顔をしながら時臣は、遠慮せずに綺礼の手の甲にクリームを出していく。柔らかいクリームが触れる感触がくすぐったくて、綺礼は眉をひそめた。
「…できた」
3分もかからなかっただろう。時臣が絞り袋を綺礼の手から離す。綺礼が目をやれば、そこに白く描かれた模様は、時臣の右手の甲にある赤い印と同じ形をしていた。
「ふふ、面白いかと思ってね」
「………………」
「本当は君のを描きたかったのだが、その、君の令呪の形は複雑だろう?だから、おそろいだよ」
三画の、令呪。
時臣から与えられた、まっしろの。
「時臣師」
「何だい?」
「これは、使えるのですか?」
「使いたいのかい?」
時臣の目が細められる。挑戦的な、挑発的な青。瞳孔が縦に細長く、綺礼を射抜く。
「…令呪を持って命じます」
綺礼は、時臣の問に答えぬままに口を開いた。
「時臣師、是非先程の続きを」
「先程?」
ちらりとイチゴの入っていたボウルに目を向ければ、意図が伝わったのか時臣の顔がぱっと赤くなる。
「重ねて命じます。消えるべき令呪は、貴方の舌で消しとって頂きたい」
少し目を見開いた時臣の前で、三度綺礼は口を開く。
「──重ねて命じます。奥方とご息女がご帰宅なされるまでの貴方の時間を、どうか私に」
沈黙。ぽかんとしたような顔をして固まっている時臣に、少々からかい過ぎたかと知る。
そう、からかってみただけなのだ。こんな無防備なことをする師に、こういう目に合うこともあるのだぞ、と。
だからその後に取った時臣の行動に、うろたえたのは綺礼の方だった。
「なッ!?」
差し出していた綺礼の左手を時臣がそっと取り、顔を近づけて、──舌を。
ぬるぬると這いまわる感触に、綺礼の全身が熱くなる。
「………了解した、マスター」
上げられた視線は青く、挑戦的な色を崩さないままに綺礼を映す。
呼名の新鮮さに、自分と彼との関係に、綺礼は夢中で手を伸ばした。
「時お」
「だがな、マスター」
抱きすくめようとした胸元は押されて離され、時臣の目が至近距離で綺礼を見上げる。その色が、いつの間にか変わっているように見えて、綺礼の熱が一気に冷めた。
「マスターとして、その令呪の使い方は失敗だ。一度に三画全てを使ってしまったら、その後の戦いに支障が出るだろう」
なんということだろう、青の瞳は、いつの間にか魔術師の色をしていたのである!
「それに、自分の欲求のために使うというのも減点だ。勝利を目指すため、状況を読んで使い給え」
「……はい」
「今回は遊びのようなものだからいいが、右手にあるそれを同じように使うなよ。いいかい、綺礼?」
声色もしっかりして、まるで魔術修行の時間のようだ。時臣側から仕掛けてきたことだというのに、これは酷い。これが人間のやることかよ、などという台詞が胸をめぐる。
「……………承知いたしました」
不貞腐れた綺礼の返事に、よろしい、と微笑んで。
時臣は。
「─────ッ!」
不意打ちのキスに、綺礼が驚いて目を見開く。
その視界いっぱいに、してやったりというような時臣の笑顔。
「しかし令呪で命じられては仕方がない」
さあ、続きをしようか、と言葉が耳に届いて。
次の瞬間綺礼から仕掛けたキスは、クリームの、甘い甘い味がした。
2012綺礼誕と同じ時間軸っぽい。
何だかよくわからんのですが、
師弟にはお菓子を作らせたくなるのですよー
あと綺礼はパン焼くのとか得意そう
何だかよくわからんのですが、
師弟にはお菓子を作らせたくなるのですよー
あと綺礼はパン焼くのとか得意そう