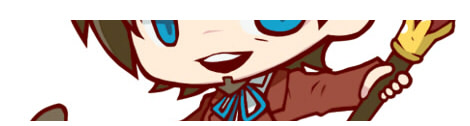
時臣が『人型の鳥』というパラレルです
その他、ギルガメッシュが富豪、綺礼がギルガメッシュ家の使用人(奴隷)
多少未完結風味
綺礼の主であるギルガメッシュは、珍しいものが好きだった。その他、ギルガメッシュが富豪、綺礼がギルガメッシュ家の使用人(奴隷)
多少未完結風味
広い屋敷を彩る調度品から日々身に付ける衣服まで。誰も見たことのないような、きらびやかで豪華で値の張る珍品が揃っている。そして綺礼自身もその一つであった。漆黒の髪と瞳は、この国では珍しいのだ。派手さこそないが、通り過ぎれば誰もが振り返る彼の闇色は、ギルガメッシュの求める珍しさのレヴェルを十分に満たすのである。
そんなギルガメッシュがその日手に入れてきたものもまた、滅多にない珍品であった。
愛識り鳥の呼び声は
「…今日はどんな趣味の悪いものを拾ってきたのだ」夕食を終えた食堂。がたごとと、白布をかけた大きなものが使用人たちによって運び込まれて来るのを綺礼は胡乱な目で眺めていた。使用人たちが退去して、あとにはその大きなものだけが残される。
「まあそういうな。オークションにかけられていたのを勝ち取ってきたのだ」
得意げなギルガメッシュの表情に、綺礼は一層呆れた顔を浮かべて更に問いかけた。
「いくら使った?」
「一億に少し届かぬ程度だな」
いつものことながら、ギルガメッシュの金銭感覚は綺礼とは全く違う。ギルガメッシュには、湯水のごとく使える金があるのだ。予想していたことではあるが相当の金額に、綺礼はため息をつく。
会話にも飽きたのか、とりあえず見ろと言ってギルガメッシュはおもむろに白布を取り去った。
はらり、と舞う布。
中から出てきたのは、細かい趣向を凝らした主柱に吊られた鳥籠だった。黒く頑丈な鉄檻、中には何か茶色いものがうずくまっている。こんなものの中にいるのだから恐らく鳥だろう、と身を伸ばし、綺礼はその中を覗きこんだ。生き物は色々と面倒くさいと思いながら。覆いが外されたことに気づいたのか、茶色いものはもぞもぞと身動きし、頭を上げる。
「────!?」
綺礼は、驚愕してその生き物を凝視した。
確かにそれは──鳥、なのだろう。翼があるから。だが、その体はどうだ。足こそ鱗の生えた四本指だが、羽毛のかわりにのっぺりとした肌が覆う腹や胸、嘴のかわりに柔らかそうな唇のある頭部、そして何より、翼があるというのに存在する両腕。その先には綺礼と同じように、5本の指が生えているのだ。顔の前方についた2つの青い目が眠たそうに瞬く。
「………これは、なんだ?」
やっとのことで声を絞り出した綺礼を、ギルガメッシュはにやにやと笑いながら眺めていた。
「見てわからぬか?どう見ても鳥であろうが」
「鳥?これが鳥だと?いや、私には、…これは………」
「人間に見える、と?」
クク、と笑うギルガメッシュに戸惑いながら綺礼は頷く。──そう、それは人間に見えた。茶色い髪に同じ色の顎髭を生やした、綺礼より少し歳上に見える男。服を着ていないため隅々まで見える整った体躯は、この年代の男性としては高さも幅も平均的なものだろう。だが、背には羽毛の生えた翼がある。髪と同じ茶色の地味な色の大きな翼だ。猛禽類のような、骨のふとい翼。人の背中に見るには不自然な形。
彼は鳥かごの床にぺたりと座り込んだまま、ぼんやりと周りを見渡していた。
「翼のある人など聞いたことがないぞ。だから、鳥なのだ、これは」
種族名など知らんがな、と言いながらギルガメッシュは手を伸ばし籠の中に差し入れた。鳥と呼ばれた男は不思議そうにそれを眺めている。指先が喉の下に触れれば、少々嫌そうな表情をしたが、逃げることはなかった。ギルガメッシュは機嫌良さそうに、それの喉をくすぐる。
「慣れれば良い声で鳴くそうだぞ」
「鳴くのか?これは」
綺礼にはどうにも、この鳥とやらがカナリヤやコマドリのような美しいさえずりをするところが想像できなかった。そんな声を出すよりは、綺礼には理解できない外国語の歌を深いテノールで歌い上げる方が似合っていると思う。
とまどう綺礼をやはりにやにやしながら眺めていたギルガメッシュは、彼に向かっておもむろに言い放った。
「綺礼、貴様がこれの世話をしろ」
「…なっ!?」
「我はこれの声が聞きたいだけだからな。面倒なことは我の下僕である貴様が行うべきだ。そうであろう?」
その台詞に、綺礼は内心歯を噛む。そう、綺礼はギルガメッシュに金で買われたのだ。ギルガメッシュの奔放な性格ゆえ対等な口を聞くことが許されてはいるものの、綺礼が彼の下僕であることはまごうことなき事実である。綺礼は、彼に逆らえる立場にないのだ。
悪趣味なことだ、と綺礼は思う。いくら美しい声をしているらしいといっても、見た目は翼を生やした成人男性だ。それを愛玩動物のように扱い綺礼に世話をさせ、ギルガメッシュはその滑稽な光景を眺めて笑うつもりなのだ。
だが綺礼は断る言葉を持てない。飽きるまでは、付き合う必要があるのだろう。
「庭に温室があったろう。あそこで放し飼いをするつもりだ」
「………ああ、わかった」
内心思うところがあるままに綺礼が頷けば、ギルガメッシュの笑みは深くなった。
「それでは任せたぞ、綺礼。此奴をせいぜい美しい声で鳴かせてみよ。
───ほれ、これが今日から貴様の世話係だ。ちゃんと覚えろよ、トキオミ」
前半は綺礼に向け、後半は鳥に向けてギルガメッシュは言った。ギルガメッシュに顎を掴まれた鳥の視線が、強制的に綺礼に向けられる。
「トキオミ?」
「これの名だそうだ。誰がつけたのかは知らんがな」
仕方なしに綺礼もその鳥の目を見返す。
ビー玉のように透き通った青は、真っ黒な男の姿を映していた。
■ ■ ■
トキオミの容姿は、人間としても美しいと綺礼は思う。とはいえ綺礼には、一般的な「美」というものが理解できないので、経験からそう判断した、というだけだが。すらりと伸びた手足は人の形として整っているし、その頭部も一般的な感覚で言えば、見目麗しいだろう。濃い眉に高い鼻梁。髪や眉と同じ茶色の濃いまつげに彩られた瞳は海のように映すものによって色を変えるブルーで、見るものを飽きさせない。だからこそ、目に悪い。
なので、トキオミの世話役に任命された綺礼が最初に行ったのは、彼に服を着せることだった。
綺礼の服では大きすぎるが、ギルガメッシュはたかがペットのために自分の服を差し出すなんてことをするはずがないので仕方ない。とりあえず、タンスの奥深くから引っ張り出してきた裾の長い服を頭からすっぽりかぶせてやれば、目に悪いものはなんとか隠れた。ただ、適当に破いただけの穴から翼を出すのはかなり窮屈そうで、その内改めて服を作ってやらなければならないだろう。
綺礼の服を着たトキオミは、まるで人間のように見えた。だがその背にはやはり翼が有り、服の裾から覗く脛は人間のものではない。ニワトリのようにオレンジの鱗に覆われ、四本指の先にはそれぞれ大きな爪のついた、鳥の足。さらにもう服に隠れてはいるが、尻の谷間から尾羽根が生えているのも確認できた。オナガドリのように柔らかく長い茶色の尾羽根だ。根本は翼と同じように白い綿毛が生えていた。全く、人ではない生き物の証だ。
「───トキオミさん」
綺礼の声に、不服そうに着せられた服を眺めていたトキオミは顔を上げない。自分の名だと認識していないのだろうか。
「トキオミさん」
もう一度呼んで顔を覗き込めば、やっと気付いたように綺礼を見た。深い色の青の瞳。だがそこには何かを思考しているような深い感情は読み取れず、あくまでも彼が人ではないのだと示しているようだった。
言いようもない違和感に綺礼の心はざわめくが、それを押し殺す。
「………籠に、戻りましょうか」
語りかけても、不思議そうに首を傾げるだけで意味を理解していないようだった、仕方なしに抱き上げ、開けておいた扉からトキオミを籠の中にしまう。トキオミは、綺礼にされるがままにおとなしくしていた。
ギルガメッシュはもう部屋に戻ってしまい、使用人たちも下がらせている状態だ。ここには綺礼とトキオミしかいない。綺礼は何だか不思議な心地がした。こんな風にギルガメッシュが手に入れてきた生き物の世話をさせられることはこれまでに何度かあったが、あくまで、珍種だとは言ってもけものの風体を出ない生き物ばかりだった。なのに、これはどうだ。───まるで、家族、が増えたようだ。
…そこまで考えて、綺礼は首を振り、思考を中断した。彼が人であろうと鳥であろうと、どうでもいいのだ。ギルガメッシュが飽きるまで綺礼が世話を焼かなければいけないという事実は変わらないのだから。
抱き上げた体は、見た目よりもずっと軽い。なるほど、鳥なのだろう。空を飛ぶためにこの体の中身は、随分と綺礼とは違う形をしているに違いない。これを人と見てはいけないのだ。綺礼は自分に言い聞かせた。
「………おやすみなさい、トキオミさん」
そう挨拶をして、今晩は綺礼も休むことにする。
ふと、トキオミに対して、年上の人間に対するように接している自分に気づいて、綺礼は自嘲げに笑った。
人として見てはいけないのだ、と自分に言い聞かせた途端にこれだ。自分は随分と見た目に惑わされる口らしい。もう騙されてなるものか、と振り返れば、トキオミのいる食堂の入り口が、暗い廊下の中で妙に明るく見えた。
■ ■ ■
ギルガメッシュの宣言通り、トキオミは温室で放し飼いにされることになった。
珍しい南国植物を育てている場所ではあるが、既にギルガメッシュはそれにも飽きており、最近ではほとんど立ち寄られていない。立ち寄るのは、その世話を押し付けられている一部の使用人だけである。だがトキオミをそこで飼うに辺り、彼らも近づくことは許されなくなった。屋敷の主であるギルガメッシュと、それから鳥の世話係である綺礼。温室に近寄ることが出来るのは、二人だけになった。
温室の中は植物を育てるために調整されていたから、それを鳥を飼うために改装しなければいけなかった。とはいえ、何本かの止まり木を用意し、餌と水を入れる器を置いてやればいいだけではあったのだが。だが一つだけ工事もあった。鳥用の便器を用意するとギルガメッシュが言い出したのだ。確かに彼は人間に似た形をしている。辺り構わずフンを撒き散らすところなど見たくはないというのがギルガメッシュの意見で、綺礼も全く同意だった。幸いなことに、トキオミは既にトイレの躾をされているそうなのである。なので、温室の端には一つ、簡易な便器が用意された。これらの工事には、全部で一週間ほどかかった。
その間、トキオミは籠に入れられたまま食堂に置かれていた。ギルガメッシュが、自分の部屋に置いておいたら綺礼が世話しづらいだろうし、綺礼の部屋に置いておけば自分が眺められない、と言ったためである。食堂に置かれた狭い籠の中で、最初に見た座った姿から殆ど動かず、トキオミは過ごしていた。
トキオミの餌は、木の実やあわやヒエ…つまり、普通の鳥と変わらない。体が大きいから量は多く必要とするものの、用意は簡単である。買い込んだ鳥の餌を、綺礼はトレイに移して籠の中に置くだけで良かった。トキオミは、綺礼の前では警戒してか余り食べるところを見せてくれなかったが、気づけばトレイは空になっている。健康上の問題もなさそうだった。
ギルガメッシュはといえば、どうやらまだ鳥に飽きはしていないようで、毎日気まぐれにトキオミにちょっかいを出していた。籠の隙間から指を突っ込んで喉や頭をなでたり、その尻に生えている尾羽根を引っ張って驚かせたり。世話など一つもしないくせに、遊んでくれる相手だと認識したのだろうか、トキオミはギルガメッシュに懐いているようであった。綺礼には面白くないが、仕方がない。トキオミを購入してきた彼の飼い主は、ギルガメッシュなのだ。自分はあくまでもトキオミの世話係でしかない。
そうこうしている内に温室の準備は整い、トキオミは食堂の狭い鳥籠から、温室へと移されることになった。
「……?」
綺礼の腕に抱かれ籠から出されると、トキオミは目を見開ききょろきょろと辺りをうかがった。
見たこともない植物が珍しいのだろう。首ごとくるくると回して辺りを興味深げに眺めれば、青の瞳にも色鮮やかな南国の植物たちが映る。それはとても新鮮にな色に見えた。
ちなみにトキオミは、1週間の間に設えられた彼用の服を着せられていた。長い裾の、前をボタンで止めるタイプの服だ。ギルガメッシュの趣味で、凝ったレース編みや刺繍が施されているが、エキゾチックな雰囲気はトキオミによく似合っていた。翼を痛めないよう、背中は大きく空いている。下着や靴下などはつけていなかった。トキオミは、人と似た形をしているとはいえ人ではないので。
「ああ、待て、トキオミ。…まだ離すなよ、綺礼」
今にも飛び出したそうにうずうずしているトキオミを制し、ギルガメッシュが手を伸ばす。その手には、子犬の首輪のようなものが握られていた。細い鎖は非常に長いが、温室に渡されたとまり木の一つにつながっている。その革ベルトの方は、トキオミの足につけるのだ。逃げ出さないように、という措置である。
「よぅし、出来た」
カチャリと小さな金色の鍵。それがギルガメッシュの手によってかけられ、赤い枷はトキオミを彩る装飾品の一つになった。人と異なる鳥の黄色い足に巻き付く、赤いベルト。それを目にすれば、なぜだか、くらりとする感覚を覚えた。
「いいぞ、綺礼。もう離しても」
ギルガメッシュの言葉に、綺礼は時臣を地面に下ろした。裸足の足が初めて土を踏み、びくりとトキオミは綺礼の服の裾を掴んだ。綺礼にぎゅっとくっついたまま、青の目を見開いて辺りを見渡している。綺礼は、そんなトキオミの様子をじっと見ていた。ふいに、トキオミの目が何かを見つける。青の瞳に映ったのはひとつの花。
トキオミが、翼を広げた。
「………───!!」
息を呑む。
綺礼の目に映ったのは、鮮やかな赤、だった。
畳まれていた時には地味な印象だった茶色の翼、しかしそれの内側の、なんと鮮やかなことか。
たとえるならば、それは炎だろう。同じ姿を二度さらすことのない揺らめく炎のように、トキオミの翼の内側はグラデーションがかった赤の羽毛で覆われていた。外側の風切羽は濃赤、内側に行くにつれて一部はさらに濃くなりまた一部は淡くなり、一番内側の三列風切は白。肩甲骨に近い付け根の肩羽は外側と同じ茶色だった。柔らかそうな羽は大きく広がり、綺礼よりも小柄なトキオミの姿を大きく見せていた。その翼が、ばさり、大きく羽ばたく。トキオミの指が綺礼の服を離れ、つま先が軽く地面を蹴った。
ふわりと彼の体が浮かぶ。
無意識の内に伸ばしていた綺礼の指先が届くことはなく、トキオミは空にいた。軽やかに羽ばたく翼から数枚の羽毛が舞い、風圧で散った南国植物の黄色い花びらと混じって幻想的な風景にくらり、めまいがするようだ。ひらひらと衣装の裾がひらめき、覗くのは成人男性の尻と足であるはずなのに、鮮やかな色に彩られ、鱗に覆われた人ならざる膝下に、倒錯的な美が見える。
羽ばたいたのは2,3度だろう。トキオミは頭上に渡された止まり木の一つの上に危なげなく降り立つと、そこに腰掛けて、鮮やかな花の一輪を手にとった。花のがくに指を添え、顔を寄せて匂いを嗅ぐ。すう、と息を吸い込んだのが離れて立つ綺礼にも見て取れた。その顔が、満足そうに笑むのも。
ああ、と、気付かぬ内にため息が漏れていた。これが『美しい』という光景なのだろう、綺礼は唐突に理解する。花を手に微笑む男。その背には炎のように鮮やかな翼が広がり、ふわふわと花びらと羽毛が舞う。天井から降り注ぐ陽の光は逆光、彼の茶色の髪や白い衣服、人ならざる足を浮かび上がらせる。まるで絵画か、宗教を描いたステンドグラスの一枚のようだった。
そして、その翼にある一部の風切羽は、途中で不恰好に断たれているのだ。愛玩用の鳥は、逃げられぬようにするために、その飛行能力を奪うためにそういう処置をするものなのである。まるで天使のように完成されたリアリティのない彼の容姿の中で、その部分だけは妙にリアルに見えて、綺礼の心臓はわけも分からぬままに高鳴った。
「ふふん、随分と気に入ったようではないか」
その言葉に、綺礼ははっとして思考を引き戻す。しかしギルガメッシュの言葉は綺礼に向けられたものではなく、トキオミに向けられたものだったようだった。広げた翼の鮮やかな色に、どうやらギルガメッシュが感動を覚えている雰囲気はなさそうだった。彼とは美の感覚が異なるのか、と綺礼は思ったが、その後、既に見たことがあるからだろうという考えに行き着く。鳥を買ってきたのはギルガメッシュなのだ。
花を眺め匂いを嗅ぎ悦に入っているトキオミの姿は、随分と楽しそうだった。とまり木からぶらりと下ろした足が、彼の意思でゆらゆらと揺れている。同じ木に咲いた黄色やオレンジの花を、あちらを眺めてはこちらを嗅ぎ、と言った風に確認しているようだった。時折遠くの木や花にも視線をやっている。その仕草は、この広い世界を気に入ったようにしか見えなかった。
「トキオミ!」
ギルガメッシュが呼べば、トキオミの視線は地上にいる二人に向けられた。指先が未練がましく花に残ったが、彼はもう一度翼を広げて空に浮かんだ。ふわりと空気をはらんで膨らむ服の裾、それがしぼんで、地面の石にあたった足の爪がカツッと小さな音を立てる。二三歩勢いを殺すかのように進んで、トキオミはギルガメッシュの前に降り立った。
「花が気に入ったか?」
ギルガメッシュの伸ばす指に、トキオミは頬をこすりつける。その仕草にギルガメッシュは微笑んで、彼の茶色の髪をわしゃわしゃと撫でた。
「そうかそうか。なら、我も用意した甲斐があるというものだな」
まるで子供か小動物でも相手にしているようだ──というところまで綺礼は考え、トキオミが成人男性の姿をしていてもあくまで鳥なのだということを思い出した。髭のある顎下を指先でこしょこしょとやるギルガメッシュの仕草は、そう考えれば納得できた。顎を撫でられているトキオミは幸せそうである。先程まで色とりどりの花を映していた青の瞳は、金と鋭い赤だけを写して、気持ちよさそうに細められた。
「………?」
それを何ともなく眺めていた綺礼は、胸の奥にちりちりするような感覚があることに気付いて見下ろした。見たところで、分厚く黒い服に覆われた胸が見えるわけでもなし、見えたとしても見るだけで何が変わるわけでもない。視線の先にはただ陽光を受けて光る十字架があるだけで、やはり何もなかった。
視線を上げれば、同じ陽光を受けてきらめく金髪の男が美しい翼を持つ鳥を楽しそうに撫でていて、綺礼の胸の違和感は一層酷くなる。
「………………?」
その違和感の名を、綺礼はまだ知らない。
鳥はまだ鳴かない。
ギルガメッシュも知らぬその鳥の鳴き声は、求愛の歌だ。
その声が響くときに、二人と一羽の関係は動き出すのだろう。
そして綺礼はようやく、その違和感に名をつけることが出来るのだ。
時臣師みたいなハンサム紳士の脳内が
けものだったらかわいいよなあといつも思っています。
あと単純に鳥が好きなので、
鳥の世話を綺礼にしてもらいたいなと思いました。
きっとこの鳥は水浴びとか超好きだぜ
けものだったらかわいいよなあといつも思っています。
あと単純に鳥が好きなので、
鳥の世話を綺礼にしてもらいたいなと思いました。
きっとこの鳥は水浴びとか超好きだぜ