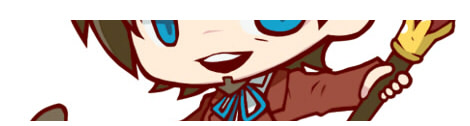
時臣死後の言→時
殺人・死体描写はありませんので安心してお読み頂けますが、
大変薄い言金言要素がございますのでご注意下さい
「ん…………」殺人・死体描写はありませんので安心してお読み頂けますが、
大変薄い言金言要素がございますのでご注意下さい
ギルガメッシュは微かな物音で目を覚ます。ぼんやりとしたまま隣にあるはずの体温に手を伸ばそうとして───そこに誰も居ないことに気がついた。
仄かな明るさに、億劫に思いながらも目を開ける。
「…ああ、起こしてしまったか」
「………ことみ、ね」
デスクランプを背に、大きく黒々とした影。それが言峰であることに気づき、ギルガメッシュはのろのろと体を起こした。ぐずぐずと目を擦るがぼんやりとした感覚は抜けない。まだ随分と早い時間なのに違いない。
カーテンの閉まったままの部屋はとても暗く、言峰の背後にあるデスクランプだけが物を見分けるための頼りだった。ただ、おそらくカーテンを開けた所でそう明るさは変わらないだろう。霞む目で時計を見れば、まだ短い針は4のところに有り、ギルガメッシュは眉間にシワをよせた。
「…こんな時間に何をしているのだ、言峰」
「出かける準備をしている」
「こんな時間にか?」
「あまり遅くなると、鉢合わせてしまう可能性があるからな」
何と、とギルガメッシュが問う前に、綺礼は彼に背を向けてしまった。
向き合っているのは壁にかけられた鏡である。いつも身なりに頓着するような男ではなかったはずだが、今日は随分と熱心に鏡と向き合い、櫛で髪を整えているようだった。
「何だ、髪型を変えておるのか」
「ああ」
振り向きもせずに言峰は鏡の自分と向き合っている。自己愛にでも目覚めたか、と軽口を叩こうとしたが、口から出たのはふわあと間抜けたあくびだけだった。
言峰は、少し伸びた後ろ毛を跳ねさせたまま、どうやら前髪をどうにかしているらしい。元から固く癖の強い彼の前髪も、目にかかるほど伸びているのだ。
はふはふと止まらないあくびにギルガメッシュが苦戦している間に、どうやらやっと言峰の目的は果たされたようだった。
「───どうだ、ギルガメッシュ」
何だかやり遂げた顔をして言峰が振り返る。
黒く硬い前髪は額の真ん中で分けられ、瞳にかからない形になっている。元々は分け目もなくただ伸びるに任せているようだった髪型に比べれば、まあ、爽やかと言えなくもないだろう。もちろん、髪がかからなくなり覗いた目は、変わらずに暗く濁っているのだが。
「ふむ、似合わんな」
「そうか」
「見慣れないだけかもしれぬがな。…しかし、どんな心変わりだ?」
ギルガメッシュが知るかぎり、彼と行動を共にし始めてから、言峰が髪型を変えるなどということはなかった。伸びてきたら切り、切ったらまた伸びるに任せる。私服はいくらか洒落たものを持っているようではあるが、元々言峰という男は自分の外見に頓着するような人間ではないはずだ。
ギルガメッシュの純粋な問いに、言峰は嬉しそうに微笑んだ。──言峰の「嬉しそうな笑み」など、もちろん他人から見ればいやらしく胡散臭いことこの上ないのだが。
恐らくは大多数が抱くであろうそれと同じ感想を抱き、ギルガメッシュは不快感を込めて鼻を鳴らした。
言峰はそんなギルガメッシュをやはり面白そうににやにやと眺めた後、デスクランプの光の届かぬ暗がりから何かを取り上げた。何かビニールで包まれた円すい形のもののようだが、ギルガメッシュの位置からはよく見えない。
「それでは少し出てくるが、」
「ああ勝手に行ってこい。我は寝る」
そう言い捨ててギルガメッシュが再度ベッドの上に体を倒した。マットは柔らかいがその下の台は固い。思ったよりも勢い良く倒れてしまったようで、打ち付けてしまった頭と肩が痛んだ。失態だ。
さぞや言峰はあのいやらしい笑みを浮べているのだろう、と顔を上げて睨みつけようとした。が。
「…………」
もう、そこに言峰はいなかった。
出てくると言って、本当にすぐに出て行ったようだ。しまりの悪い扉はまだ揺れてさえいる。
見ていなかったのならば見ていなかったと言えば良いものを、とギルガメッシュは八つ当たりのように思う。
しかし。
ギルガメッシュは寝台の中でごろりと転がった。
今日の言峰はおかしい。朝の祈りだ何だと早起きをすることは多いが、今日はどうやらちがうようだ。神父としての勤めを果たすならばもう少しいつも朝は遅いし、どこに行くのか結局はぐらかされてしまった。しかも、そこに出かける際に誰か、鉢会いたくない相手までいるらしい。手荷物まで持って、ギルガメッシュと言葉を交わす時間すら惜しいとでも言うように、急いて。
寝台の中で、もう一度ごろりと転がる。つけっぱなしのデスクランプが、閉じた瞼を貫いて眩しい。
「…………」
───気になるではないか。
元より愉悦の気配には敏感な彼である。言峰のその行動は、全て何か面白そうな気配を漂わせていた。その行動への興味は、ギルガメッシュの眠気を上回るものに膨らむ。
ギシリと寝台を鳴らし、彼は床に足をつける。大きなあくびをしながら、伸びを一つ。裸足の足に靴をつっかけながら、ハンガーに無造作にかけていたジャケットを寝間着の上から羽織る。どうせこの時間であれば誰に会うこともないだろうし、ギルガメッシュの寝間着は、寝間着といえど普通のTシャツにジャージのズボンであるから外に出るのも問題無いだろう。
つけっぱなしにされていたデスクランプを消してやり、ギルガメッシュはのろのろと外に出た。
むわり、と湿気の多いまとわりつくような空気。
未だ日の昇らぬ世界は薄暗く、何故だか嫌な予感を漂わせていた。
朝焼けの紺
パスの繋がった相手を探すのは造作も無いことである。ギルガメッシュはすぐに言峰の居場所を探り出し、そちらへ足を向けた。存外近い。というよりも、言峰の私室からは離れているが、それは教会の敷地内のようだった。
しかし、そのあたりに何があったかと思いだしたギルガメッシュは眉をひそめる。
確か、そこは墓地なのだ。
言峰は誰かの墓参りでもする気なのだろうか。だとしたら、そんな辛気臭いことは面白くもない。やはり寝て待っていたほうが良かっただろうかとは思うものの、一旦立ち上がって外に出てしまったのだから、言峰の目的を知らずに帰るというのも、どうにも癪だ。
だから仕方なく、ギルガメッシュは言峰の元へ向かうことにした。
ついてくるなと言われたわけではない。このままギルガメッシュが彼の目の前に現れた所で、咎められることもないだろう。だから堂々と。石畳の続く通路を通ることにした。
そして数分。
広い墓地の中で言峰を探すのは面倒かと思ったが、それはとても容易かった。整然と並ぶ墓碑。灰色の十字。その中に、長身の神父は体を折り曲げ真っ黒な影のように跪いていた。
だが、ギルガメッシュが彼をすぐに見つけることができたのは、その姿や色のせいではない。むしろ真っ黒な彼の姿はモノクロの景色に溶け込んでいて見えづらいほどだ。彼を見つけることができた理由は、別にあった。
───目の覚めるような、鮮やかな赤が。
彼の目前の墓碑に供えられていた。
「………」
それは、薔薇の花束だ。言峰が部屋を出るときに持って出たのが、多分これだったのだろう。大きな花弁が零れそうなほど咲き乱れている。まるで新鮮な血液を思わせるような紅はいっそグロテスクで、その墓の下に眠る人間を毒々しく卑しめているようにすら見えた。
だが、ギルガメッシュにはわかってしまった。その毒々しい花束は、その下に眠る人間に酷く似合うものなのだと。彼を、むしろ飾り立てて美しく見せる花なのだと。
───ああ、なぜならば、その墓に刻まれた名は。
朝靄に歪む影法師が振り返る。
目にかかる、中心で分けられた前髪と、首筋で跳ねる後ろ毛を揺らして。
白む、まだ薄暗い蒼を淀んだ目に映して、その瞳は深く染まる海のように。
弧を描く口元に浮かんでいるのは、いつものいやらしい笑みとは違う、酷く清廉なものだった。
その唇が開き、声が、耳に、届く。
「英雄王」
その科白は、聞き慣れた男の声のはずなのに、何故だか違う声に聞こえて──────────おもいだしたくもない。
なにかを幻視して──────────だれかのような。
ぞわり、と鳥肌が立った。
「────────とき、」
「ああ、何をしているのだギルガメッシュ。寝ているのではなかったのか?」
「…言峰」
瞬きをしてよくよく見てみれば、それはやはり見慣れた男の姿だった。
手を後ろに組み昏い目を細めてにやにやと口元を歪める姿は、いつも通り不快ではあるものの、何故だか妙に安心する。
「…別に、我が寝てようが起きようが貴様には関係ないだろう」
「そうだがね。あんな失態を見せた後で、私の前に現れるとは思っていなかったものでな」
「っ!?貴様見ていたのか!?だったら何か言ったらどうだ!」
「くくく、痛みと失態に歪むお前の顔はなかなか珍しいものだったぞ」
「〜〜〜っ、………ところで、貴様は結局何をしていたのだ」
「見ればわかるだろう。墓参りだ」
ギルガメッシュは、数歩彼に近づいた。言峰が少し立つ位置をずらし、ギルガメッシュの目にもその石碑に刻まれた文字が読めるようになる。そこには予想通り、今世に呼び出されたギルガメッシュの、唯一の臣下だった男の名が刻まれていた。不快げに眉を潜めるギルガメッシュとは対照的に、その石碑を眺める言峰の表情は酷く楽しげに見えた。楽しげ──いや、幸福そうに、というべきか。それは、ギルガメッシュの知らない表情だった。
「…墓参りは分かった。だが、なぜ今日なのだ?命日でもあるまい」
思い出せと言われてもあれが何月何日だったのかなど覚えてはいないが、それは、もっと寒い日だったはずだ。全く季節は合わないし、かといって今日という日には意味がないというわけでもないだろう。そうでないなら「誰かと鉢合わせる」可能性などそう重視しないはずだ。そんな可能性があるということは、この日に言峰以外の誰かが、この墓を訪れる可能性があるということだろう。
ギルガメッシュの何気ない問いに、言峰は笑みを浮かべる。
「───今日は、師の誕生日なのでな」
そのはにかむような笑みは、愛しい人の生まれた日を祝うという純粋な喜びに満ちていた。
───或いは、それは狂気か。
自らの手で死を与えた相手に向けるには、その瞳には愛情が満ちすぎていた。愛しくて仕方がないとでも言うように、言峰の無骨な指が石碑を撫でる。まるでその滑らかさに何かを重ねるように。冷たい石の中に、何かの暖かさを感じるとでも言うように。ぞっと、ギルガメッシュの背に寒気が走る。
「だから、ほら、今日は師を真似てみたのですよ」
言峰は、もうギルガメッシュを見てはいなかった。石碑の代わりに誰かがそこにいるかのように、口調すらも変わっている。それは共犯者ではなく、嘗ての師へ向けた。しかし、恐らくはその師すらも見たことのない笑顔で。
どうですか、似合いますか。こうしていれば、鏡を見るたびに貴方の面影を感じられる気がするのです。ああ、師よ、貴方も喜んでくださいますか。師よ、師よ、師よ────。
「───この世に生まれてくださって、ありがとうございます」
射し始めた朝日にロザリオをきらめかせながら跪き、石碑に口付けを贈る神父の姿は、見ようによっては酷く美しいものに見えるだろう。たとえ彼がそれを意図していなくとも、もちろんその愛情が歪んでいたとしても。
石碑に触れる指先も唇も、愛情にあふれたそれは酷く優しい。
唇を離し、名残惜しげに最後まで残った指先を離し、言峰は立ち上がる。
「………言峰」
「何だ、ギルガメッシュ」
「貴様は、奴を、」
「ああ、愛している」
過去形ではなく、彼は言った。
微笑みも、声も。本物だった。
「───行くぞ、ギルガメッシュ。あまり長くいると、こんな時間でも鉢合わせかねない」
今ならば、それが誰との話なのかわかる。
奴の娘のことか、と問えば、言峰はにやにやとした笑みを浮かべた。
「その通りだ。愛する父の誕生日を祝うために訪れるのだろうがな、誰のものかもわからぬ上等な花束が置いてあるのを見た瞬間の彼女の表情には非常に興味はあるが──」
「…ああ、それはいいな」
「まあ、いいだろう。送り主が私だとわかれば、彼女は捨ててしまうかもしれないからな」
あれは私が、彼に似合うだろうと選んできた品なのだ。そう簡単に捨てられてしまってはつまらない。と言峰は言う。ギルガメッシュは、そんな言葉に、ああそうだな、と頷いてやった。
言峰綺礼は歪んでいる。
そんなことは、とっくにわかっていたことではないか。
踵を返し歩きさろうとする言峰に続こうとして、ギルガメッシュはふと足を止める。思い立って上着のポケットを探れば、未開封のガムの包みが一つあった。
こんなもの、奴は口にしたことなど無いだろう。そう思うと少しだけ愉快だったから、真っ赤な薔薇の花束の隣にそれを置いてやった。今日は奴の誕生日だそうなのだ。
「…お前は、哀れだな」
弟子の歪みに気付かぬままその弟子に命を奪われ、そして死んでよりなお愛される。その全ては、恐らく彼の理解を超えるものだろう。真面目がすぎるつまらぬ臣下のことを、ギルガメッシュは初めて哀れに思った。
今となっては全て遅い。
彼が弟子に会うことは二度と無いし、弟子はその歪んだ愛を伝えることはできない。
闇に足を踏み入れようとしなかったからこそ自分に都合のいい真面目な弟子と思ったまま逝った彼、言葉を伝えずその回答を得られなかったことをいいことに自分に都合のいい師の姿を幻視する弟子。それは、もしかしたら幸福、なのかもしれないと。一瞬、昏い考えがよぎった。
「───ギルガメッシュ」
離れたところから言峰の呼ぶ声が聞こえて、ギルガメッシュは今行く、と声を張った。
朝日は既に登り始め、しらじらと世界を照らしている。
朝特有の清々しい清廉な空気、ふと視線を感じて振り返るが、そこには整然と墓碑たちが並んでいるだけだった。
2013時臣誕生日に。
初めて祝う師の誕生日が死にネタ…
五次峰の髪型が時臣に似てるよねっていう話題が好きなので
使い古されたネタですがねりこんでみた
初めて祝う師の誕生日が死にネタ…
五次峰の髪型が時臣に似てるよねっていう話題が好きなので
使い古されたネタですがねりこんでみた