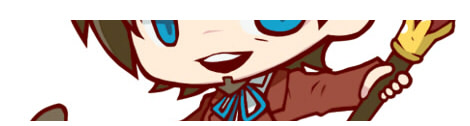
ギル←←←時からの言→→→時
ギル様が若干DV男、時臣師が恋愛脳。全員クズなNTRネタ
現パロです。中身にはほとんど反映されてないけど全員IT系リーマン
赤や緑のイルミネーション、そこかしこに吊るされたリボンやモール。金糸や銀糸を使ったオーナメントは光を反射しきらきらと輝いている。それらを指さしては談笑し、あるいはそれらに目もゆかぬように傍らの恋人を見つめ、人々はクリスマスの町を通り過ぎて行く。人々のざわめきに、控えめな音量で流されるBGMはほとんど聞こえない。ギル様が若干DV男、時臣師が恋愛脳。全員クズなNTRネタ
現パロです。中身にはほとんど反映されてないけど全員IT系リーマン
駅前の広場には、特に大きなツリーが設置されていた。もちろん本物の木ではなく、作り物だ。高さ5メートル程度のツリーのてっぺんまでをこの広場に立ったままでは見ることは叶わないが、それでも多くの人々がそのツリーの下に佇んでいた。恐らくは待ち合わせなのだろう。彼らの視線は駅の出口に固定されており、時々向こうから手を振って近付いて来る者がいれば、ツリーの下の人口は一人減った。
時臣もまた、ツリーの下で人を待つ一人である。ただし視線は駅ではなく、その正反対に。駅へと向かう人の群れを眺め、ただ一人の姿を探しているのだった。
時臣の恋人、ギルガメッシュ。
約束の時間から、そろそろ1時間が過ぎようとしていた。
Who are most of you?
ギルガメッシュに出会ったのは10ヶ月ほど前。時臣の会社が同業の他社と業務提携することになり、相手方の会社に出向いて調整をすることになったのが、当時は営業であった時臣だった。そして、その応対をしたのがギルガメッシュだったのである。社長と紹介されても過言はないような横柄な態度で出迎えられ、第一印象は最悪だった。しかし、いまいち立ち位置の分からないこの男は時臣の青い瞳を不躾に覗き込み、言ったのである。
───ほう?綺麗な青ではないか。繰り抜いて指輪にでも嵌めれば、さぞや良い輝きをするのだろうなあ。
初めて出会った相手に顎を掴まれて目を覗きこまれ、そんなスプラッタな発現をされたわけだ。恐ろしさや嫌悪感を抱くのが当然だろう。だが時臣は違った。
───本当に?本当に私の目は、綺麗ですか?
そんな反応をされるとは思わなかったのか、これにはギルガメッシュも少し驚いたような顔を浮かべた。
───ああ、美しいと思うぞ。
だが彼は、そう言い切ってくれたのだ。
その瞬間の時臣の喜びを、ギルガメッシュが正確に把握することは、きっとないだろう。
ずっと、時臣にとってその瞳の色はコンプレックスだった。今はもう亡き母から受け継いだ色だ。嫌いではないし、むしろ誇りに思っている。だが子供というものは、自分と違うものを迫害したがるいきものだ。青い目を持つ時臣は、黒い目を持つ子どもたちにとっては格好のいじめ対象だったのである。大人にも味方はいなかった。異端を受け入れさせるという面倒を、拒んだのだ。
そうして敵だらけの世界を、持って生まれた忍耐強さと生きていくうちに身につけた駆け引きの腕で生きてきた。口先だけで時臣の瞳を褒めるものはいたが、彼らの口調は昔の子どもや大人たちを彷彿とさせた。だから時臣は、これまでほとんど人の言葉を信じたことはなかった。
だが、目の前のこの男はどうだ。嘘とも揶揄とも無縁の声音で、時臣のことなど全く知らないというのに時臣をを肯定した。
言葉をなくした時臣を少々不審げに見ていたギルガメッシュだが、やがて時臣から手を離すと元の席に戻ってしまった。そしてやっと、打ち合わせが開始される。事務的な言葉の応酬の中で、その声が確かに、時臣をただ肯定してくれたのだと考えてしまえば、どうにも落ち着かなかった。
一目惚れとは違う。
だがそれは、確かに恋だった。
そして、艱難辛苦を乗り越えた末に、時臣はギルガメッシュを恋人として手に入れたのである。
業務提携がうまくいくことを祈願した飲み会、酔って千鳥足のギルガメッシュが心配だからという口実で一緒に乗り込んだ終電。誰もいない車両の、妙に距離の近い隣りに座って伝えた無謀な愛を、ギルガメッシュは受け入れてくれたのだ。
にやりと笑っていきなり塞がれた唇は、たっぷり三駅分、のしかかるようにして奪われた。ぼんやりとした視界に見たいたずらっ子のような彼の笑顔が自分に向けられているのかと思えば、どうしようもなく胸が締め付けられた。
それが愛だと、確信していた。
■ ■ ■
時臣は、腕時計を覗きこむ。短い針が真上よりも少し左に、長い針がちょうど真下を指していることを確認し、はあ、とため息をつく。冷たい空気に白い呼気が舞った。寒さに小さく身震いをし、左腕の時計を右手で握りしめる。
その腕時計は、付き合い始めた初期の頃、時臣の誕生日がとうに過ぎていたことを知ったギルガメッシュが与えてくれたものだった。淡い青の文字盤にピンクゴールドの縁。華奢な3本の針にはそれぞれ上品な小さいダイヤが付いている。どこからどうみても女性物のそれは、しかしチェーンだけは時臣の腕に合わせて伸ばされていた。恐らくは、ギルガメッシュがわざわざ注文したのだろう。似合うものを選んでくれたのかと思えば、そのデザインが女性向けのものであろうが関係はなかった。純粋な嬉しさだけがこみ上げる。
時臣がギルガメッシュと待ち合わせをするとき、いつも共に待ってくれるのがこの腕時計だった。ギルガメッシュを待って、どれだけこの時計を覗きこんだだろう。ギルガメッシュが待ち合わせの時間に現れることなどほとんどなかったからだ。そして姿を表した時にはいつだって言うのだ。なんだ、まだ待っていたのか、と。
「………」
今日も、それを言われるのを待っている。
ギルガメッシュが勝手なのは今に始まったことではないし、待ち合わせの時間に現れない以外にだって、これまで色々なことが合った。
例えば、時臣のジャケットのデザインが気に食わないとボタンをむしりとったり、デートの途中で「お前はつまらん」と言って急に帰ってしまったり。不機嫌なときに話しかけて怒鳴りつけられたり髪を掴まれたりしたこともあった。部屋で会うときには、したくないと言うのを無理やり押さえつけられ、縛られて気絶するまで犯されたことさえある。
最初は、確かに愛していたはずだ。彼に告白したのは自分のほうなのだから、彼に嫌われないようにしようと卑屈になってしまったのがいけなかったのかもしれない。彼のわがままはエスカレートするばかりで、いつか、もしかしたら彼に殺される日が来るのではないかとすら思ってしまう。先日は戯れに首を締められ、そのときのギルガメッシュの嫌な笑みを思い出すと、体が震えた。
………いや、震えたのはきっと寒いからだ。息すら白い。
そういえば朝のニュースで、今日は気温が氷点下まで下がるだろうと言っていた。だからだ。
「………」
人の波は、やや落ち着いてきたようだった。
ざわめきが落ち着くと、急にかかるBGMが大きく感じる。聞こえるのは、ジングルベルだった。しかし安っぽいオルゴールのような音は、オーケストラに慣れた時臣の耳には耳障りだった。
指先に、はぁ、と息を吐きかけてこする。一瞬だけ温かい呼気が指先にあたったが、それだけだった。吐息の中の水分が付着したのか、さらに冷たささえ感じる。手を合わせたまま腕時計を見れば、針はまた進んでいた。あと、15分。15分で今日は終わる。
時臣は、腕にかけていた紙袋を抱え直した。小さい赤い紙袋は、覗けば中に赤いリボンの掛けられた包みが見えるだろう。それは、時臣から恋人へのクリスマスプレゼントだった。中身はマフラーである。残念ながら手作りではないが。いつだって派手な色の衣服ばかり着ているギルガメッシュだから、一本くらいシックな色のものがあってもいいだろうと思って選んだ、焦げ茶色のマフラーだ。
「………」
───会えたとして、受け取ってもらえるのだろうか?
きっとこの品は、彼の意に沿わぬものだろう。時臣が、彼に似合うと思って選んだ、などという理由は、ギルガメッシュにとってはどうでもいいものに違いない。全ては自分の意思通りにことが進むことばかりを、彼は望んでいる。だからこそ、これを渡された時、彼は…
いや、だが恋人同士なのだ。わがままも言われるし無体も働かれるが、それでも彼は時々とてもやさしかった。料理に失敗して値の張る肉を焦がしてしまった時など頭をなでて慰めてくれたし、時臣の帰宅が深夜になったときには玄関で出迎えて抱きしめてくれた。愛されているのだ。愛されているはずなのだ。待ち合わせを守らなかろうと、首を絞められようと、つまらないと詰られようと。
「………ぁ、」
ふいに、前触れもなくぽろりと涙がこぼれた。戸惑っている間に、それは次々と落ちていく。慌てて手の甲で拭おうとして、その水分の熱さに自分で驚いた。それだけ、この指は冷えきっていたのか。
通り過ぎて行く人々が奇異の視線を自分に向けていくことに気づく。当然だろう、いい年をした男が、一人で泣いているなんて。だがそんな、誰のものかもしれない視線などどうでもいい。それより早く涙を留めなければならなかった。もしもこのタイミングでギルガメッシュが現れたのなら、絶対に激怒して帰ってしまうだろうから。だが思えば思うほど涙は止まらない。厚手のコートの袖で拭うものだから、目の周りがヒリヒリしだした。
その、時だった。
「───────時臣さん!!!」
名を呼ぶ声に、驚いて顔をあげる。走り寄ってきた黒い男は息を荒げながら、少し高い位置にある視点で時臣を見下ろす。感情の読めない黒い瞳は怒っているように見えて、時臣は少しだけ体を引いた。
「こんなところで何をしているのですか?ああ、そんなことよりも。何故貴方は、泣いているのですか」
「…きれい」
「大丈夫ですか。泣かないでください、時臣さん」
困って時臣は、その男───言峰綺礼を見上げた。
彼は、前のプロジェクトで同じチームだったチームメイトである。技術力もさることながらスケジュールを立てたり調べ物をするのも得意だったので、プロジェクトリーダーである時臣の補佐のようなことまでしてくれた。どうやらその時にずいぶん懐いてくれたらしく、それから二年以上が経った今でも、時々は二人で飲みに行ったりするような仲の相手だった。
時臣は綺礼のことを気に入っている。だからこそ、こんな姿を見られたくはなかった。
「なんでも、ないよ」
「なんでもないことはないでしょう。今自分がどんな顔をしているかわかっていますか?」
こんな日に恋人にふられた女のような顔をしていますよ、と言って綺礼はハンカチを取り出して時臣の目元を拭おうとした。なんという的確な比喩だろう。
大丈夫だよ、ありがとう。そんなばかみたいな顔をしていたかい?時臣は苦笑して、そのハンカチを受け取り自分で目を拭う。柔らかい布地は、ひりついた目元をなぞっても痛みを与えはしなかった。
「洗濯して返すよ」
「お気にせずに」
強引に奪い取ると、綺礼はそのハンカチを無造作にコートのポケットへとねじ込む。
「しかし本当に、なにをしていたのですか?どなたかをお待ちのように見えましたが」
「そう見えたかい?いや、ただ時間を潰していただけだよ。終電にはまだ時間があるからね」
「3時間もですか?」
「………」
「偶然ですが、先程そこのコンビニにで買い物をしたんです。その時も、貴方はここに立っていました」
ちょうど三時間ほど前のことです、という綺礼に言葉をなくし、時臣は目をそらす。
見られていた。見られていたのか。
言い繕う言葉すら探せずに、視線だけがうろうろと彷徨う。
「私は………」
言うべきなのだろうか。恋人を待っているのだと。迷っているうちに、綺礼が表情を変えないままに口を開いた。
「───ギルガメッシュですか」
「ッ!?」
時臣は驚いて綺礼の顔を見上げる。
何故、それを。時臣は綺礼にギルガメッシュと付き合っていることを話したことがないし、そもそも恋人がいることさえ話したこともない。男同士だし、それに自分たちの関係が他人から見れば歪んでいるように見えるだろうこともわかっている。だからこそ、綺礼どころか誰にだって言ったことはなかったというのに。
動揺する時臣を前に、それでも綺礼は淡々と言葉を続ける。
「…来ませんよ、彼は」
「な、何故」
「第二システム部の飲み会があるんだそうです。さっき女性社員に誘われて、行くと浮かれていたのを見ました」
「………」
約束したのは、先々週の日曜だった。24日の夜は空いていますかと問えば営業部の飲み会だと断られた。それならば25日はと問えばその日は空いている、と。それなら一緒に何処かへ行きませんかと誘ったのは時臣で、じゃあディナーにでも行くかと提案してくれたのはギルガメッシュだった。その日は優しい日だったから、どうせなら高いワインでも頼むかと言ってくれたし、嬉しいと喜ぶ時臣を抱きしめて額にキスさえくれた。
先に約束をしたのは、自分なのに。
彼の自分勝手なところはちゃんとわかっていたはずだ。待ち合わせの時間に現れないなど、いつものことじゃないか。その飲み会とやらに参加した後に、きっとこちらへ来てくれるはずだ。きっとそうだ───その、はずだ。きっと。きっと。
「………時臣さん」
「………」
「…………………時臣さん」
「………」
「時臣さん」
ぎゅう、とコートの裾を掴んでいた手を、そっと取られる。
手袋越しでも温い体温が伝わってくる。それに比べ自分はなんて冷えているのだろう。暖かさは伝わってくるのに、触れられている感触すら無い。赤を通り越して白くすらなった時臣の指先を、綺礼はゆっくりと撫でる。
「やめましょう」
「………なにを」
「あんな男など。やめてしまえばいい」
綺礼に擦られる指先をぼんやりと見つめた。言われている意味は、よくわからない。
「私はずっと、貴方を見ていました。あの男に振り回され、悲しんだり苦しんだりしている貴方を。貴方は気付いていなかったかもしれませんでしたが、貴方の目はいつも、あの金色を追っていたのですよ」
「………」
「覚えていますか?3ヶ月前くらいのことです。出社した貴方は、頬を赤く腫らしていました。何があったのか、聞いても教えてくれませんでしたね。だけど、貴方の姿を見かねている私に、あの男から教えられたのです。あれは、我がやったと」
「………」
「激高する私に、奴は言いました。あれは我のものだから何をしたっていいのだと。そこまで言われても、貴方は奴を許すのですか?…ああ、今貴方がここにいることこそが、その答えですね。わかりきったことを聞きました。すみません」
感覚がないほど冷えきっていた指先は、今や火傷でもしそうなほどに熱い。不意に綺礼は、左手でその指を握ったまま右手で、時臣の頬を拭った。親指が濡れた跡をなぞるが、頬も冷えきっているのだろう、触れられた感覚はなかった。
「私は貴方を敬愛しています。ずっと貴方を見ていました。貴方は完璧で素晴らしい人だ。そんな貴方が、モノのように扱われることなど許せない。だから…あんな男など、やめてください」
「でも、ギルは」
「愛しています、時臣さん」
はっとして綺礼を見上げた。
光さえも飲み込むような漆黒の瞳が、ただ時臣だけを映している。いつもと同じ何を考えているのかわからない無表情のくせに、その瞳は酷く真剣で、時臣は言葉を失った。触れられている指が、頬が、その部分だけ熱い。
───恋を、していた。
どんな風に扱われたって胸の一番上のところにいるのはいつだってギルガメッシュで、彼にそばに居てもらうためには何だってした。彼に微笑んでもらうために、彼に喜んでもらえるように。どんな風に扱われたって、ただ一人、自分を損得もなく肯定してくれた相手に尽くすため。
それは恋だ。確かに恋だった。
だが。
だが、しかし。
もしも、彼ではない誰かが、自分を肯定してくれるのだとしたら───
「わ、私の話はつまらないよ」
「そんなことありません。貴方は私の知らないことを良く知っている」
「私のセンスは、悪いし、」
「原色や金銀ばかりを好むほうがどうかしています」
「ど、どうにもうっかりしてしまうから、迷惑をかけてしまうし」
「愛する人を支えることは幸せですよ。むしろ、私に貴方を支えさせて欲しい」
「………」
だから、あの男をやめて、私を選んでください。と、綺礼は言った。
「………本当に?」
「本当です」
「ほんとうに、私でいいのかい………?」
「貴方がいいです。貴方だから、いい」
綺礼の目に自分が映っている。それを見ている時臣の目にも綺礼が映っていることだろう。
止まっていた涙が再び溢れだした。ああ、泣いてばかりだと時臣は思った。頬を伝う涙は熱くて、それを拭っていく他人の指先も熱い。あとからあとから溢れる涙にぼやける視界で、それでもしっかりと綺礼を見つめながら、時臣は頷いた。
「………うん、」
「時臣さん」
「っ、うん………、うん…!わたしも、君がいい…っ!」
嗚咽が混じって、最後はうまく言葉にならなかった。言い終わるやいなや、綺礼に抱きすくめられる。強く強く抱きしめられ、二人の間にある厚手のコートが邪魔だと思った。肩口に顔をうずめて、声を上げて泣く。後頭部を撫でてくれるてのひらが、背を抱き寄せる腕が優しくて、嬉しくて悲しかった。
───ギルガメッシュのことを愛していた。愛していたのはでも、きっと自分だけだったのだ。だからこんなにも悲しくて惨めで悔しくて、体は冷えきっていた。それを、綺礼は抱きしめてくれる。愛してくれるという。時臣だからいいのだと言う。それは、ついぞ時臣が貰ったことのないものだった。
名前もわからない感情に揺さぶられるままに、わあわあと時臣は泣いた。
全てこの涙と一緒に流れてしまえ。
そして、新しい感情を受け入れられるように。
そのままどれくらい抱き合っていただろう。涙がようやく止まっても、名残惜しく時臣は綺礼の肩に顔をうずめたままでいた。時々しゃくりあげる背をあやすように撫でてくれる手は優しく、つい甘えてしまいたくなる。
いつしか人通りは全くなくなり、ジングルベルも聞こえなくなっていた。静かな駅前に、わびしくイルミネーションだけが輝いている。
「………ん、すまなかったね、綺礼」
「いいえ。もう、大丈夫ですか?」
「ああ、大丈夫だよ。ありがとう」
ようやく、そっと時臣がからだを離す。離れると、急に寒く感じた。身震いをする時臣の姿を見て、綺礼は自らのマフラーを外す。時臣が何か反応をする前に、綺礼はそれを時臣の首にしっかりと巻きつけてしまった。
「寒いところにずっと居たからでしょう。これくらいしかありませんが、どうぞ」
「いや、そうしたら君が…」
そこまでいいかけてふと、時臣は自分の手にあるものを思い出す。躊躇したのは、一瞬だった。
「…もし良かったら、これを使ってくれないか…?」
「これは?」
「………本当は、ギル、にあげようと思って、用意したものなのだが…」
自分でリボンと包みを解いて、綺礼に渡す。こうすれば、プレゼントの体裁は保たれなくなると思ったので。目をそらして複雑な表情を浮かべる時臣の顔を見つめながら、綺礼はありがとうございますとそれを受け取り、自分の首に巻く。綺礼の黒いコートに、その焦げ茶色のマフラーは酷く良く似合っていた。
「私が貰ってしまっても良いのですか?」
「違う人のために用意したものだから申し訳ないけれど、…君が、嫌じゃないのなら」
「嫌なことなんてありませんよ。愛する貴方がくれるというものが、嫌なわけがありません」
ですが、そうですね、と、真っ赤になった時臣を置いて綺礼は続ける。
「実は、もう少しで私の誕生日なのです。もしよろしければその時に何か、私に似合うものを選んでくれませんか?」
「ああ、もちろんだとも!」
嬉しくなって、時臣は微笑む。綺礼も笑っているように見えた。彼がこんなにやわらかい表情を浮かべるのをは初めて見た、と思う。
「そろそろ行きましょうか。私も寒くなってきました」
「ああ、それならばうちにくるかい?ここから近いんだ」
「…誘っているのですか?」
「…えっ」
そう、ほんのさっきから二人の関係は変わったのだ。家に行く、という意味も。時臣は赤面する。
これまで行っていた、二人で飲みに行ったり互いの家に遊びに行ったりという行為には、これからは別の名がつく。そしてきっと、ただの同僚であった時には縁のなかった行為が、それらの中に紛れ込んでくることだろう。それは、どうなのだろう。幸せなのだろうか。きっと幸せなのだろう。
「…綺礼」
「はい」
「そうだよって言ったら、…君はうちに来てくれるのかい?」
「っ、そんなこと…!もちろんです…!」
力強く頷く姿に、時臣は苦笑する。まだ、関係が変わってしまってから数分だ。それなのに、自分を求めてくれる。本当に、彼は自分を愛してくれているのだ。
綺礼の手を、ぎゅう、とつかむ。じゃあおいで、微笑んで言ったつもりだが、もしかしたら頬がこわばってしまったかもしれない。こんな風に人を誘うのは初めてなのだ。綺礼も少し緊張したようにぎこちない笑顔を浮かべて、はい、と頷いた。
「時臣さん、手が冷えきってしまっていますよ」
「ああ…今日は手袋をしてこなかったから」
「私のを貸します」
「そうしたら君が寒いだろう?さすがに、手袋の替えは持っていないし、それに腕時計をしているんだ。上から手袋なんて出来ないよ」
「それならば、空いた手を繋ぎましょう。恋人っぽいと思いませんか?」
「、あ」
綺礼の手が時臣の左手を取り、そこに巻かれた腕時計を静かに外す。その瞬間小さな声を漏らした時臣を綺礼は訝しげに見たがそれきりで、自分の左手から外した手袋を冷えたその手に嵌めた。
綺礼のコートのポケットへとしまわれていく腕時計から、時臣は目をそらした。あの時計を見ながら恋する人を待つ時は、終わったのだ。
だから時臣は、その時計が本当に綺礼のポケットにしまわれたのかを最後まで見届けなかった。
「…どうされました?」
「いや…なんでも、ないよ」
「そうですか?…それでは、行きましょうか。貴方の家へ、案内してください」
彼となら、きっと幸せになれる。彼は自分を愛してくれているのだから。そして、きっと自分も彼を愛することができるだろうから。
ギルガメッシュにしてあげたかったことを、いっぱいしよう。それから、できれば自分がして欲しかったことをいっぱいしてほしい。それをきっと綺礼は、許してくれる。
だから、時臣は裸のままの右手を、そっと綺礼の指に絡めた。綺礼は、それを強く握り返してくれた。
「───行こう、綺礼」
■ ■ ■
───日付が変わって1時間。
誰もいなくなった駅前に、息を切らした男が一人、立っていた。
彼はその日───いや、変わる前の日付に、その場所で大事な相手と待ち合わせをしていたのだ。だが、予定が入ってしまった。業務提供先の社長も参加するという飲み会。そことの橋渡しを務める営業である彼が、それを欠席するわけには行かなかった。
このご時世だというのに携帯電話も持っていない相手にそのスケジュール変更を伝えるすべもなく、結果がこれだ。この場所には、もう誰も居ない。
我儘の通る相手だと思っていた。一時間二時間の遅刻だったら、彼は困った笑顔を取り繕いながら、許してくれるはずだった。そんな顔を見ていると、こんな自分など見捨てて帰ればいいのにと、どうしても気持ちと違う言葉が出てしまうのが、自分の悪い癖である。
男は男なりに、相手を愛していた。相手が必要以上に卑屈になるのが嫌で、随分と無体を働いた自覚もある。だが、それでも相手は男を愛してくれた。その愛が揺らぐ日がくるなど、思ってもいなかった。
「………」
足元に落ちたモノを見て、男は歯噛みする。
それは、彼が相手に贈った腕時計だった。
後悔はきっと、もう遅かった。
このあとギル様のスーパーNTR返しタイム。
そうだNTRネタ書こうと思い立ったはいいのですが
綺礼さんがキレイキレイすぎて…誰や
あと時臣さんが相当な恋愛脳ですみませんでした
そうだNTRネタ書こうと思い立ったはいいのですが
綺礼さんがキレイキレイすぎて…誰や
あと時臣さんが相当な恋愛脳ですみませんでした