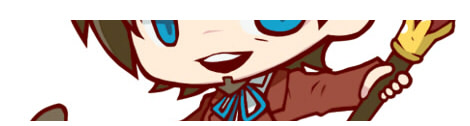
時臣と綺礼がショタ化。現パロ。
綺礼&璃正誕生日話です。
綺礼&璃正誕生日話です。
神様ではかなえられないお願いひとつ
「おや、綺礼じゃないか」「ときおみさん!」
新しい消しゴムが欲しかったので買い物に来た商店街。そこで時臣が出会ったのは、隣の家に住む4つ年下の綺礼と、その父璃正だった。
時臣を見つけた綺礼は急いで彼のもとに向かおうと、繋いでいる父の腕をぐいぐい引っ張る。璃正は微笑ましい顔をして、綺礼に引かれるままにしていた。綺礼は時臣のことが大好きなのだ。
「やあ、時臣くん。お買い物かい?」
「ええ、私は消しゴムを買いに。璃正さんたちも、買い物ですか?」
「ああ、そうなんだ」
「ケーキ屋さん、ですね」
璃正が少し掲げてみせたのは、駅前にあるケーキ屋のパンフレットだ。何かの記念日や誕生日には、時臣もよくこのケーキ屋でケーキを買ってもらう。3日前のクリスマスも、ここのブッシュドノエルを食べた。砕いたミルクチョコレートとチョコの生クリームがデコレーションされたもので、とても美味しかったと記憶している。上に乗っていた、プレゼントを象った砂糖菓子の甘さを思い出して、思わず時臣の頬はほころんだ。
だが、ケーキを買うというのなら、何かあるのだろう。
「今日は、何かの記念日ですか?」
「わたしのたんじょう日なのです」
ずいっと一歩踏み出して、綺礼が時臣を見上げた。あまり感情の出ない子供ではあるが、むふーと鼻息を漏らし、どこか得意げな表情だ。
「へえ、そうなのか。ごめんね、知らなかったよ。おめでとう」
「ありがとうございます」
「だったら、何かプレゼントをおくりたいな。綺礼、何か欲しいものはあるかい?」
「い、いいのですか!?」
時臣が尋ねると、綺礼は父の手を握る手に力を込め目をいっぱいに開いた。父と時臣にせわしなくきょろきょろと視線を往復させるのは、驚きと嬉しさを表しているのだろう。良かったな、と父に頭をなでられると、はい!と大きな声で返事をした。
そして綺礼は幼い顔を精一杯難しくしてうーんと悩みこみ、そして何か決意したような顔をして時臣を見上げる。
「それなら…、ときおみさん、今日は一日、わたしとあそんでくれませんか?」
「そんなことでいいのかい?」
今度目をぱちぱちとさせたのは時臣の方だった。もともと綺礼は物欲がない方である。ない方というよりも、璃正が心配になるくらいに彼は何も欲しがらない子供だった。それを時臣も知っているからこそ金額的に困るようなものを綺礼が望まないだろうことは想像していたが、まさか遊んでほしいとは。
やっぱりこの子も子供なんだなあ、としみじみしてしまうが、そんな時臣もまだ11歳だったりする。遊ぶのはもちろん、好きだ。
「もちろんだとも。いっぱい遊ぼう」
「!!」
綺礼は、ぱあっと顔を輝かせた。表情のどこが変わったというわけではない。わからない人には分からない程度の、些細な雰囲気の変化だ。だが、ここに綺礼の感情が読めない人間などいない。綺礼よりも年上の子どもと大人は、目を合わせてにっこりと笑った。
「そうだ、時臣くん。これからケーキを買いに行くのだが、君も一緒に来るかい?」
「いいんですか?」
「一緒に選んでくれれば、これも喜ぶだろう」
大きな父の手に頭をぐりぐりと撫でられて、綺礼がくすぐったそうな顔をする。
「じゃあ、ぜひ」
「ときおみさんもいっしょですか?」
「いっしょにケーキ、選ぼうね」
時臣が手を差し出すと、綺礼は空いていた方の手でぎゅうっと時臣の手を握った。時臣を見上げる瞳は、いつになくきらめいているようだ。相当嬉しいのだろう。年下の友人に好かれることが嬉しくない時臣ではない。そもそも時臣だって綺礼のことが好きなので、そんな表情を浮かべられてしまえば、時臣だって嬉しくなるのはもちろんだった。
両手に父と大好きな年上の友人の手を握った綺礼は、なんとなく無敵になった気がして、鼻息も荒く走りだした。
「あ、待って綺礼!私後ろ向きだから!!」
どうやら左手と左手をつないでしまったらしい。
慌てて綺礼は、時臣の右手を掴み直した。
■ ■ ■
綺礼には、ケーキの良し悪しがわからない。
白いのと茶色いのとピンクのがあって全部味が違うということはわかる。ピンクのは甘いのに酸っぱくて、茶色いのはコーヒーの苦い味がするから、白いのが一番美味しいと思う。だけどわかるのは色と味だけで、その上の飾りのことはよくわからない。
父はこれはかわいいなと言うし、年上の友人はこれは綺麗だねというのだけれど、綺礼にはぴんとこないのだ。そもそも、かわいいとか綺麗とか別にどうだっていいと思う。だってケーキなのだ。切って食べてしまえば、その元の形なんてわからないのだから。
だが、父や友人がかわいいとか綺麗とか言って喜ぶから、綺礼もそれが嬉しいものだと思うことにする。うさぎが乗っているのはかわいい。バラが咲いているのはきれい。ふわふわの白いクリーム。
「どっちにするかい、綺礼?」
父の問いかけに三分ほどじっくり時間をかけて二つのケーキを睨んで、最終的に綺礼はバラを指さした。
父は毎年ケーキを選んでくれるけれど、時臣が選んでくれることなんて今後あるかどうかわからないから。そんな子供の悲壮な決意に気付かないままで、そうか、もうお前もうさぎさんっていう年ではないのだなあ、などと父は息子の頭を撫でた。
「お誕生日ですかー?」
店員の男がそんな三人を見てにこやかに話しかけてきた。不良みたいなオレンジの髪をしているが、どうやら子供好きらしい。細めた目が、綺礼と時臣を交互に映している。
「ええ、この子の誕生日で」
「ローソクお付けしますね!何歳です?あ、プレートにお名前書くサービス、無料ですよ」
「ありがとう。ローソクは8本でお願いします」
「はーい」
「プレートも戴けますかな?」
「はーい。お名前いただけますかー?」
「きれい、です」
「き・れ・い・くん。はい、承知しましたー。ちょっと、待っててくださいね」
店員は少々崩れた字でメモ帳に「きれい」と書き殴ると、ガラスケースの中からバラのケーキを取り出してくるりと後ろを向いてしまった。ふんふんと機嫌のいい鼻歌が漏れている。
「綺礼」
何をしているのだろう、とレジの向こうを覗こうとしていた綺礼は、時臣に呼ばれて振り返る。
「ケーキ、美味しそうだね」
「はい」
「綺礼は、生クリーム好きだったかい?」
「きらいではありません。茶色いのとピンク色のよりは、好きです」
「あはは、オペラは大人の味だよね。私もまだ、あんまり得意じゃないなあ」
「ときおみさんも、茶色はにがてですか?」
「いつか、こくふくするつもりでいるけどね」
「さすがときおみさんです」
「綺礼もいつか、大丈夫になる時が来るよ」
そしたらいっしょにオペラ食べようね、と時臣が言ってくれるのが嬉しくて、綺礼は、はい!と元気よく返事をした。あんな苦いものを食べられるのは、きっと大人に違いない。そんな大人になるまで時臣といっしょにいる約束ができたということが、とても嬉しかった。
いつのまにか、店員はプレートを書き終わっていて、ケーキの箱詰めも完了していたらしい。オペラも美味しいんだけどねー、子供にはまだ早いよね、と言ってへらりとした笑顔を浮かべた後、璃正に向かって、2400円です、と料金を請求した。
またどうぞーという店員の声に見送られ、大人一人と子供二人はまた町の中に戻る。
璃正の右手にはケーキが新しく追加されたが、綺礼の両手には大好きな二人の手が変わらずにあった。
■ ■ ■
「今日は一日一緒に遊ぶ」という約束を守るため、時臣はその足で綺礼の家へお邪魔することにした。家族には、買い物に行くついでに図書館へ寄ってくるかもしれないと伝えてあるから、少しくらい遅くなったって平気だ。お邪魔しますと声をかけて、脱いだ靴を行儀よく玄関に並べる。
声をかける、と言っても綺礼の家は、綺礼と璃正との二人暮らしだ。綺礼のお母さんは、綺礼が赤ん坊の頃に亡くなったらしい。人の家の事情に首を突っ込むような無粋な真似をするようには育てられていない時臣だから、余り詳しくは知らないが。
まあとにかくその家は二人暮らしで、二人暮らしにしては充分広い家なのである。
靴を脱いだ時臣は、綺礼に腕を引っ張られながらリビングへ向かった。
リビングには四角くて背の低いテーブルが置いてある。座布団を引いて床に座る形だ。時臣の家にあるのは背が高くて椅子に座る形のテーブルだから、いつも座りなれない。綺礼は部屋の隅に積んである座布団を三枚引っ張り出してきて、テーブルのこっち側に二枚、むこう側に一枚を置いた。こっち側の二枚は小さくて、向こう側の一枚は大きい。時臣に、綺礼の隣に座れというのだろう。
「ありがとう」
「ざぶとんをしくのは、わたしの係なのです」
「おや、綺礼。今日は儂の座布団も出しておいてくれたんだね。ありがとう」
先にちょこんと座った綺礼の隣に腰を下ろすと、折よく璃正が戻ってきたところだった。お盆を持っていて、その上にはオレンジジュースが満たされた三つのコップとスナック菓子が盛られた白いお皿が置かれている。
そのお盆をテーブルの上に置き、よっこいしょと掛け声をかけながら璃正は座布団に腰掛けた。そしてにやりとした笑顔を浮かべて、時臣に向き直る。
「時臣くん、綺礼はいつも、自分の座布団を出すと儂の分を出すのを忘れてしまうんだよ。困ったものだろう?」
「ち、ちちうえ!」
「はっはっは、時臣くんに嫌われたくなかったら、次からは儂の座布団も出してくれるかな?」
「もうぜったい、わすれません!!」
膝で立ち上がって机の向こう側の父親に言い放つと、綺礼はぷうっと頬をふくらませてそっぽを向いてしまった。璃正ははっはっはと豪快に笑っているが、だしに使われた時臣は苦笑するしか無い。
そしてやっと笑いをおさめた璃正が、ぽんと手を拳で打つ。
「そうだそうだ、ケーキも開けねばな。時臣くん、手伝ってくれるかな」
璃正が傍らに置いていた綺麗な紫の袋をテーブルの上に置き、そして中から白くて四角い箱を取り出そうとした。袋にひっかかってなかなか出てこないので、慌てて時臣は袋を引っ張って外す。璃正はありがとうと言って箱をテーブルの上に置くと、四辺に貼られていたセロテープを丁寧に剥がした。
「さて、二人で開けておいてくれるかい?包丁を取ってくるよ」
「はい!」
璃正が立ち上がる。綺礼がわくわくした瞳を時臣に向けた。先ほどへそを曲げたことなどもう忘れたらしい。時臣に、箱を開けてくれと言うのだろう。その視線に時臣は頷いてやり、膝立ちになって白い箱に手を伸ばした。
セロテープは剥がされているから、あとはかぶさっているだけの蓋を持ち上げるだけだ。時臣は両側に小さい手を添え、慎重に蓋を持ち上げた。
「わぁ…!」
漏れた感嘆の声は一つ。もう一つの口はぽかんと開いたままだった。
時臣が声を上げたのも無理は無い。そのケーキは、店で見た時よりもずっと綺麗に見えたのだ。
白い生クリームで覆われた全面。上には絞り出したような形で、同じクリームがたっぷりと乗っていた。側面には赤、緑、黄色の小さなマカロンがクリームで貼り付けられていて、白の多い色の中で鮮やかさを演出していた。
上面には時臣が気に入ったバラの飾りがある。いや、店で見た時にはただの飾りだと思ったのだけれど、それは実はクリームで出来ているようだった。生クリームではないもう少し硬いクリームのようで、時臣も綺礼も知らないが、それはバタークリームで出来ていた。食紅か何かで色をつけているのだろう、花びらはまろやかなピンク、葉は鮮やかな緑色をしていた。
そして何よりも二人の子供の目を引いたのは、もちろんその真ん中にドンと配置された白いプレートだった。それは分厚く、どうやらチョコレートではなくてマジパン製らしい。下辺の短い台形の形をしており、そして平面いっぱいに、茶色いチョコペンで文字や絵が書かれていた。上品な見た目のケーキ本体に比べると随分可愛らしいが、アンバランスさはない。
「…、…、…、…、…き、れ、い、く、ん」
「ハッピーバースデー、って書いてあるんだよ」
「たんじょう日おめでとう、ですか?」
「そうだよ、よく知っているね、綺礼」
ひらがなだけを読んだ綺礼に、時臣は英語部分に何が書いてあるのかを教えてやった。
とても綺麗な文字である。それに、最初の「H」の左上部分や、最後の「y」の下部分をくるりと巻いていたりと、遊び心満載の文字だった。
文字のないスペースには、クローバーをくわえた小鳥やハートマークが隙間をうめつくすかのごとく描かれているし、「きれいくん」という文字だって、クッキー文字のようにかわいらしく書かれている。あの店員は、随分こういったプレートを書き慣れているのだろう。
「おお、綺麗なケーキだね」
戻ってきた璃正がケーキと、ケーキを覗きこむ子どもたちを眺めて微笑んだ。子どもたちはまるで血のつながった兄弟のように、柔らかい頬に同じ笑顔を浮かべて頷いた。
■ ■ ■
八本のローソクは三人で立てて、ローソクに火をつけるのは、璃正にサポートしてもらって時臣がやった。途中五本もマッチを折ってしまうというハプニングもあったが、なんとか八本ともに火は灯された。
ぱちりと璃正によって部屋の電気が消され、カーテンも閉めた部屋には暗闇が満ちる。ゆらゆらと小さな火が揺れるローソクの先端だけが部屋の明かりの全てという状況だ。璃正と時臣は声を合わせてハッピーバースデーの歌を歌う。歌の終わりと共に、大きく息を吸った綺礼が、思いっきりローソクを吹く。見事に八本は一息で消えたので、時臣は歓声を上げて手を叩いた。
そして電気が再度つけられ、ケーキが切り分けられる。私はいいですからという時臣の前にも三等分に切ったケーキが置かれ、結局三人で食べることになった。ちなみに、プレートはもちろん切り分けず、綺礼の皿の上に置かれている。ケーキは見た目通り上品な味で、大人である璃正はもちろん、時臣と綺礼もぺろりと平らげてしまった。綺礼は名残惜しそうにプレートを取っておいたが、最後にようやく口に運ぶ決意を堅めたのであった。
それからジュースとおやつを頂きながら最近のことを話す。時臣と綺礼の家は隣同士だし通う小学校もいっしょだけれど、意外と知らないことは多いのである。例えば綺礼は生き物係だから、冬休みの間も三日に一回学校のにわとりの餌やりに行っていることとか、時臣が図工の授業で描いた静物画が地区のコンテストに入賞したことだとか。綺礼はさっきのお返しのつもりなのか、買い物に出かけた璃正が財布を持ってくるのを忘れてしまって、綺礼を店においたまま慌てて家に帰って取ってきたことがあったというエピソードを時臣に教えてくれた。そんな璃正は明日誕生日だということも。
それから、初めて算数のテストで100点を取ったということも。
「ときおみさんが教えてくれるおかげです」
「そんなことないよ、君が勉強を頑張ったからさ」
綺礼は時臣に勉強を見てもらっているのだ。正直なところ、綺礼はあまり勉強が出来ない。特に算数だ。できない、というか、よくわからない。5たす7が12だとか、それから3引いたら9になるということはわかるのだけれど、なぜそうなるのかがわからない。わからなくて考えてしまうので、12という数字を書く前にテストの時間が終わってしまうのだ。
それを、時臣は果物の絵を描きながら教えてくれた。リンゴが5個、みかんが7個。だからこの場所に果物は12個あるんだ。この中から好きな果物を3つ私が食べちゃったら、9個になるね。それから綺礼はずっと算数のテストの時、リンゴとみかんと、それで足りない場合はバナナやスイカを描きながら計算をすることにし、その結果、今回は満点を取ったというわけだ。
ちなみに、漢字は覚えればいいだけだし、国語は先生の喜びそうなところを文章の中から抜き出せばいいだけなので、そこそこ出来たりする。
そんな話をしていれば、いつの間にか外はオレンジ色に染まっていた。
冬の日が落ちるのは、早い。
「そろそろ、帰ろうと思います」
予定をたてた今日の分の宿題もやっていないし、いくら図書館に寄るかもと言ったって、そんなに遅くなるわけにも行かない。時臣は台所で食器を洗っている璃正に断って立ち上がろうとした。そのズボンの裾を握って時臣が立ち上がるのを阻んだのは、綺礼だ。
「帰っちゃうんですか?」
「うーん、まだ、宿題をやっていないんだよ」
「…でも、わたしと、一日あそんでくれるって、言ってくれました」
しょんぼりとうつむく綺礼。時臣は困ってしまった。宿題をやらないと。それに、両親に心配をかける訳にはいかないし。だけど、綺礼と遊ぶと約束もしたのだ。綺礼は、ほとんどわがままを言わない子供である。なのに、今時臣の服を掴んで、去ろうとする時臣に言い縋って。綺礼は時臣のことが大好きなのだ。そして時臣もまた、綺礼という年下の友人のことが大好きなのである。
ズボンを掴む手を、時臣はゆっくりと握った。
「うん、宿題は明日やることにする。お母さんたちに、綺礼の家でもう少し遊ばせてもらうって、断ってくるよ」
その一言に、綺礼は顔を輝かせた。いつもはほとんど表情が変わらないくせに、時臣の言葉にだけは表情を変えすぎである。
その時、台所から璃正が顔を出した。
「時臣くん、それなら今日は泊まっていくかい?」
「え?」
「綺礼も、そのほうが嬉しいだろう」
「いいんですか?」
時臣の顔も輝く。この年の子供にとって「お泊り」という響きは甘美すぎた。しかも、大好きな友人の家で、である。
「お母さんに断ってきますっ!」
普段の優雅さも何処へやら。時臣は一目散に家を飛び出していった。
■ ■ ■
一時間くらいして戻ってきた時臣は、お泊り道具一式を抱えていた。パジャマに着替え、タオル、歯みがきセット。改まって、今日はよろしくお願いしますと玄関で頭を下げる律儀さを、璃正は微笑ましく見守った。そして綺礼にぐいぐいと腕をひかれ、時臣は本日二度目のおじゃまを果たしたのであった。
それから二人で一緒に遊んだ。
落書きをした。色鮮やかに先ほどのケーキの絵を描く時臣に感心する綺礼は何故か黒しか使わない。ちなみに綺礼はモノを描くのは壊滅的に下手だが、人を描くのはとても上手だった。どことなく劇画タッチな父と年上の友人を描いてみせるので、時臣はちょっとだけ引いてしまった。
オセロをした。時臣のほうが年上なので上手なのは当たり前だから璃正が後ろから綺礼に色々とアドバイスをするのだが、負けず嫌いの綺礼はそれに断固として従わず、結果、綺礼が勝利を上げることは1回もなかった。
夕飯の手伝いをし、一緒に夕飯を食べた。今日は綺礼の誕生日だから綺礼の好きな献立だと璃正が言ったとおり、メニューは麻婆豆腐だった。綺礼は、これのとても辛いのが好きなのである。ただし璃正はそこまで辛いのが好きではないから、まずは普通の味のを作ってから綺礼のにだけ香辛料やスパイスを足すのである。その量たるや、それを見ていた時臣の食欲を減退させてあまりあるものではあったのだが、言峰家ではどうやら普通のことらしい。時臣と綺礼が並べた皿に璃正が料理を盛りつけて、三人で揃って「頂きます」を言った。
テレビを見た。といっても、そのドラマを見たかったのは璃正だったので、子どもたちは本当に『見ているだけ』だったのだが。それでも、家でほとんどテレビを見ない時臣は真剣に画面に見入っていたし、綺礼はそんな時臣の横顔を眺めるのに忙しかった。
二人で風呂に入った。水鉄砲にはしゃいだり、時臣が家から持ってきた黄色いアヒルで遊んだり、互いの髪や体を洗い合ったり。湯船は一人で入るには広いが、二人で入るには狭い。どうにか工夫して二人で肩まで浸かれる方法を考えているうちに、どうやらいつもよりも長く浸かりすぎてしまったらしい。のぼせてぼんやりしている二人を、慌てて璃正が掬いあげた。
おやすみなさいをして綺礼の部屋に上がったあとは、二人で並んで布団に潜り込みながら、色々な話をした。時臣の幼なじみの友達の話や、綺礼が最近すごく気になっているクラスメイトのこととか。いくら話したって話は尽きないが、時間だけは容赦なく過ぎていく。
だんだんと瞼が重くなるのを感じて時臣が時計を見れば、もうそろそろ夜の10時だった。
「そうだ、綺礼。これを」
「これは…?」
ごそごそと自分の荷物を漁って、時臣は何かを綺礼へと差し出した。
「誕生日、おめでとう」
差し出され綺礼が受け取ったそれは、小さな四角をしていて、軽く、綺麗に包み紙とリボンがかけられていた。どこからどう見ても、プレゼントである。時臣は、さっき家に帰ったひとときでこれを用意してくれたのだ。
慌てて綺礼はその包みを開く。赤いリボン、水色のストライプの包み紙。そして中から出てきたのは、透明の四角い箱に入っている小さなクマのキーホルダーだった。小さいながらも手足がちゃんと動く構造をしている、しっかりとした造りのクマだ。
時臣が、プレゼントをくれた。一緒にいてくれるだけじゃなく、プレゼントまでくれた。その喜びに、綺礼は小さなクマを抱きしめる。
「あ、ありがとうございます…!」
「時間がなかったから、あんまり選べなかったんだけど。かわいいだろう?」
ビーズで出来た黒いつぶらな瞳が綺礼を見つめている。しかし綺礼はその愛らしい顔立ちよりも、その首元に小さく括りつけられた青いリボンが気になっていた。
何故なら。
「…このクマ、ときおみさんににていますね」
「そうかい?」
「ときおみさんも、いつもリボン、結んでいます」
言われていつもの服装を思い出せば、確かにそこにはリボンタイが結ばれている。母の趣味ではあるが、時臣も気に入っているファッションだ。
「そうだね、おそろいだ」
「あの、ときおみさん」
「なんだい?」
「ときおみさんと遊べない日は、このクマをときおみさんって呼んでもいいですか?」
時臣は、自分が小さかった時のことを思い出す。忙しくてなかなか会えない父が、クリスマスにうさぎのぬいぐるみをくれたことを。そして、こっそりとそのぬいぐるみをお父さん、と呼んでいたことを。
「―――うん、いいよ」
「ありがとうございます!」
綺礼は頬をバラ色に染めて力強くお礼を言った。バラ色の頬で頬ずりしながら小さなクマを抱きしめる姿は幸せそのもので、時臣は、プレゼントの選択も返答も間違っていなかったことに安堵の息をついた。
「さ、もう寝ようか。もう、10時だよ」
嬉しそうな綺礼の目は、半分くらい閉じそうになっている。自分だって眠いのだから、年下の彼だってもっと眠いだろう。
「まだ…ときおみさんと、おはなし、します」
「今日はお泊りなんだよ?明日にだって話せるよ」
「あしたも…」
「うん、ここにいるよ」
「ときおみさんも、いっしょに、ねましょう」
「うん、私もねるよ」
ふわりと綺礼は微笑んだ。
時臣は一回布団から立ち上がって、電気の紐を引っ張る。一回、二回。これで、豆電球だけの明かりになる。
「おやすみ、綺礼」
「おやすみなさい、ときおみさん」
温かい体温が擦り寄ってきて、抱きついてくる。時臣はその体を抱き返してやった。
「ときおみさん」
「うん?」
「わたし、こんなに幸せなたんじょう日は、はじめてです。ありがとうございました」
「ふふ、喜んでもらえてうれしいな。私も、君に喜んでもらえて幸せだよ」
「だいすきです、ときおみさん」
「私も大好きだよ、綺礼」
やがて、すう、と聞こえてくる寝息。
時臣は暗闇の中で目を眇め、眠りに落ちた年下の友人の顔を眺めた。
今日が誕生日の綺礼に色々なものをあげられたとは思うけれど、同じくらい色々なものを貰ってしまった気がする。来年はもっともっとたくさんのものをあげたい。もっともっと、彼の喜ぶ顔が見たい。
それより、明日もまだ綺礼と一緒にいられるのだ。朝から一緒にいられるなんて初めてだ。一体何をしよう?考えるだけで、とても楽しくなってくる。
こっそりと微笑む時臣の胸元に、既に夢の中の綺礼が頭を擦り付けた。
■ ■ ■
璃正は、居間で一人で新聞を読んでいた。今日は時臣が遊びに来ていたから、余り自分の時間を取る暇がなかったのである。
とはいえ、時臣は手のかからない子だった。時々綺礼の友達が遊びに来ることがあるのだが、あの金髪の子供はなかなかに奔放だ。気を抜けばお菓子を全部食べつくしジュースを全て飲み干し、綺礼のおもちゃを持って帰ろうとしたところで、おなか痛いと脂汗を垂らしながら璃正に泣きついてくるのだ。ジュース飲み過ぎである。
まあ彼の場合は綺礼と同じ小学二年生だから、多少は仕方ないところはあるのだが。対する時臣は六年生。手がかからないのも当たり前である。
だから璃正はちゃんと自分の時間を取る事もできたのだが、どうにも二人の様子をうかがってしまっていた。なにせ、綺礼は時臣が大のお気に入りなのである。なにか迷惑をかけてはいないか、本当は時臣が嫌がっているのではないか、そう思ってしまうのだ。だが幸いなことに時臣の側でも綺礼を好いてくれているようで、随分と嬉しそうに相手をしてくれる。
しかし、来年は時臣も中学生。そうそう綺礼と遊んでくれる時間も取れないだろう。それでも、相手をしてくれればいいのだが、と思ってしまうのは、やはり息子の喜んでいる顔を見たいがためのわがままになってしまうのだろうか。
ふいに、コンコンとリビングの扉が開かれた。
驚いて振り返る璃正の前で扉は開かれ、茶色い髪がこそっと覗く。
「時臣くん?」
「良かった、まだ起きてたんですね、璃正さん」
ほっとしたように微笑んだ時臣がするりとリビングに入ってくる。服装は、さっき寝室へ行く前と同じくパジャマだ。足元は璃正のスリッパを履いている。子供の足にはもちろん大きすぎて、歩けばぱたぱたと音がした。
そのまま時臣は璃正の前まで進んでくると、じっと璃正の顔を見上げた。目は、少し眠そうだ。
「どうしたんだい。眠れないかな?」
「いいえ、そうじゃなくて…」
時臣は少しもじもじと視線をうろつかせたあと、覚悟を決めたように後ろに隠していたものを璃正へと差し出した。
「これは…?」
「り、璃正さんも、誕生日だって聞いたので…!!」
「儂にもくれるのかい?」
それは小さな四角い包みだった。綺麗にリボンまでかけられている。はっとして時計を見れば、0時を少し超えたところだった。もう今日は29日、確かに、璃正の誕生日である。
時臣はこれまで璃正の誕生日など知らなかったはずだ。先程の雑談の中にそんな話題が出てきて、初めて知ったことだろう。それから自由になった時間といえば、一回家に帰ったあのタイミングだけだ。その時間で用意してくれたのだと思うと、なんだかくすぐったい気がする。
「ありがとう。開けてもいいかい?」
「はい!」
「おや、これは…キーホルダーかな?」
箱のなかに入っていたのは、小さなクマのキーホルダーである。この時点で璃正が知る由もないが、それは綺礼のキーホルダーと色違いでお揃いの品だった。綺礼のものは青いリボンで、璃正のものは赤いリボンである。
「昔、時臣くんがこんなリボンをしていたのを思い出すよ」
「あ、あの、綺礼にも、私に似てるって言われました」
「綺礼にも同じものをプレゼントしたのかい?」
「色違い、ですけど」
「かわいいね、ありがとう」
頬を染めて、時臣は照れたような笑顔を浮かべた。璃正はその頭を優しく撫でてやる。
「じゃあ、あの、寝ます」
「ああ。綺礼が邪魔かもしれないが、ゆっくり寝るといい」
「邪魔なんかじゃないです!一緒に寝ると、暖かいですし」
時臣は微笑んで、そう言った。
「じゃあ、おやすみなさい、璃正さん」
「ああ、おやすみなさい、時臣くん」
「お誕生日、おめでとうございます」
ぺこりと頭を下げ、来た時と同じように時臣はそっと扉を閉じる。ぱたり、と閉ざされた扉、ぱたぱたと階段を上がっていく足音を聞き届け、璃正はふうと息をつく。手の中には小さなクマのキーホルダー。
目の高さまで持ち上げると、ビーズの目と目が合う。クマは片手を上げた格好で璃正の目をじっと見つめ返している。よく見ていればくるくるとした茶色い毛並みさえ、少年を思い出しそうで璃正は苦笑する。本当にいい子だ。綺礼だけでなく、自分も祝ってくれるとは。
時臣くんの誕生日は6月だったかな。璃正は思い出す。半年も先だと忘れてしまうだろうか。
いや、今のうちから用意しておけばいいのだ。そういえばこのクマのシリーズに、白い毛並みをしたものがあったはずだ。あれを、自分だと思って、と渡してみようか、と考えたところで、流石に吹き出す。別に、見立てさせる必要はないのである。
ちゃんと彼のほしいものをリサーチしておかなければ。
その日まで、彼が息子と仲良くしていてくれればいいのだけれど。
(…いや、綺礼が離さないかもしれないな)
せめて時臣の負担にならないよう、自分が間に立ってやらなくては。
子どもたちを見守る優しい父の顔をして、璃正は赤いリボンを巻いたクマをそっと撫でた。
やがて朝が来て、子どもたちが目覚める。
三人の幸せな時間は、そうしてまだまだ続いてゆくのだ。
2013綺礼&璃正さん誕生日に。
璃時好きなんですが書いたことないなと思って。
なんかいろいろこじらせた挙句のショタ化…
綺礼くんにケーキ食べさせたかったのです。
璃時好きなんですが書いたことないなと思って。
なんかいろいろこじらせた挙句のショタ化…
綺礼くんにケーキ食べさせたかったのです。