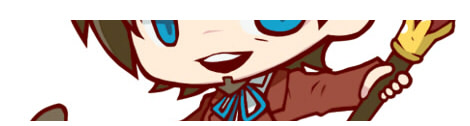
時臣師の下半身が山羊(ケンタウロス)
という設定の原作沿い?パラレル
という設定の原作沿い?パラレル
MY LOVE GOAT♥
「やあ、君が綺礼くんだね」言峰綺礼は困惑していた。
とはいえ、常通りの無表情の仮面からその困惑を読み取ることは、生まれた時から綺礼を知っている彼の父ですら難しいことであったろうが。
「璃正さんから話は聞いているかもしれないが、私が遠坂時臣だ」
男が一歩踏み出すと、かつりという足音が高く響いた。低く優しい声と深淵さえ覗き込めそうな碧い色の目に引き込まれそうになる。
元々父から魔術師に会うと聞いていたし、その外見に驚かないようにと言う言葉もあった。だから綺礼はそれなりに覚悟はしていたのだ。それに綺礼は元代行者。根源へ至るための試行錯誤の道程で二目と見られぬ姿になった魔術師と対峙したことも、少なからずある。
そんな綺礼を困惑させた魔術師の姿。それは、これまで見たどんな異形よりも醜かったわけではない。むしろ、多少目に光が足りないものの彼の顔かたちは整っているといえよう。
だがその整った頭部、薄いが広い肩幅、それが纏う腰の絞られた赤いジャケット、その下。普通ならばそのジャケットの中へ重なるようにして纏われるであろうスラックスを彼は履いておらず、それどころか靴すら彼は身に着けない素足であった――その、毛むくじゃらで足先に爪ではなく蹄をもつ脚を、素足と呼ぶならばの話だが。
そう、彼には蹄があった。髪とは異なる白色の毛がみっしりと生えた脚があった。しかも、四本。
人の頭、人の胸、人の腹、それが、獣の体に乗っている。
あれは馬だろうか。いや、男自身の背丈は綺礼より少し低い程度。馬にしては小さい。それに毛も長い。あれは、あれは――多分、山羊だ。
よく見れば男の頭にはぐにゃりと巻いた小さな角があった。顎鬚も生やしているようだし、彼は人でありながら、山羊であるのだ。
男と綺礼の父は、何か綺礼へ語りかけながら何故か綺礼の周りをぐるぐる回っている。聖杯がどうの、魔術がどうの。なんでも綺礼は、数日前に手の甲に浮かんだ謎の文様のためになんたら言う戦争に参戦してこの時臣という男に手を貸さねばならず、その準備として彼へ弟子入りをしなければならないらしい。
なんとも荒唐無稽な話であるが、今の綺礼にとっては些細なこと。それより、時臣の脚が石床を踏むときにはかつかつ鳴り、敷かれた絨毯を踏むときには小さな偶蹄の足跡を残すのを、耳で目で追うのに忙しかった。
時臣の肩からは当たり前ではあるが腕が伸び、五本の指を持った手がワイングラスを揺らしている。だが、その腹の下には前脚二本と後ろ脚二本がしっかり生えているのだ。彼の骨格を想像する。肩甲骨と肋骨の二対ある、妙に背骨の長い歪なかたち。
ああ、と綺礼は気付かぬうちにため息をついていた。あの完成された上半身と獣の下半身の組み合わせ。あの歪なかたちこそが、『うつくしい』と言うものなのではないだろうか。
ふいに、綺礼の周りを回っていた二人の足が止まる。どうやら話は終わったらしい。ほぼ聞き流してしまったが。
「何か質問はあるかね?」
「――、一つだけ」
時臣の声に、綺礼はそう返す。
ああ、これだけは聞いておかねばならない。あの歪なかたちへの興味は一つの質問などでは到底足りないが、綺礼は彼へ弟子入りするというのだ。ならば時間はたくさんある。だから、まずは小手調べの一つ。
「――貴方は、トイレでどうやって尻を拭くのですか?」
その瞬間の、驚いたような彼の顔と言ったら!
* *
そして晴れて言峰綺礼は遠坂時臣に弟子入りした。
かたちこそ歪なれど、綺礼の師は大変まともな人間だった。正しいことを好み、努力を重ね、足ると思われる量を手に入れてもなお努力。家庭よりも自身の研究にのめり込み融通の効かないようなところと多少うっかりしているところはあったが、それを理解し支える妻と娘を持ち、彼女らへ夫として父として愛を返す。どこをとっても非のない完璧な人物像。
だがその下半身は山羊なのだ。
仰向けに寝転がることはできず、夏場は獣臭を纏い、人の腕はトイレに行っても獣の尻まで届かない。土地の管理者として、土地を犯そうとする外来の魔術師へ容赦なくその杖を向ける際も、背後から見ればつんと立った短いしっぽがふりふりと揺れているのだ。まさに台無しである。
「私だってね、生まれた時からこんな体ではないのだよ」
彼の娘が二本足である理由を聞いた時、時臣はそう教えてくれた。
「昔敵対した魔術師にかけられた呪いの解呪方法がわからないだけなんだ……」
「はぁ……」
よくわからないが、そういうことらしい。
そのまま、もう数年。諦めたわけではないが、慣れてしまったのだと彼は言う。ちなみに普段外出するときは、他人から見た時に普通の人間に見えるような幻術の魔術をかけているのだという。そのせいで自分も獣の腰から下があることを忘れ、扉に挟まったり他人を蹴り飛ばしてしまうこともあるのだとか。
その補佐が、綺礼の役割になった。
妻を伴っては出られない魔術師の会合でも弟子ならば入り込めるし、男同士であるから風呂や着替えの手伝いだって気を負わずに頼める。時臣にとって綺礼という存在は、聖杯戦争に挑むための補佐というだけでなく大事なものになっていったのだった。
一方、綺礼の方でも時臣に対して抱く感情があった。歪なうつくしいかたちはいくら眺めても飽きないし、そんなうつくしい姿がうっかり尻を扉に挟んだり硬い床に蹄を滑らせて転んだりするのを見ると何故か胸が高鳴った。だが、その感情の名がどうしてもわからない。
「時臣師」
「うん?何だい、綺礼」
「腰の辺りの毛並みが乱れています。ブラッシングを、させて頂いても?」
だから、綺礼は積極的に行動にしてみることにした。思う通りに動けば、その感情の名を知ることができるかもしれないと。
弟子からの突然の申し出に目をしぱしぱと瞬かせた時臣は、少しの沈黙を置いた後、それではお願いしようかな、と答えたのだった。
時臣の執務室、彼のための柔らかな絨毯。そこに時臣は四本の脚を折って座り込んだ。
この体では椅子には座れないのだろう。かつて人型であったときの名残かこの部屋には重そうな執務机と椅子もあったが、それはどちらも暫く使われた形跡がなかった。代わりに絨毯と、背の低い書き物机が設置されているのだった。
綺礼もその隣に座る。立っているときは綺礼の方が背が高いが、座れば時臣の方が高い。前脚を折ると正座しているようなものだし、人の上半身の下に獣の体高もあるのだから当然だ。
時臣は、どこか不安げな様子で綺礼を振り返る。当然だ、この弟子がブラッシングさせてくれと言い出すのは初めてなのだから。というより、時臣は誰かにブラッシングされたことすらない。普段は自分で整えているからだ。髪さえ、誰かに梳かしてもらった記憶もなかった。
「失礼します」
宣言して、綺礼は時臣の獣の身体に触れた。ふさふさとした毛は短いが柔らかく、温かい。獣の背中と人の肩が連動してひくりと震え、ああこの体は真に一つなのだ、と改めて思う。何度か撫で付けて毛並みの流れを確かめると、綺礼はそっとその毛並みにブラシを宛てがった。そのまま、髪を梳くように動かす。
髪ほどブラシの通りは良くないが、毛が短いおかげでたやすく動かすことができた。ブラシの通った後には、梳かれ整った毛並みが残る。
「いかがですか?」
「ああ、――気持ちがいいよ」
意外にもそんな声が返ってきた。他人にこんなことをさせたことはないだろうから、もっと嫌悪感を持たれるだろうと思っていたのだが。――別にその顔を見たかったというわけではない。
だが心地良さそうに深い息を吐くのを良いことに、綺礼はブラシをさらに時臣の体へと滑らせた。
背中をなぞり、尻側に向けて毛並みを整える。脚はそれぞれつま先の方へ向けて。髪に似て少し癖のある毛並みはくるくると波打っていたが、ブラシを通すことで綺麗に揃うのだ。
自分ではやっていたとは言え、それでも手の届く範囲には限りがあったのだろう。獣の脚の先端の方に強くブラシをかければ、はあ、とまた気持ち良さそうな吐息が漏れた。
「師よ、脚を。――失礼します」
「ああ……」
時臣の前足を少し持ち上げさせ、その隙間にブラシを入れて付け根の毛並みを整える。そこも気持ちがいいのか、無意識にだろうが時臣は、獣の身体を揺すってブラシに体をこすり付けるようにしていた。
「綺礼、こちらも……」
「はい、導師」
ねだられるがままにブラシを走らせていく。それは既に毛を梳くというよりかゆい場所をかくような、そんな行為になっていた。正しくブラッシングである。
時臣の目は、とろりと半分閉じていた。綺礼にはごわごわと固いだけの毛のブラシにしか見えないが、毛で覆われた獣の体にはよほど気持ちがいいのだろう。くたりと力の抜けている獣の体を横にさせ、腹側にブラシを入れる。少し長めの毛が絡まっているところは、指も使って丁寧に梳いた。
「ふ……ぅ……」
「気持ちが良いのですか?」
「ん……きもち、ぃ……」
恍惚そうな笑顔を浮かべて時臣が答える。その漏れる声の、何と耳に毒であること。気持ちがいいという感情がその音と言葉の前面に押し出され、吐息を含んで掠れた声。力の抜けて為すがままの体と潤んだ瞳。
獣の本能が勝って、気持ちが良すぎて眠ってしまいそうというところなのかもしれないが、腹に素手で触れても足を持ち上げさせても全く抵抗なく受け入れられるというのは、何か悪い気を呼び起こしそうな感じがした。
――こういうよくないものは、早く終わらせてしまうに限る。
綺礼は邪念を振り払うように首を振った。もう殆ど目を閉じかけている時臣の後ろ足を持ち上げ、腹の下の方にブラシをかけようとした、――その時。
綺礼は失念していた。その男の腹から下が獣のものだという、その意味を。
時臣は常に赤いジャケットと白いシャツ、青いリボンタイをきっちりと身につけている。逆に言えば、彼が身につけている服はそれだけだということ。何故ならば、獣の身体に合う服などないし、獣は元々服を着ないものだからだ。
つまり綺礼が横たわる彼の後ろ足を片方持ち上げれば、そこに見えるのは。
「………………なるほど。」
普段はそんな風に。そしてその一部だけには毛が生えておらず肉色がむき出しに。ふむ。と頷いて綺礼は持ち上げていた足をそっと下ろす。つい、凝視してしまった。もしかしたら自分は混乱しているのかもしれないと自身に言い訳するかのように考える。
(しかし……、ということは)
彼は自身の妻や娘の前でも、下半身裸でうろついているということである。いや、獣にも胸はあるのだから、全身の三分の二ほどは丸出しだということだ。これは罰せられるべき悪徳ではないだろうか。
真っ当な精神を持つ師、きっちりと着込んだスーツ、優雅な笑み。なのにその下半身は異形で、おまけに丸出しである。それは彼の崇高な精神に比べ、余りに歪な姿。
――ああ、私はこの人を愛することができる。
そんな想いが綺礼の胸をよぎる。静かに胸が高鳴っていた。もしかしたら、本当に彼こそが綺礼へ答えを与えてくれる存在なのかも知れないと、思った。
時臣はいつの間にか寝入ってしまったようで、すうすうと寝息を立てていた。幸せそうに笑んだ表情で、体を綺礼に預けたまま、きっと綺礼の想いには気付かないままで。
ひとまずは、またブラッシングをさせて頂く機会を作らねば。
そう決意を込めて強く頷く綺礼の横顔を、窓から差した明るい陽光が照らしていた。
ケンタウロスが…好きなんです…
あの野性味あふれるしなやかな姿は本当に素晴らしい
なのでうちの山羊臣さんは山羊足臣さんでも
角臣さんでもなく、ケンタウロス臣さんです。
少し獣臭いのを気にしていたりとか、
山羊の本能で脅かされると硬直したりとか
そういう山羊臣さんが欲しいです
あの野性味あふれるしなやかな姿は本当に素晴らしい
なのでうちの山羊臣さんは山羊足臣さんでも
角臣さんでもなく、ケンタウロス臣さんです。
少し獣臭いのを気にしていたりとか、
山羊の本能で脅かされると硬直したりとか
そういう山羊臣さんが欲しいです